インタビュー/玉置 崇さん|それぞれの教員が自らの働き方を振り返り、「個別最適な働き方改革」を【今こそ問い直す!先生を幸せにする「働き方改革」とは⑤】
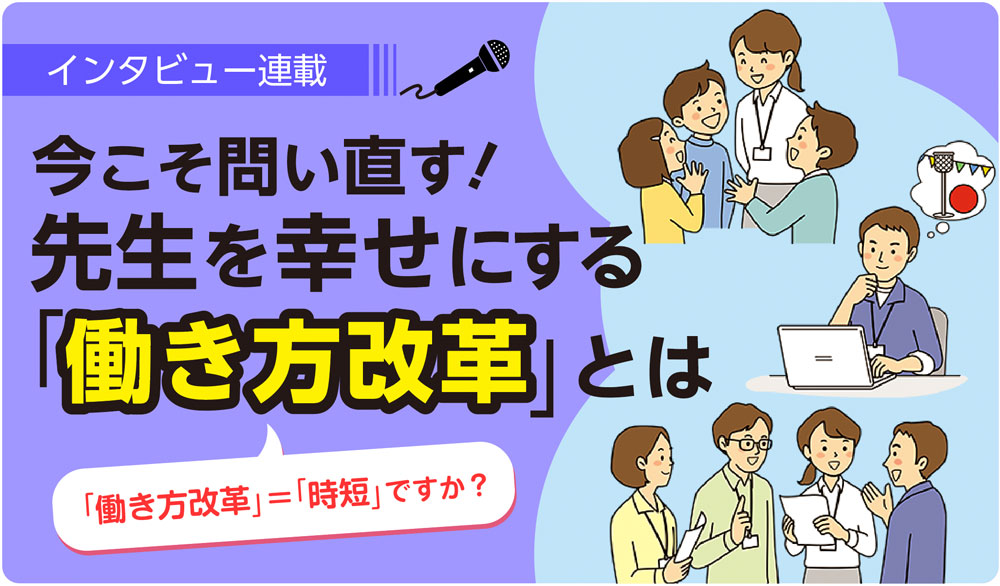
全国の学校で、今進められている「働き方改革」。ともすると時短ばかりが強調されがちですが、本当の意味で教師の仕事にやりがいや楽しさを感じられる改革になっているのでしょうか。学校教育のオピニオンリーダーの方々に改めて「働き方改革」の本質を語っていただきながら、子供も先生も皆が幸せになる「これからの教師の働き方」について考えていきます。連載第5回目は、岐阜聖徳学園大学の玉置崇教授にお話を伺いました。
〈プロフィール〉
玉置 崇(たまおき・たかし)
1956年、愛知県生まれ。公立小中学校教諭、国立大学附属中学校教官、中学校教頭・校長、県教委主査、教育事務所長などを経て、2015年4月より現職。教員養成に精力的に取り組みながら、学校や自治体のアドバイザーとしても活動中。文部科学省の各種委員会の委員を歴任。『スクールリーダーの“刺さる”言葉 教職員、子どもの心を動かす55のフレーズ』(明治図書出版、2023年)など著書多数。

目次
学校で今、先生たちに何が起きているか
「『働き方改革』だから、とにかく早く帰れとそればかり言われます。子供たちのためにやりたいことがあっても、家に帰るとやる気力が出ず、 結局やらずじまいになってしまいます。玉置先生は、教員時代にいろいろなことにチャレンジしておられて、私も刺激を受けていますが、今はそういう気持ちをだんだん失っていっています」
「私には、行事で子供を育てていきたいという強い思いがあります。しかし、行事がどんどん削られて、行事を通して育んでいくべき大事なものが、『働き方改革』の名のもとに欠けていっていると感じます」
「校内研修がどんどん削られていきます。もっと学びたいのに、本当にこれでいいのかなと思うことがあります」
これらの声は、大学時代に私のゼミで学んだ若い教員たちから受けた相談の一部です。今、「働き方改革」の推進によって気力を失いつつある教員が、身近にたくさんいると感じています。
以前は、教員は授業の準備に時間をかけていろいろな教材を作ったものでした。部活動をとことんやりまくって、子供や保護者に応援してもらっていた教員もいました。
しかし、今は横並び主義で、時間と行動を制限され、どの教員も同じであることを求められるわけです。このまま時短重視で「働き方改革」を進めていくと、このような教員たちと日々接している子供たちはおそらく「学校には個性的な先生は少ない」と感じるのではないでしょうか。
また、頑張る教員に対して、「あなただけ目立つと、保護者から苦情が来るので、他の先生に合わせるように」などと言う校長もいると聞きます。私が管理職をしていた頃よりも、管理職の個性も薄くなってきたように思えます。
子供にとっては「あの先生、面白いよな」と印象に残る教員が減り、平均的な、まぁまぁの教員ばかりになってしまう気がします。そうすると教師という仕事の魅力も薄まっていきますから、「あんな先生になりたい」と思うような、教員に憧れる子供は減っていくのではないでしょうか。
今の「働き方改革」の何が問題なのか
今の「働き改革」の何が問題なのかを考えるために、原点に戻ってみましょう。そもそも「働き方改革」の趣旨は、教員が働き過ぎて疲弊し、よい教育ができなくなるといけないから、無駄な業務はやめて負担を軽減し、一番大事な部分に力を注げるようにしていきましょうということです。教員が元気で子供たちによい教育をして、よい学校をつくるために「働き方改革」を行うのです。
しかし、現状ではそれがどこかへ行ってしまって、多くの学校では時短至上主義に走っています。時短は、結果が数字で出ますから、教育委員会としては目標に設定しやすいのだと思いますが、それは本質ではありません。
皆さんの学校では「働き方改革」を進めたことで、教員が働きやすくなりましたか。教員と子供の関係はよくなりましたか。教員と保護者の関係はよくなりましたか。もしも答えがNOだとしたら、よい教育ができていないということですから、今行っている取組に意味はないということです。

