小学校の学びの未来をつくる「自由進度学習」への挑戦~授業者の役割と課題~

昭和の時代から提唱されてきた加藤幸次(ゆきつぐ)氏の「個別化教育」が、コロナ禍を契機に新たな注目を集めています。特に、GIGAスクール構想の教育現場への導入により、かつては理想論とされていた「自由進度学習」が現実のものとなりつつあります。未来の教育における可能性を探り、「自由進度学習」という新たな学びのカタチについて考えていきましょう!
【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~
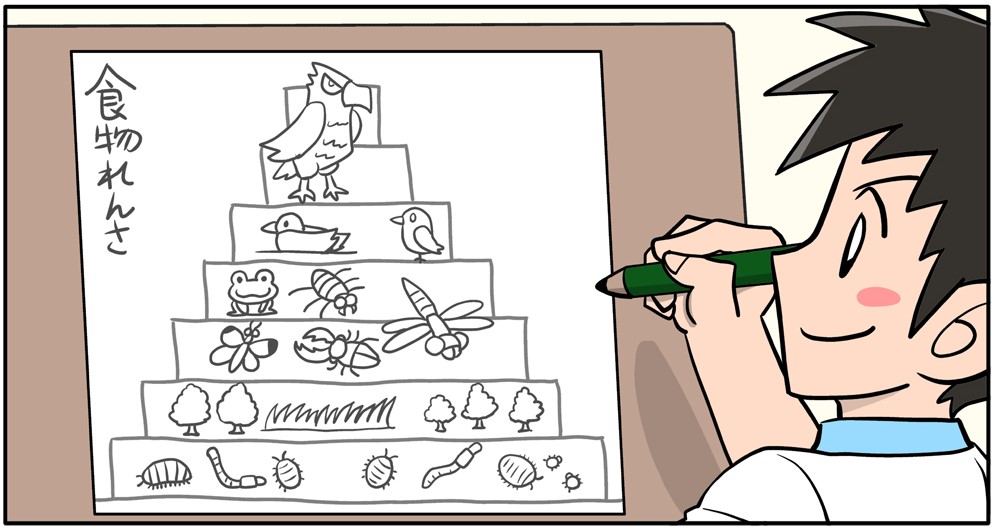
目次
1 日本の伝統だった「個別化教育」
「手習い」という言葉があります。指導者がそれぞれの教え子の状況に即した学びを行うもので、寺子屋、藩校、私塾など、明治時代に一斉教育が導入される以前の日本では、学び手一人一人の実際に合わせた教育が行われてきました。
指導者は学び手の志や興味、能力に基づいて個別最適な指導を行います。例えば、松下村塾では、一斉授業、自学自習、教え合い(交流)、まとめや発表といった、多様な学習形態を複合的に用いていました。このように、実は個別最適な学びは日本のお家芸であったと言えるでしょう。司馬遼太郎氏の著作「風塵抄」によると、江戸時代末期の日本人の識字率は、実に7割にも達していたと言われており、同時代世界中のどこを探しても、これほどの教育成果を誇る国はありませんでした。
明治時代になり、近代的な学校制度が制定されると、我が国の教育方法は一斉教育に転じます。
そして時代は流れ、昭和末期になって、加藤幸次氏によって「個別化教育」の考え方が提唱されました。画一的な一斉授業ではなく、一人一人の児童の個性や能力に応じた教育が真の教育である、ということです。
愛知県東浦町立緒川小学校を中心に数校がモデルとなり、「単元内自由進度学習」が全国に紹介されました。この実践は現代の「自由進度学習」の基礎を築いたと言えます。
2 新型コロナウイルスが教育現場に与えた影響と変化
新型コロナウイルスの感染拡大は、教育現場に大きな変化をもたらしました。学校にとっては暗黒の時期とも言える状況でしたが、混乱の中でオンライン授業が普及し、時間や場所に縛られない学習の可能性が見出されました。この過程で「自由進度学習」という概念の具体性が高まってきました。
また、児童一人ひとりの学習状況を把握し、個別指導を行うためのICTツールの開発も進んでいます。 文部科学省のGIGAスクール構想は、全ての小中学校に高速なインターネット環境と1人1台の端末を整備することを目指しました。この構想は、「自由進度学習」の実現に不可欠なインフラ整備を推進し、教育のデジタル化が急速に進みました。教科書にもQRコードが掲載され、「自由進度学習」の万全な基盤が整ったと言えます。
「自由進度学習」は、自分のペースで、自分の判断と責任のもとに、自分の好きなことから学べるため、学習がより楽しくなり、自発的な学びへの意欲が育まれます。これはまるでゲームの世界で、自分のレベルに合わせて自由に冒険できるような体験です。仲間との協力や課題を克服する感覚も伴います。 このスタイルでは、失敗を恐れず挑戦することが奨励され、新しい知識やスキルを獲得することで自己成長を実感できます。興味を追求することで、学習は単なる義務から解放され、心から楽しむことができるのです。
「自由進度学習」は仲間との交流も促進します。同じ目標をもつ仲間と情報や経験を共有し、お互いに刺激し合うことで、より深い理解が得られます。このようなコミュニティは孤独感を和らげ、共に成長する喜びを感じさせてくれます。実際、私が担当した学級では、児童が机を寄せ合ったり、図書室に行って調べ物をしたりしていました。1人で集中したい児童もいましたが、それぞれのスタイルで学びを楽しんでいました。
このような環境は、学びの楽しさを実感させるだけでなく、主体的な姿勢を育む重要な要素となります。児童たちは互いに教え合ったり助け合ったりすることで知識が深まり、人間関係も豊かになります。このような環境では、学びは単なる知識獲得にとどまらず、社会性やコミュニケーション能力の向上にも寄与します。

