教師にとっての守・破・離とは? 【伸びる教師 伸びない教師 第43回】
- 連載
- 伸びる教師 伸びない教師

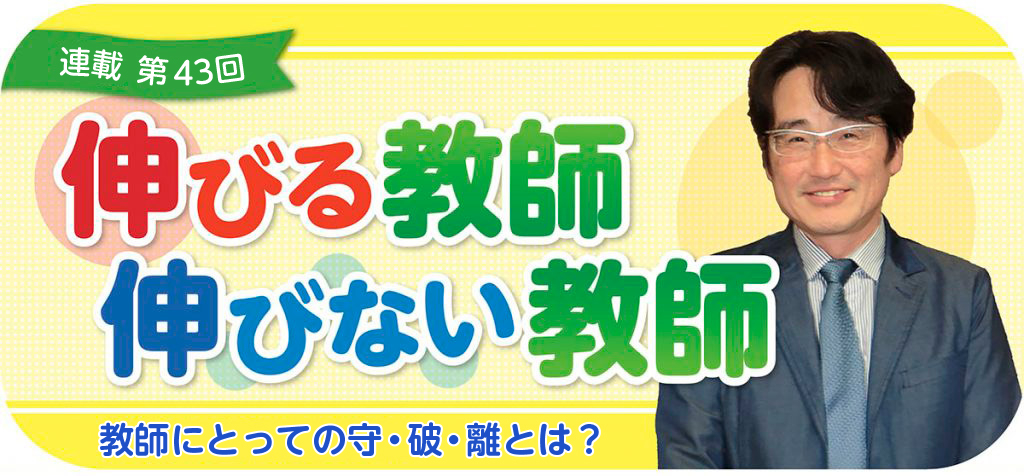
豊富な経験によって培った視点で捉えた、伸びる教師と伸びない教師の違いを具体的な場面を通してお届けする人気連載。今回のテーマは、「教師にとっての守・破・離とは?」です。教師の授業づくりは守・破・離をたどるようです。授業を考えるのは大変だけれど、「先生、楽しかった」「今日みたいのまたやってね」と子供たちに言われると、「また次も」と授業を考え続けるというお話です。
執筆
平塚昭仁(ひらつか・あきひと)
栃木県公立小学校校長。
2008年に体育科教科担任として宇都宮大学教育学部附属小学校に赴任。体育方法研究会会長。運動が苦手な子も体育が好きになる授業づくりに取り組む。2018年度から2年間、同校副校長を務める。2020年度から現職。主著『新任教師のしごと 体育科授業の基礎基本』(小学館)。
目次
茶道から教わった守・破・離
先日、ある会社のHPで久々に「守・破・離」という言葉を目にしました。
「守」 基本や型を身に付ける基本的な段階
「破」 基本や型を破り改善・改良できる応用的な段階
「離」 基本や型を離れ自分の独自性・独創性を見いだす発展的な段階
私が初めてこの言葉を知ったのは、20代の頃でした。子供たちが茶道を体験する授業をしたときのことです。講師の茶道の先生へ挨拶をするとき、子供たちを座らせたままで礼をさせました。
授業終了後、講師の先生が私に次のようなことをおっしゃいました。
「茶道は礼節を重んじるものです。たとえ子供とはいえ、これから教えてもらう人に対して座ったまま礼をするのはそれに反します」
きっと若い私のことを思って教えてくださったのだと思います。
続けて、その背景にある修行の中での師弟関係、茶道や武道、芸術の分野で修業における過程を表す「守・破・離」についても教えていただきました。

自分の授業力は守・破・離をたどる
今、改めて「守・破・離」の言葉の意味を考えると、自分の授業力はまさにこのような段階をたどってきたと感じています。
私の「守」の段階は、教師になって5年目くらいまでだったと思います。初任者のときは、とにかく次の日の授業に追われていたという記憶があります。教師用指導書に書かれている通りに授業を流そうと毎日必死でした。指導技術も未熟で、自分自身でも授業がおもしろくないということを自覚していました。授業はうまくありませんでしたが、その分、若さとやる気はあったのでなんとか毎日過ごすことができました。
その後、何年か経つと教師用指導書に書かれた授業案が「自分の学級には合わないかも」「この発問では子供に伝わらないな」と感じ始めるようになりました。そのため、他に違うやり方はないか、毎月多くの教育書や教育雑誌を買って情報を集めました。
著名な先生が本に書かれている授業を同じようにやってみるのですが、著名な先生の学級の子供たちと自分の学級の子供たちの反応があまりにも違いすぎて、何度も打ちひしがれていた記憶があります。うまくいかない授業がほとんどでしたが、時々子供たちの反応がよかった授業もありました。
「こういう授業を増やしていきたい!」
数少ない手ごたえを支えに教材研究に励んでいました。

