各教科には異なる部分がある一方で、共通部分もある 【授業づくり&学級づくり「若いころに学んだこと・得たこと」第36回】
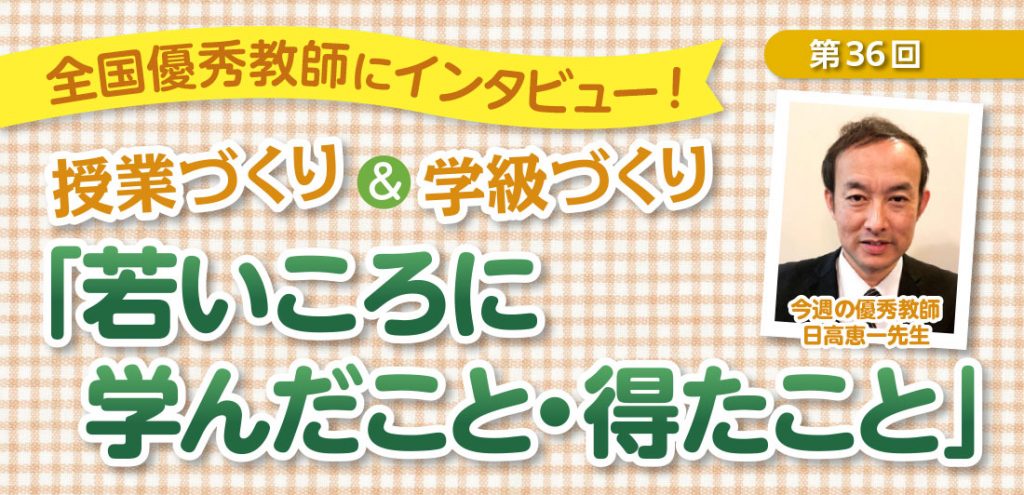
前回は、宮崎県のスーパーティーチャーである日高恵一先生(小学校·国語科)が教師を志した経緯や、講師として教職の道に入ったごく初期までの話を紹介しました。今回は、現場での苦労や経験を経て、次第に国語の研究に力を入れていった経緯を中心に紹介していきます。

目次
ちょっとしたほめ方のバリエーションも身に付ける
本採用になった初年度は5年生の担任になりましたが、学級づくりの面で言うと、女子児童との関係づくりに少し苦労しました。端的に言えば、高学年の女子との距離感がむずかしかったという感じです。多分お兄ちゃんでもない、おじさんでもないという微妙な年齢ということもあったのではないかと思いますし、私自身の指導が一貫していなかったこともあったのではないかと思います。前回もお話しした通り「学級をちゃんとしなきゃいけない」と思いすぎるあまり、少し厳しくなったりする一方で、「子供との関係づくりを大事にしなきゃ」と思って甘くなったり、と一貫していなかったのでしょう。また、つい授業の中で「明日までに調べておくよ」などと言っておきながら、忙しさにかまけて調べ忘れていたりとか、「来週は席替えをしよう」と言って、忘れているようなこともあったりして、それで信用を失っていたのではないかと思います。
男子は高学年と言っても、まだまだ子供の面が強く、一緒にドッジボールとかサッカーをして遊んでいれば、何となく信頼関係ができます。しかし、ひと足先に思春期に入っていく女子は、男子よりも早く精神的にも大人になるため、教員のちょっとした矛盾も感じ取って覚えており、どこかギクシャクしてしまうのでしょう。それを感じた私が良いところを見付けてほめようとしても、思春期に入った女子の中にはみんなの前でほめられることを恥ずかしがる子がいて、それでかえってうまくいかなくなることもありました。
ただ、そうした子供との距離感のとり方は先輩からも学びましたし、経験を積むことで分かっていくところもあります。例えば、ある子供をみんなの前でほめるのではなく、休み時間にその子の友達に、「○○さんって、がんばっているよね」と間接的にほめることで本人に伝わるようにするなど、ちょっとしたほめ方のバリエーションも身に付けていきました。あるいは思ったことを伝えるにも、ちょっと言い方を変えて言ってみるなど、直球だけでなく変化球も覚えるようになっていったのです。もちろん、先の調べものや席替えなど、一度口に出した約束は必ず守るということも、この頃の失敗を通して実感し、その後は必ず守るようにしてきています。
授業づくりの面では、初任校で2年目に道徳の県大会が行われる予定になっていたため、その間は道徳の授業に力を入れてやっていました。複数行う公開授業の中の一つにすぎませんが、私もその大会で授業公開を行うように言われていましたから、学習指導要領を読み、先輩方の授業を見て、教えていただきながら授業づくりをしていったのを覚えています。ワークシートへのコメントの書き方についても、細かく教えていただきました。前回も、講師時代に周囲の先生に積極的に聞いて学んだことについてお話ししましたが、このときも先輩方に積極的に聞いて学んでいきました。

そして、その大会が終わった3年目に、学校内の教科部会で国語部会に配属されることになったのです。宮崎県では、各学校の教科部会の教科主任が地区ごとに集まって自治体の教科部会を形成しています。他の自治体では、常時定例会をもつ会もあるようですが、私がいる地域の国語部会は年に4回ほどの会合をもち、年1回の授業研究会の計画·実施を行ったり、地区で年1回作成する子供たちの文集の選考を行ったりするのが主な仕事となっています。そこで与えられた仕事には、力を入れてがんばっていました。
その他、宮崎県では初任者が研究論文に取り組むことが決まっており、初任のときは係活動について書いたのですが、その後も独自に国語で論文を書き続けていました。例えば、「読解力を高めるための指導のあり方」のようなテーマで、自分なりに実践研究をして論文にまとめていたのです。また指導主事訪問のときには、国語の授業を公開していました。

