ゲストティーチャーを活用するコツとは?「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」きっとおもしろい発見がある! #8

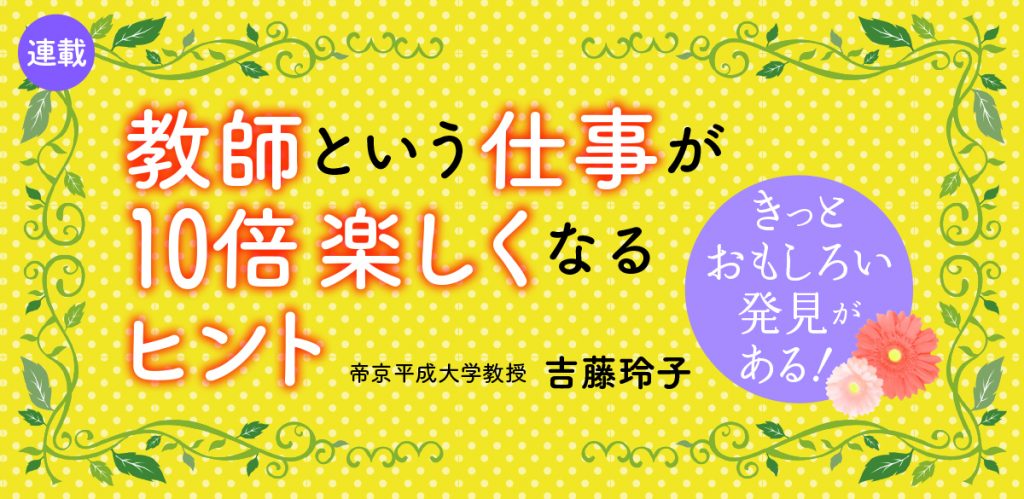
教師という仕事が10倍楽しくなるヒントの8回目のテーマは、「ゲストティーチャーを活用するコツとは?」です。ゲストティーチャーをどのようにして見付けるのか、どのように関わるのか、子供たちのためにどのようにするのがよいのかというお話です。そこには、教師だからこそ関わることができるすてきな出会いがあります。

執筆/吉藤玲子(よしふじれいこ)
帝京平成大学教授。1961年、東京都生まれ。日本女子大学卒業後、小学校教員・校長としての経歴を含め、38年間、東京都の教育活動に携わる。専門は社会科教育。学級経営の傍ら、文部科学省「中央教育審議会教育課程部社会科」審議員等様々な委員を兼務。校長になってからは、女性初の全国小学校社会科研究協議会会長、東京都小学校社会科研究会会長職を担う。2022年から現職。現在、小学校の教員を目指す学生を教えている。学校経営、社会科に関わる文献等著書多数。
目次
教師だからこそ出会える人間関係
パソコンを開いてインターネットにアクセスすると、毎回必ずと言っていいほど学校関係、教育関係の見出しを見る日々です。教員の超過勤務や不祥事、部活動の問題などが主なニュースですが、そのようなニュースが教員を志そうと思う学生や社会人に与える影響は大きいです。私は、声を大にしてそんなに困難な仕事ではないと伝えたい気持ちでいっぱいです。もちろん大変な仕事ではありますが、それ以上に喜びも経験できる仕事です。実際に教育実習に行った学生からも、ネット情報と違い「定時に先生たちが帰っているので驚いた」とか、「職員室はとてもよい雰囲気だった」「子供たちと関われて思わぬ発見があり、楽しかった」などポジティブな感想が寄せられています。メディアの放送が負のニュースばかりなので、残念なのですが、読者の皆さんにはぜひ教員の楽しさを分かってほしいと思います。
教員に対してのイメージの中に、仕事がエンドレスで終わらない忙しさということ、さらに、教育関係の仕事ばかりで視野が狭くなり、いろいろな人と関われなくて狭い人間関係になってしまうのではないかというような声をよく聞きます。それは絶対にありません。今回は、自分の経験の中で先生になったからこそ会うことができた人間関係に触れたいと思います。教師になると「教育活動」という共通ワードで多種多様な人に出会うチャンスがあります。
ゲストティーチャーの活用
授業を進める中で、自分だけでなくその道の専門の方々の力を借りて、より授業を楽しくすることができます。そうは言っても、(どうやって探したらよいの?)と思う先生もいるでしょう。
まず学校に出入りしている人から探しましょう。学校に来ている保護者やPTAの中にも、その道のプロはたくさんいます。地域の方から探してみることも手です。例えば、地域のラーメン屋さんの店長が祭りの睦(むつみ)の会に入っていて、生活科で「お祭りを楽しもう」という授業に来てくれて、神輿の担ぎ方や祭りに関わる人の思いを子供たちにたくさん話してくれました。
同じく生活科の「できるようなったよ」という単元で「昔遊び」の体験をしたときに、地域のおじいさん、おばあさんたちが来校してくれ、子供たちにこまやけん玉などを教えてくれました。その後も子供たちは仲良くなったおじいさん、おばあさんと道端でよく挨拶を交わしていました。
IT関係の仕事のお父さんがプログラミングの授業などを手伝ってくれたこともあります。テレビ局に勤めているお父さんがテレビ局の取材の仕事について話しに来てくれました。このように、ちょっと見まわしてみると、先生として、子供たちに経験談を話してくれる人たちが保護者や地域の中にはたくさんいらっしゃると思います。ある学校では、6年生のキャリア教育の一環で体育館に地域の多様な職業の方たちに集まってもらい、子供たちがそれぞれのブースに行って話を聞き、将来の仕事を考えるという学習をしていました。私もそこに参加させてもらったのですが、医者、看護師、法律関係者、警察官、消防団員、消防士、獣医、製品開発に関わる工場の人、パン屋さん、スポーツ選手、教員、大学教授など、多くの地域の方が集まり子供たちと交流する活動がありました。まさに地域は人材の宝庫です。PTA会長などから情報を集めて、ゲストティーチャーを発掘しましょう。
役所や図書館などで行っているプログラムの利用もおすすめです。市区の福祉政策や街づくり事業など、相談に応じて役所の人も来校して話をしてくれる場合が多いです。図書館もいろいろなイベントを開催していることがあるのでそことつながり、司書の方に来校してもらうのもよいと思います。最近は、昔ながらの紙芝居を自転車に積んで学校まで来て話してくれるおじいさんもいるそうです。

地域の活動や文部科学省、企業の情報にアンテナを
地域などで公的に行っている啓蒙活動を利用するのも1つです。例えば、都心の学校に勤務していると、農業や漁業などの第一次産業との関わりが難しいです。各地域のJAのホームページを開けば、いろいろな出前授業が載っています。環境活動であったり、食育であったり、バケツ稲の栽培であったりと、実際に子供たちが体験して学ぶことのできる授業があり、専門の職員が学校まで来て教えてくれます。
漁業に関しては、東京都では八丈島の女性部が八丈島の魚や漁業についての話をしに学校へ来てくれます。初めてトビウオを見た子供たちは、魚に羽があると大喜びでした。
最近では、文部科学省が推進している起業家教育がおもしろいです。日本は外国に比べて、起業家の割合が少ない、自分で企業を起こしたいと思う若手を育てようということで、旅行業務や商品開発の仕事など企業の取組を知ることができます。いろいろな自治体で行っていますので調べてみましょう。
またそれぞれの自治体が交流している姉妹都市とのつながりも楽しい授業につながります。姉妹都市の人がその地域の特産物であるこけしの絵付けを教えに来てくれたことがありました。こけしは、描く人に顔が似るそうです。子供たちは本当に真剣にこの絵付け作業に取り組んでいました。子供たちの作品の中から何点かは、その地域のこけし祭りの際に学校の体育館に展示されました。この活動が縁で、私もその自治体を訪問させてもらうことがありました。全国いろんな地域で姉妹都市交流は盛んです。ぜひ調べてみてください。
民間の企業も自分たちの仕事を知ってもらいたいと出前授業を工夫して実施しています。興味のある企業があれば、ホームページにアクセスしてみましょう。食品や自動車づくりなどいろいろな企業が学校に職員を派遣してくれます。野球やサッカーなど、スポーツ選手を派遣してくれる団体もあります。話だけでなく、その後、実際に選手とキャッチボールやドリブルができれば、子供たちは大喜びです。学校外から先生を探してくるのは教員の腕です。こまめに興味のある出前授業を実施している企業のホームページをチェックし、情報を得ることです。
ある自動車会社の関連企業で、パラリンピックの車いすマラソンの車いすを作成している会社の人に来てもらったことがあります。車いすマラソンの車いすは各選手の体形に合わせてつくられており、何よりも驚いたのはとても軽いのです。片手で持ち上げられます。そんなことはこの企業の授業を受けるまでは知りませんでした。狭い、身体にフィットした車いすマラソンの車いすに乗って、子供たちは改めてパラリンピックについて考えることができました。実際に体験してみて分かることがたくさんあります。ぜひ、企業が行っている無料の出前授業を実施することをおすすめします。

