ICT活用の際、どんな力を育むのかという本質を見失ってはいけない 【授業づくり&学級づくり「若いころに学んだこと・得たこと」第31回】
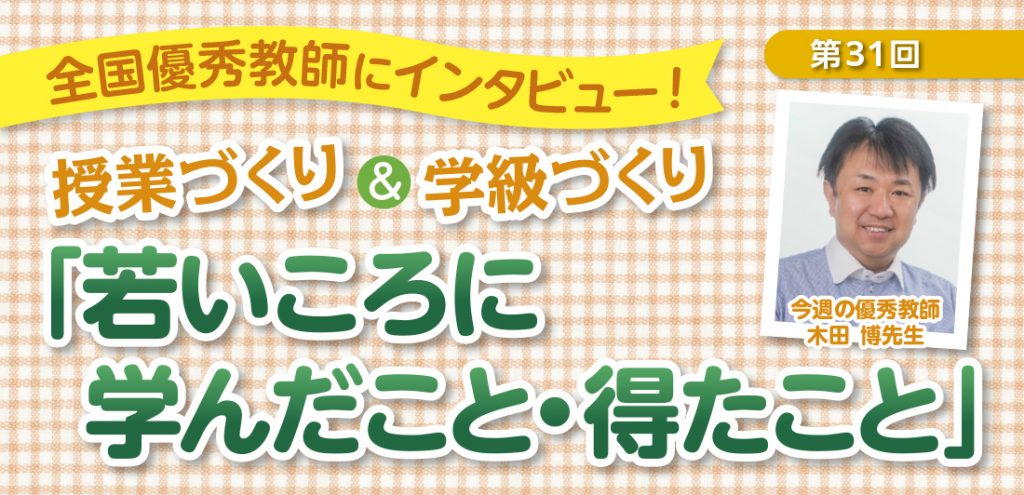
前回、鹿児島市立学校ICT推進センターの木田博所長が、授業改善に加え、 ICT活用に取り組んでいく過程を紹介しました。今回は、ICTを多様に活用した後、行政に入り、若手を育てる立場から気付いたことや気になったことなどを紹介していきます。
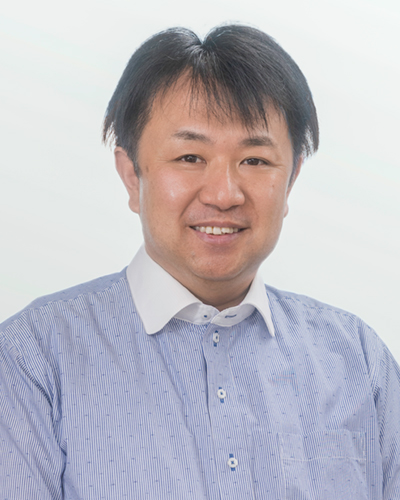
目次
ICT活用で、本当に授業のコストパフォーマンスが上がる
前回、スクール・ニューディール政策を契機に、ICTの活用に特に力を入れるようになったことをお話ししましたが、教育でICT活用をリードしてこられた堀田龍也先生(東北大学大学院教授、東京学芸大学大学院教授、国立教育政策研究所上席フェローなど)にお世話になるようになったのは、そのときです。ちょうど在籍校が電子黒板利活用の研究指定校だったこともあり、ご訪問いただき、ご指導いただいたのですが、その頃から現在のGIGAスクール構想のイメージをもたれていて、感銘を受けたのを覚えています。その後、堀田先生の著書を拝読したり、講演を聴きに行ったりして、勉強をさせていただきましたし、今でもたいへんお世話になっております。
後に鹿児島市教育委員会の指導主事になりましたが、現場の先生方の授業を見ていて感じたのは、授業のコストパフォーマンスがあまり良くないのではないかということです。指導主事として先生方の授業を見た後、話をしてみると、みなさん、「やりたいことがいっぱいあるのに、時間が足りない」「今日はここまでやりたかったけど、時間がなくてできなかった」と言うのです。しかし考えてみると、その授業の中でプリントを配ったり、それをまた回収したりとか、板書とそれを写すことに時間を取ったりとか、あまり有用ではない時間を使っていると思います。「始業のチャイムが鳴ったら、授業に遅れないように始めるよ」と子供たちに言う割には、先生の授業の中に時間を生み出す余地があるのです。
私は先の研究校で、ICTを多様に活用したわけですが、実際に活用すると、本当に授業のコストパフォーマンスが上がるのです。例えば、授業で子供たちがホワイトボードに自分の考えを書いて、黒板に貼って、比較して意見を言うという授業があるとします。この過程にある、ホワイトボードに書く、貼る、見にくいボードの文字を読んで比較する…といった時間は、情報端末を使うことでほぼ必要なく、送信後、即座に並べて比較することができるのです。実際に、ホワイトボード利用と情報端末利用とを比較した場合、最も重要で多様な考えを比較し、考え、意見を出し合うという部分に10分以上、多くの時間を取ることができます。
例えば、先生が授業のめあてを書いて、それを子供たちが写すというような作業時間も、小学校45分の授業時間、中学校50分の授業時間の中では、本当に毎回必要だろうかと思うのです。もちろん子供たちがめあてをつかむことは大切ですが、すでに子供たちとめあてが共有できている状況ならば、先生が時間をかけて板書したり、それを写したりすることに時間を使うのではなく、子供たちが問題意識を共有するために意見を出し合って、めあてや課題を設定して子供たち一人一人がつかむことに時間を使い、それを情報端末で瞬時に共有したりしてもよいのではないかと思います。
授業の勘所が明確になっている先生が使ってこそ、ICTの効果が発揮できる
後に鹿児島市教委から鹿児島県教育委員会に異動してICT担当となり、その後、鹿児島市教委で現職となって、ずっとICTを活用した教育の推進に携わってきました。その間、感じてきたのは、情報教育の分野は、以前はそれほど重視されてきた分野ではなく、「あってもよいけど、なくても困らないよね」というイメージでした。それが近年ではだいぶ印象が変わっており、なくてはならない分野になっているというのが現在の実感です。これまで「ICTなんか使わなくても、いい授業はできる」と言っていた先生方が、「使わないといけないな。特に子供たちに使わせないと」と言ってくれるようになりましたし、実際に使ってみると、「これは有効だ」と言ってくれます。それも、授業力が高い先生のほうがそう言ってくれることが多いのです。
ICTを使ったからといって良い授業ができるわけではありません。ICTを使っても、授業力が十分でないと授業の質はなかなか高まりません。それは授業の肝や勘所が分からないからです。それに対して、授業の上手な先生が使うと格段におもしろい授業になるのです。先に授業のコスパの話をしましたが、「以前は対話するまでの準備に時間がかかって、対話し、深める時間がわずかだったけど、ICTを活用して必要な情報を即時共有すれば、予想外の気付きや疑問も生まれた」というようなことが起こるのです。それは、子供たちの考えを集約したり、その集約の仕方で異論や共通点が明確になったりすることが、短時間で可能であり、真剣に対話し考えさせたいことに時間を取れるからです。私は、指導主事として教員研修を行い、先生方がそのような体験を通して授業の質が少しずつ変化していくのを感じました。

これまでも教育の世界には様々な流行があって、その際、「この指導方法がはやっているから、これで授業をやる」と言う人も少なからずいました。しかし、まず方法ありきでは決して良い授業にはなりません。子供たちにどんな力を付けたいという目標があり、だからどんなことをやるのか、そのためにはどんなツールや方法が適切なのかを考えて選択してこそ、最適な学習活動が形づくられるのです。そのプロセスがないまま、どこかで見た方法を形だけ真似ても良い授業にはなりません。それはICTも同様で、使えば必ず子供たちが深く考えられたり、分かるようになったりするわけではありません。授業の目指すところや勘所が明確になっている先生が使ってこそ、何倍もの効果が発揮できるのですが、刃物と同様でへたに使うと怪我をしてしまうでしょう。怪我というと大げさに聞こえるかもしれませんが、準備や実践に時間をかけた割には何も残らず、コスパの悪い授業になりかねないということです。
だからと言って、経験不足の人は使わないほうがいいと言っているのではありません。私は、若い先生方には「教育原理をしっかり学ぼう」と伝えたいのです。今、現場を見ていると、子供たちが分かるようになるためにどう教え込むかということに汲々としている若い先生が少なくないように見えます。前々回お話しした有田和正先生が、「授業は生き物なんだ。やっているうちに流れが変わることもある。その流れを見極めて、それが前に進むものであれば、どの流れに乗ってもいい」という趣旨のことを言っておられました。それとは逆に、自分が事前に描いた流れのほうに無理やりもっていこうとすると、流れがせき止められたり、氾濫を起こしたりするのだと思います。ですから、ICTを活用するに当たっても、この時間で子供たちにどういう力を付けたいのか、そのために何をやるのか、それをやるためにICTをどのように使えば授業の濃度やコスパが良くなるのかを考えてほしいのです。

