必ず1日に最低1回は直接声をかけ、すべての子供と関わる 【授業づくり&学級づくり「若いころに学んだこと・得たこと」第28回】

今回からは、文部科学省の学校DX戦略ICT活用教育アドバイザーを務める、鹿児島市立学校ICT推進センターの木田博所長に、どのようにして教師の道を選び、学級づくりや授業づくりの専門性を高めていったのか、またどんなきっかけでICTの活用を始め、その専門性を高めていったのか、についてお話を聞いていきます。
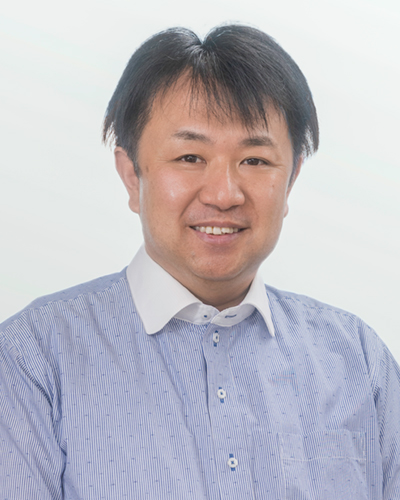
目次
教育実習時に、教えることの責任の重さとおもしろさを感じた
私が大学進学をどうするか考えていたのは、ちょうどバブル景気に差しかかる頃で、私も当初は経済学部か経営学部志望でした。社会全体の景気が良く、教員も含め公務員になる人に対し、「なんで公務員になるの?」と言われるような時代だったのです。しかし、残念ながら第1志望大学の当該学部には合格せず、地元大学の教育学部に進学することにしました。ただ、教育学部を出たら教員にならなければならないというわけではありませんから、卒業時にはトレーダーとか、景気の良さを象徴するような仕事につこうと考えていたのです。
ところが、大学入学後にたまたま勧誘されて入ったのが、キャンプ・カウンセラーというサークルで、子供たちを野山に連れていってキャンプをさせていたのです。もちろん日々、キャンプだけをしているわけではなく、レクリエーションをさせたり、グルーピングをさせたりもするわけですが、その経験を通して、子供たちが目の前で変わっていく(成長していく)ことの尊さ、おもしろさを感じるようになっていきました。
ちなみに、私の大学時代の専門は教育学でした。3年生で専門学科を選ぶときに、希望の教科は他にあったのですが、あまり熱心な学生でもなかったため、希望教科には倍率が高くて進めなかったのです。もちろん、当初は望んで進んだわけではありませんが、そのときにジョン・デューイやウィリアム・キルパトリックなどについて学んだことが、後々教員になって問題解決学習とかプロジェクト学習に取り組んでいく上で、非常に役に立ちました。
その後、教育実習に行き、教えることの責任の重さと同時におもしろさを感じたことが、教員になる大きな契機になったと思います。どうやれば、子供たちが授業に興味をもって入ってきてくれるか、どうやれば授業を通して「やった、できるようになった」とか、「こんな考えができるようになった」という喜びを感じてくれるようになるか。それを考え、工夫し、実際に子供たちがそう感じる場面に関われる仕事って、とても尊いし、おもしろいと思ったのです。
ですから、4年生のときにはもう他の仕事につこうとは考えず、教員採用試験を受けて教員になりました。高校の同級生のほとんどが民間企業に入り、給与も良かったですから、「何で教員なんかになったの?」という感じもあったのですが、私は少しも選択を間違えたとは思いませんでした。それくらい、教員という仕事はおもしろいと思っていたのです。

