子供とつくる楽しいICTの授業とは?「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」きっとおもしろい発見がある! #7

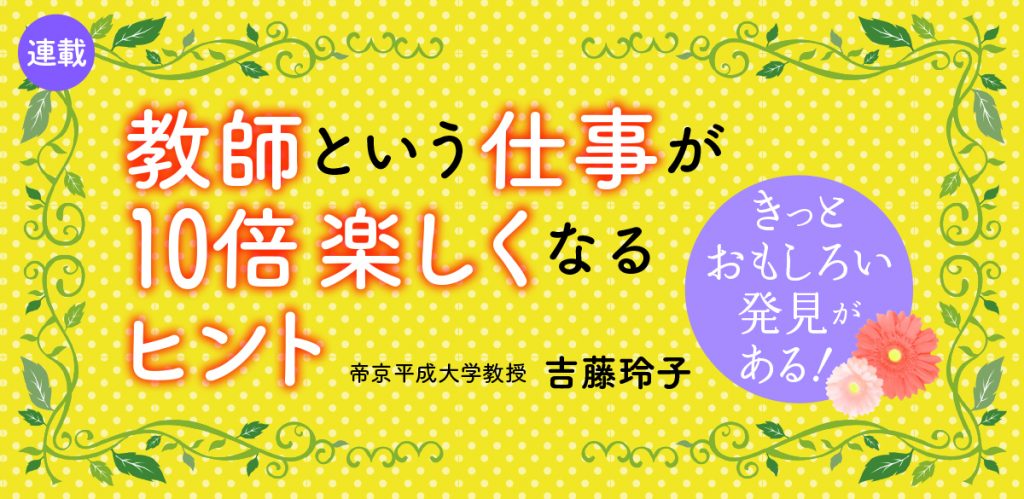
教師という仕事が10倍楽しくなるヒントの7回目のテーマは、「子供とつくる楽しいICTの授業とは?」です。子供たちはICTが大好きです。そのなかでも、子供たちとつくっていくプログラミングの授業の実践とはどのようなものか? 子どもたちとつくるICTの授業のつくり方のコツが分かる話です。

執筆/吉藤玲子(よしふじれいこ)
帝京平成大学教授。1961年、東京都生まれ。日本女子大学卒業後、小学校教員・校長としての経歴を含め、38年間、東京都の教育活動に携わる。専門は社会科教育。学級経営の傍ら、文部科学省「中央教育審議会教育課程部社会科」審議員等様々な委員を兼務。校長になってからは、女性初の全国小学校社会科研究協議会会長、東京都小学校社会科研究会会長職を担う。2022年から現職。現在、小学校の教員を目指す学生を教えている。学校経営、社会科に関わる文献等著書多数。
目次
子供とつくる楽しい授業 ICTの活用「プログラミング」
子供たちとの関係をつくるには、教師の説教でなく授業だということを以前にも伝えました。
授業は教材研究、先生のアイデアもありますが、何よりも子供といっしょにつくっていくという姿勢が大事です。
コロナ禍で全校に1人1台のタブレット型端末が普及しました。私は、タブレット型端末を活用しての様々な学習はおもしろいと思っていますが、ここ数年の情報機器の変化と普及のスピードには驚かされています。いつの間にか子供たちがランドセルにタブレット型端末を入れて通学するのが当たり前になりました。学校からパソコン室がなくなり、校内のあらゆる環境でインターネットを活用した授業ができるようになりました。
このタブレット型端末が配付される前、パソコン活用の普及を考え「プログラミング教育」ということが盛んに言われていました。小学校段階から、生活や社会におけるプログラミングの意義を知り、コンピュータに触れながらプログラミング的思考を身に付けていくことが必要だと言われ、Scratchなどのソフトウェアやロボットなどの教材を活用した研究授業が多く行われました。今でも学習指導要領にはありますし、必要なことですが、まずは目の前の1人1台のタブレット端末をどう有効活用するかが先となり、最近では「プログラミング教育」という言葉をあまり聞かなくなりました。プログラミング教育は、子供の個性を引き出すことができ、操作も簡単で、いろいろと取り入れるとおもしろい授業ができるので、ぜひおすすめしたいです。

ICTを使った授業や活動の難しさ
「プログラミングだ」「ICTだ」と言われ、それを活用したほうがよいことが分かっていても、躊躇したり、悩んだりしている先生も多いと思います。まず、タブレット型端末の使い方を覚え、子供にいろいろ聞かれても分かるように、ハードとソフトの両面の活用方法を勉強しなくてはいけません。スマホ時代の若者なら簡単かもしれませんが、少し年配の方は、戸惑うことも多いでしょう。
次に機器の充電忘れや故障への対応が面倒で大変です。さあ使おうと思ったら、「先生、家で充電し忘れました」という子供もいます。教室に予備が用意できる環境であればよいですが、なかなかそうはいかないと思います。日々使用していれば破損してしまうこともあり、機器の会社に連絡しなくてはいけません。その他、授業の中でもどこでどのように活用したらよいか、インターネットで検索するだけでなく、意見交換をしたり、プレゼンテーションを作成したり、全体で共有したり、有効な活用方法が多すぎるので教師の側の選択と準備が必要です。そして何よりもICTを活用した授業で配慮しなくてはいけないことは、子供の操作能力の個人差が大きいということです。
A児はさっさと作業が終わり、きれいに作品もできあがって余裕でインターネットで検索しているのに、B児は、ようやく1行だけ文章が打てただけなどという事例があります。本来ならこの個人差があっても、各自のペースでタブレット型端末を活用し、学習活動を進めていけばよいのですが、学校現場ではなかなかその余裕がなく、時間の確保が難しいのです。休み時間や放課後の時間を活用するなどのフォローも必要かもしれません。

