提言|授業づくりのポイントはUDL×「個別最適な学び」 【発達障害8.8%をどう受け止めるか #5】
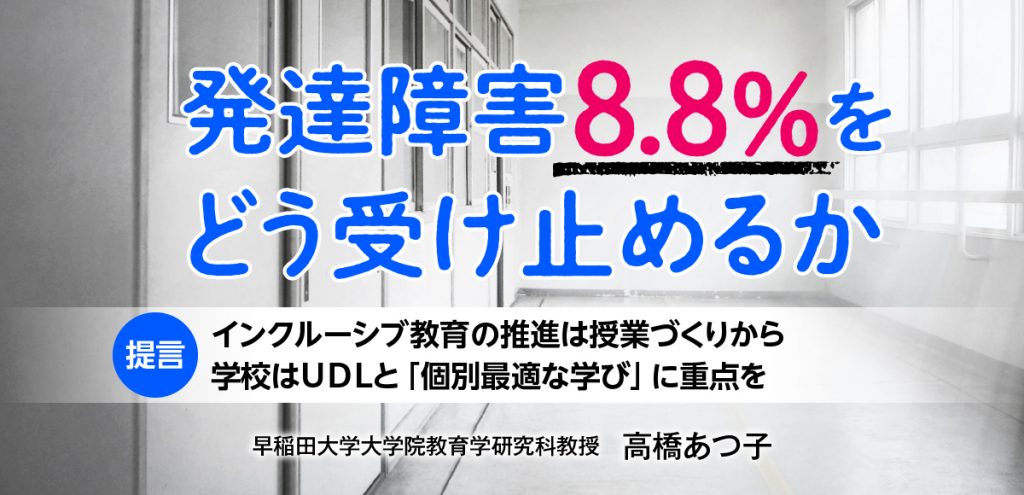
「通常学級の小中学生の8.8%に発達障害の可能性」という調査結果を専門家たちはどう受け止めているのかを知り、学校の未来を考える7回シリーズの第5回目です。この調査結果を受け、学校はどんな授業づくりをする必要があるでしょうか。学びのユニバーサルデザインを推進してきた早稲田大学大学院の高橋あつ子教授に聞きました。

高橋あつ子(たかはし・あつこ)
神奈川県川崎市の公立小学校で重度重複障害児学級、障害児学級、通常の学級の担任を経験し、交流教育に力を入れてきた。その後、指導主事時代に特別支援教育の体制づくりに携わる。教頭を経て、2008年より現職。アセスメントやカウンセリング、授業力の向上を図る科目を担当。現在は、学びのユニバーサルデザインの授業づくりを指導しながら、臨床心理士、特別支援教育士SVなどの資格を活かし、新宿区の巡回相談や各地の教員研修も行い、のぼりと心理教育研究所で臨床も続けている。
■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全7回予定)
●提言|川上康則 学校管理職に気づいて欲しいのは「学校が子どもに合わせる時代」になったこと
●提言|児童精神科医が指摘! 発達障害の子どもと不登校の関係は?
●提言|木村泰子 「困っている子が困らなくなる学校」をつくる
●提言|赤坂真二 今、学校がすべきなのは学級経営のUD化
●提言|授業づくりのポイントはUDL×「個別最適な学び」(本記事)
目次
高校生の2.2%にも注目したい
8.8%という数値は、小中学校の担任が認識している子どもたちの行動について調べたものであり、このデータは、先生たちが「この子は発達障害の可能性がある」と気づけるかどうか、その眼力に依存しています。振り返ってみますと、2000年代には「発達障害の子どもはうちの学校にはいない」と思い込んでいる教師や、「『こういう子がいて困る』『手に負えない』などと言うのは、教師の指導力がないせいだ」と考えるベテラン教師がたくさんいました。昔から発達障害の可能性がある子どもは通常の学級にいたのですが、障害とは認識されず、躾の問題や努力不足と捉えられていたのです。発達障害という概念が知られるようになってから約20年経ち、今は公立小中学校ではいるのが当たり前になり、多くの先生たちが気づけるようになった、ということでしょう。
私が注目しているのは、同じ調査で高校生は2.2%という数値が出たことです。今までは高校生のデータがありませんでした。かつての小中学校のように「いないはずだ」と思われがちでしたし、先生が気づけなかったからです。おそらく正確なデータとはいえないだろうとは思いますが、少なくとも2.2%はいると認められたわけですから、これは画期的なことです。
今、高校でも「発達障害の生徒はいない」という空気が少しずつ変わり始め、発達障害に対する認知度が上がってきているところです。それは、公立高校の入試で合理的配慮が行われるようになったことが大きいと言えます。教師個人の考え方ではなく、法に定められた権利保障としての入試が、基準を引き上げたのです。入試だけでなく、当然、入学後も合理的配慮が求められ、大学受験でも合理的配慮が行われます。このように公立高校は、入試のしくみの変化によって発達障害の生徒に対する認識と対応を変えてきたのです。
その一方で、私立高校の中には、未だ合理的配慮についての認識が十分とは言えない学校も少なくありません。入学試験に合格して入学しても、「本校の校風に合わないのだったら、どうぞ辞めて頂いて構いません」という文化が残っている学校もあります。仮に発達障害の生徒がそのような学校に入学しても、「いないもの」として扱われますから、合理的配慮を提供されず、結果、中退することになったりします。ただ、私立高校も少しずつですが、変わり始めています。障害者差別解消法で、民間業者としての私立学校は当面は「努力義務」とされていた合理的配慮が、同法の改定で義務(東京都は、都の条例で既に義務)となったことも影響し、最近は、私立高校でも合理的配慮の提供についての関心が高まってきているのを感じます。
日本の分離教育について考える
今回の調査結果を受け、学校はどんな授業をする必要があるのかを考えるために、まずは分離教育に対する私の考えを述べておきます。
日本では、これまで障害のある子どもたちは特別支援学校や特別支援学級で個に応じた教育を受けることが勧められてきました。しかし、これは、分離教育という側面も有しています。現在、教壇に立っている先生たちは、特別支援学級設置校を除いて、障害のある児童生徒と学校生活を共にすることもなく育ってきましたので、場を分ける教育に疑問を感じずにいる人も多いのではないでしょうか。校長先生には、この機会に改めて考えてみてもらいたいのです。
私の教員生活のスタートは、重度重複障害者学級の担任でした。当時、就学を猶予されてもおかしくないほどの重度の障害のある子どもに教育を保障するために、川崎市はスクールバスと介助員を配置し、小学校に重度重複障害児学級を設置しました。私は運良く、その学校の1つに着任して担任となったのです。そして、全ての学級と交流活動をしました。
そのときに気づいたのは、子ども集団の力です。例えば、言葉がなく、多動でよく叫び声をあげて教室を飛び出していた自閉症の子どもが、2年生の音楽の授業に参加し、目を見開いて子どもたちの演奏を見て、自らタンバリンに手を伸ばし叩きだしたときには感動しました。私たち教師が教えるよりも、子どもは子どもから感化されていることを知り、子ども集団の力、子ども相互の力は大きいと実感したのです。
一方で、一緒に育つことで周囲も変わります。私が通常の学級を担任していたとき、クラスメイトである自閉症の子どもが、上級生や他の学級の子どもにからかわれる場面に遭遇します。そのことに子どもたちは憤慨し、何とかしたいと言い出しました。そこで、自閉症のその子のことをわかってもらうための説明を考え、他の学級に説明に行ったのですが、こう関わるといいよ、こういうのはからかいだからやめて、という願いが込められていて、幼いのに仲間を守ろうとする彼らの力に驚かされました。
ですから、私は分離教育に突き進む動きには否定的な考えを持っています。
諸外国に目を向けてみますと、教育先進国では障害の有無には関係なく、子どもは一般教育システムの中で一緒に学ぶ、という方向に進んでいます。障害のある子どももない子どもも一緒に学ぶことで、どちらの学力も伸びる、というエビデンスもあります。
しかし、今の日本の学校では、逆のことが起きています。就学時には「通常学級でどれぐらいできるかを試してみたい」といった保護者の期待もあり、発達に課題のみられる子どもも通常の学級に在籍したとします。ところが通常の学級の授業や人間関係づくりが従来のままだと、トラブルが起きたら本人のソーシャルスキルの問題と捉え、通級指導教室を使うことを求められます。それでも状況が変わらなければ、特別支援学級を勧められます。学年が進む中で、悪い言い方をすれば、保護者が子どもの実力を知り、それなりの場を選んでいく、そういうエクスクルージョン、つまり、排除と思えるようなプロセスを踏むことが行われています。
本来は、子どもの能力には関係なく、環境を整え、どの子どもも通常の学級で過ごせるようにしていくのが、学校として行うべきインクルーシブ教育ではないでしょうか。多様な子どもが違いを乗り越えて学び合い、認め合うことで、共生社会は実現します。仮に入学時には特別支援学級から始まったとしても、学年を経るにしたがって、通級指導教室+通常学級、通常学級オンリーへと進んでいく、このプロセスを踏むケースを増やしていく必要があるように思います。
けれども実際は「学年が長じ、学習内容が難しくなり、能力差が大きくなるにつれ、障害のある子も一緒に学ぶのは難しくなる。だから、分離教育の比重が大きくなるのは当たり前」と思っている先生は多いと思います。確かに日本型の一斉授業をやろうとしたら難しいでしょう。
カナダのある学校区では、保護者の運動によって特別支援学校が廃止されました。高校には、7段階程度の能力の生徒が在籍し、課題や進捗状況を個々の生徒が調整して学んでいます。アメリカのある学校区でも、保護者が特別支援学級を希望しても、一緒に学んでも学力を上げられるとして、特別支援学級を廃止しました。特別支援学校に行くレベルの子ども、特別支援学級に行くレベルの子ども、通級指導教室利用の子ども、通常の学級で学力の低い層の子ども、中間層の子ども、高い層の子どもなどが同じ教室で学んでいるのですが、それができるのは、子ども一人一人が目標を設定し、自己評価をして管理しているからです。つまり、「個別最適な学び」が行われているのです。
今後、日本でインクルーシブ教育を推進していくにあたり、学校が取り組むべきなのは、「個別最適な学び」を充実させることであり、そのために先生たちに知ってほしいのは、UDL(学びのユニバーサルデザイン、Universal Design for Learning)です。

