名作『ナイン』(井上ひさし 作)の読書会抄 ー「仏作って魂入れず」の現代教育ー【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第58回】

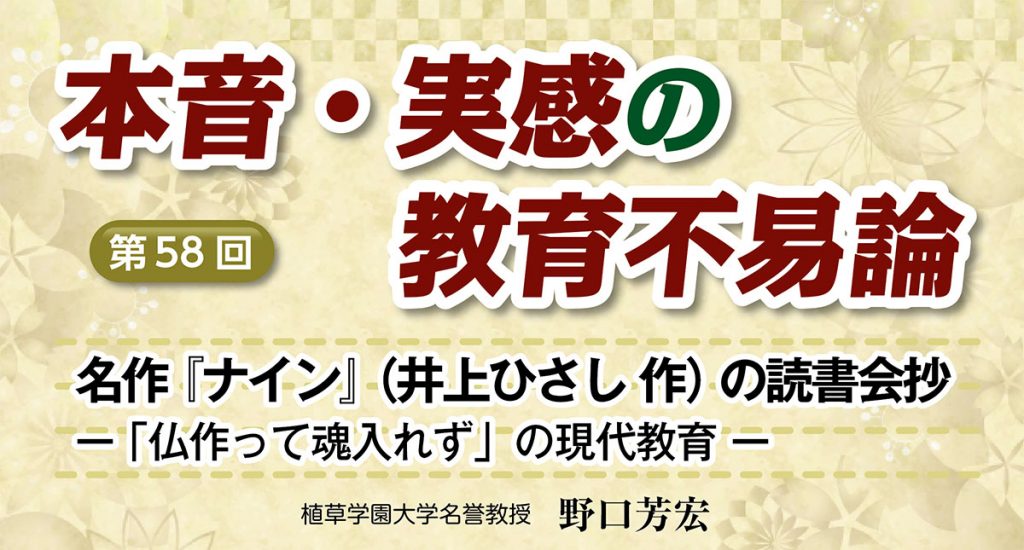
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第58回は、【名作『ナイン』(井上ひさし 作)の読書会抄 ー「仏作って魂入れず」の現代教育ー】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。
目次
1 デジタル版出航への思い
今日は3月3日、雛祭りの日である。さすがに春の気配が濃く、梅は満開、爛漫を経て散り始めている。新年を迎えたと思っていたのに早くも弥生である。私は今年、米寿を迎えた。数え年88歳である。国民学校に入学するまでの幼時は体が弱く、病気ばかりして随分親に心配をかけたようなので、こんな長寿に恵まれるとは思ってもいなかった。大学の同期生も鬼籍に入った者の方が多くなった事実の前に、唯々有難いと感謝の日々である。
本誌、とはもう呼べないのかもしれないが、他の呼称が思いつかないので旧称を用いる。本誌デジタル化の初号が2023年3月から配信されるについて、連載を続けるようにとのお話を戴いた。身に余る光栄である。恐らく、このデジタル社会にあって、今も手書きの連載原稿を書いているのは私の外にはあるまい。だが、やはり文章は紙に手書きでないと思考が進まないのだ。
デジタル化に合わせてどんなことに気をつけたらよいかと編集長にお尋ねしたところ、今まで通りで全く差し支えないとのことで安堵はしたものの、私以外は全ての方がキーボードで原稿を打ちこんでいるのであろう光景を思い浮かべると、何となく我が身が化石めいた姿に映って見えてくる。
だが、大切な誌面の一部を戴くのだから、残り僅かの時間ながら、誠実に本音、実感を吐露して御批判を乞いたい。もうしばらくのお付き合いをお願い申し上げる。

2 名作『ナイン』を仲間と読む
井上ひさし作の『ナイン』という短編が高校の教科書に載っている。井上ひさしという名を初めて知ったのは、『手鎖心中』で直木賞を受賞した時だ。雑誌『オール讀物』で読み、凄い作家が現れたものだと思った。文章の滑らかさに驚いたのだった。
『ナイン』は、東京の四谷駅近くにあった「新道(しんみち)少年野球団」が、新宿区の少年野球大会で準優勝をした折の思い出と、その後社会人になってからのそれぞれの消息が語られる作品である。井上ひさしの文章が実に味わい深い筆致で展開していく佳品、名作である。ナインは9人の小学6年生のチームの絆を表している題名である。
この作品を10人足らずの教員仲間でじっくりと鑑賞する。勉強会というよりは読書会に近い楽しい集いである。北は札幌から南は福岡まで、オンラインで結ぶ授業道場野口塾の例会である。65歳で北海道教育大学を退官した私は、その後は暇になるだろうと考え、私的な勉強会を立ち上げた。その会がずっと続いて23年、回数は370回を超え、オンラインの回数も160回超になった。オンラインを取り入れると同時に、中学校、高校の教材にも積極的に取り組むことにした。オンラインの技術担当者が、中学校と高校の教員である好機を積極的に活かそうという訳である。小学校の校長を退いた仲間が殆どなので、中学校や高校の教材への取り組みは新鮮であり、大いに学び合えて楽しい。『ナイン』もこんな経緯の中から生まれた出合いだ。
小稿は、この教材をどのように授業すべきかという話ではない。この作品に登場する人物相互の言葉の使い方をめぐって教育のあり方を考えたいのだ。『ナイン』の作品の素晴らしさは各自が直々に味わって貰いたい。読後、清々しい感動に心が洗われること請け合いである。多くの文庫本に載っている。

