24時間をデザインする力【妹尾昌俊の「半径3mからの“働き方改革”」第24回(最終回)】
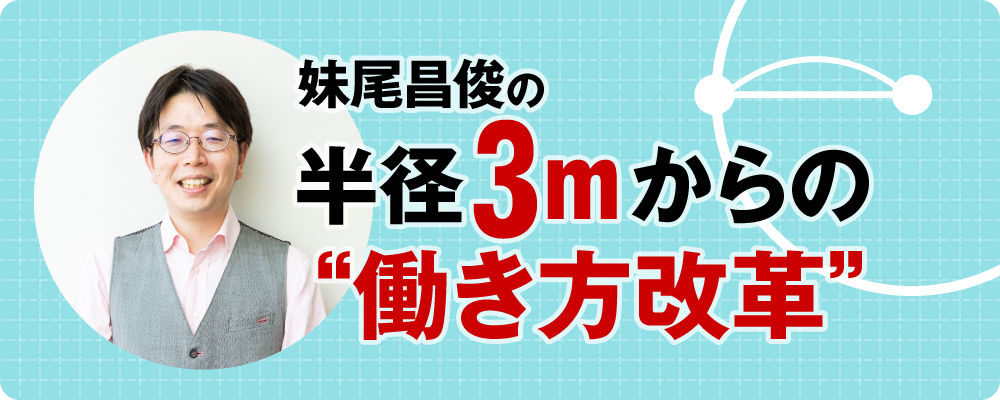
学校の“働き方改革”進んでいますか? 変えなきゃいけないとはわかっていても、なかなか変われないのが学校という組織。だからこそ、教員一人一人のちょっとした意識づけ、習慣づけが大事になります。この連載では、中教審・働き方改革特別部会委員などを務めた妹尾昌俊さんが、「半径3m」の範囲からできる“働き方改革”のポイントを解説します。
執筆/教育研究家・一般社団法人ライフ&ワーク代表理事・妹尾昌俊
目次
半径3mから
「国がもっと予算を付けてくれないと、学校でできることには限界がある」
「学校で既に見直せるものはやっている。絞りきった雑巾をさらに絞れと言うのか」
学校の働き方改革をめぐって、校長や教職員の反応、反発のなかには、上記のようなものも少なくない。読者の皆さんもいかがだろうか。賛同する、共感するところもあるかと思う。
確かに、文部科学省や財務省の役割は大事だ。教職員の増員を含めて、もっと教育にカネをかけないといけないと思う。
それに、文部科学省は学校にスクラップ&ビルドを求めているのに、自身の施策はビルド&ビルドである。学習指導要領がその典型であるし、そのうえ、キャリアパスポートだ、観点別評価だなどと、学校に負担を増やす一方に見える。GIGAスクールで一人一台コンピュータを整備するのはいいが、メンテナンスや更新で学校側、とりわけ情報担当教員の負担が増大している例は多い。
国に対する批判、政策提案は声を大にしていきたいと、私も思う。だが、同時に思うのは、他人のせいや愚痴を言うだけではダメだろう、ということだ。
何より、今日の学校の過酷な状況は、教職員にとっては自分事である。自分と同僚の命、健康を守るためにも、またよりよい教育活動にしていくためにも、教職員に余力を取り戻す必要がある。
この連載も、今回で最終回を迎える。〈半径3mからの「働き方改革」〉というタイトルにしたのは、「学校のごく身近なところでできることは、まだまだ多いのではないか、もっとこんなこともやってみては」という思いからだ。理想の24時間を描くワークや、運動会や部活動はなんのためという問いかけ、採点は聖域か、刃を研ぐなど、かなりいろいろなことを取り上げてきた。 「学校にできることは、たかがしれている」と思う読者(その知人も含めて)は、過去回を参照いただけると、多少考えが変わるかもしれない。あるいは、実践している現場も増えたから、見に行ってほしい。

