「信頼を得る通知表の作成術」保護者を味方にする学級経営術 #4

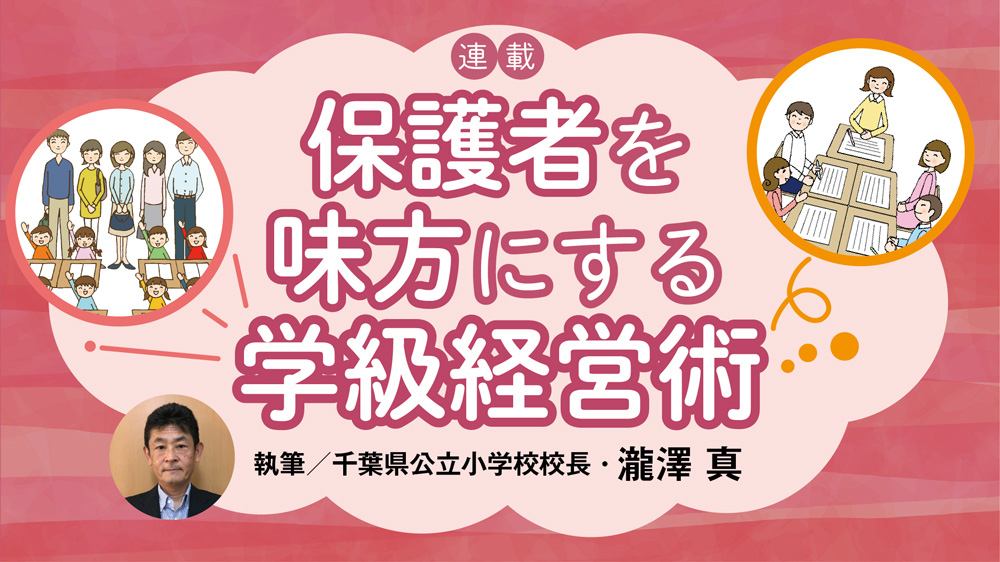
学級担任なら、一度は保護者対応に悩んだ経験があるのではないでしょうか。しかし、保護者が味方になってくれたら、こんなに心強いことはありません。この連載では、保護者が担任と学級を応援したくなるような学級経営について、その月の学校状況に合わせたアイデアを紹介します。第4回は、通知表の作成術を取り上げます。
執筆/千葉県公立小学校校長・瀧澤真
目次
通知表は保護者の信頼を大きく左右する
わが家の経験なのですが、息子の所見に「遠足のバスレク」についての記述しかないことがありました。レク担当として、バスでのゲームに熱心に取り組んでいたことが詳しく記述されていました。あまりほめることがない息子のために苦労して書いてくださったのだろうなあ、と同業者の私はその心中を察しましたが、「それにしてもバスレクしか書かないって……」と複雑な気持ちを抱いたのも確かです。
通知表の作成でもこのように、保護者は様々な印象を担任に抱きます。書き方1つで信頼を失うことも、逆に信頼を増すこともできるのです。
そこで今回は、年間を見通した通知表の作成術についてお伝えします。
さて、今年度、初めての通知表です。
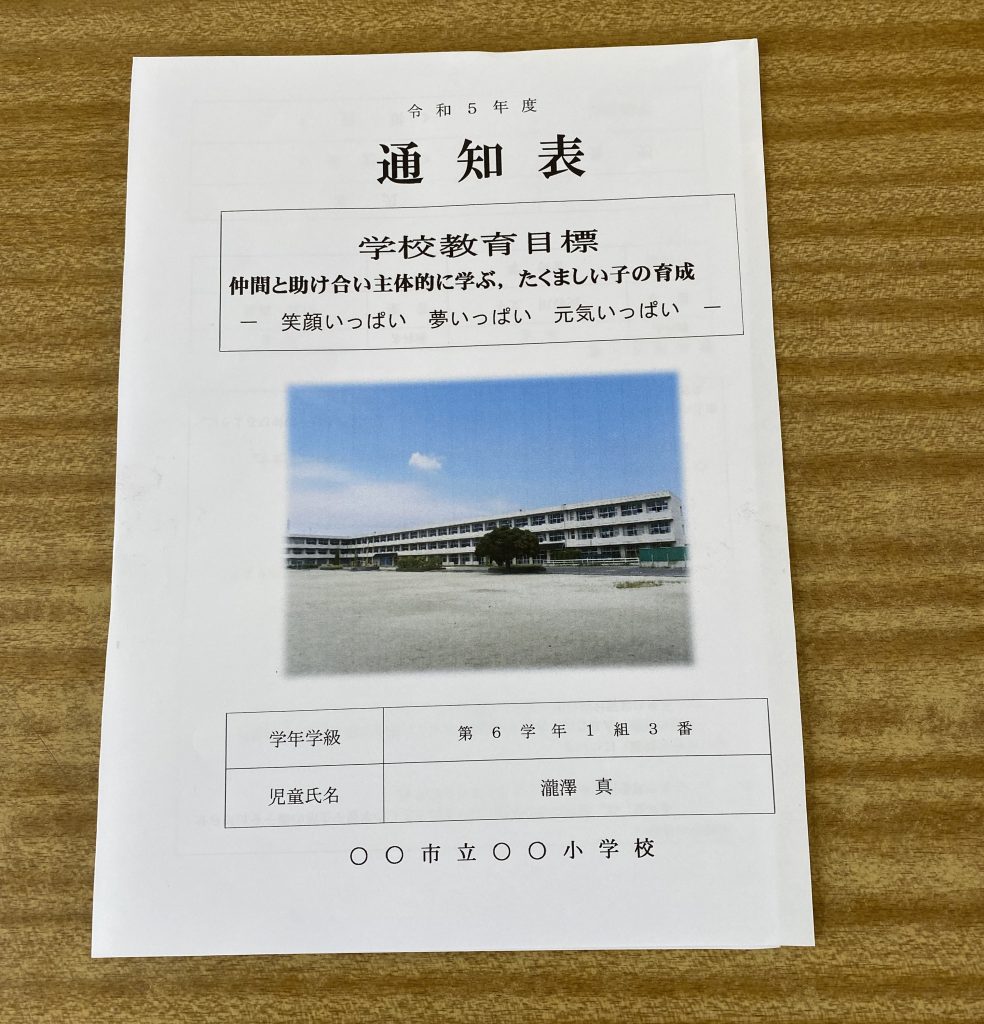
安心を伝える通知表のポイント
まずは保護者に「安心」してもらうことが大切です。残念ながら、わが子の成績に無関心な保護者がいることも確かです。一方で、関心の高い保護者は「わが子はしっかりとやれているのだろうか(やっていてほしい)」と、期待と不安が入り交じった状態でいるでしょう。
ですから、保護者がわが子の様子を知り、安心できるような工夫をしていきましょう。
以下、その具体的な方法をご紹介します。
①平易な言葉で書く
安心感を与えるといっても、文意が通じなければ意味がありません。そこで意識したいのが、一文を短くすることです。文が長いと、主述がねじれていたり、修飾関係が分かりにくかったりします。
また、保護者だけでなく祖父母が通知表を読むという場合も考えられます。そこで、学校特有の用語は使わないようにしましょう。例えば、「視写」「学習問題」といった言葉は、一般には通じません。
②意欲、態度に重点を置く
通知表の文章は、評価するという意識が強くなるあまり、「~~できました」「~~にはもう少し努力が必要です」というように、「できる」「できない」といった文意になりがちです。いろいろなことができる子であれば、特に問題ないのですが、そうではない子の場合に注意が必要です。
1学期だからといって「~~という点をもう少しがんばりましょう」などと書かれると、保護者の期待も、子供のやる気もそがれてしまいます。ですから、基本的には課題は書かないようにしましょう。
そこで、「まだ不十分ではあっても、努力していること」「がんばっていること」「前向きに取り組んでいること」を記述するようにすると、保護者も安心できるでしょう。
例えば、
○国語で習った詩を何度も音読し、すべて覚えることができました。
というような文章だと、暗唱できた子供しか認めることができません。

そこで、
○詩を覚えようと何度も繰り返し音読していました。
と、その努力の過程を認めるようにしていきましょう。
③周りの様子も付け加える
保護者にとっては、「わが子が学校になじめているのか」も気になるところです。そこで、その子が活躍した場面を記述した際に、周りの様子を付け加えると安心感が増します。
例えば、
○校歌を覚え、大きな声で伸び伸びと歌っていました。その様子を見て、周りの友達も元気よく歌うようになりました。

このように友達の反応などを書くことで、教室での様子がより詳しく伝わり、安心感のある通知表になります。
④事実のみの羅列にならないようにする
学校の方針で「事実しか書かない」ということもあるようですが、できれば「事実」に教師の意見を添えるようにしましょう。通知表の文章を「所見文」といいますが、「所見」の「見」は担任がどのようにその子を見たかということなのです。
A:リレーの練習に一生懸命取り組みました。
B:リレーの練習に一生懸命取り組むなど、やる気を感じました。
保護者はAとBの所見分を読んで、どちらに安心感をもつでしょうか。「やる気を感じた」という、ちょっとした一言に教師の温かみを感じるはずです。また、子供の意欲を高めることにもなるでしょう。

