「まとまる」ことを嫌い、避ける風潮(下) ー「不信と点検ばやり」からの脱却ー【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第38回】

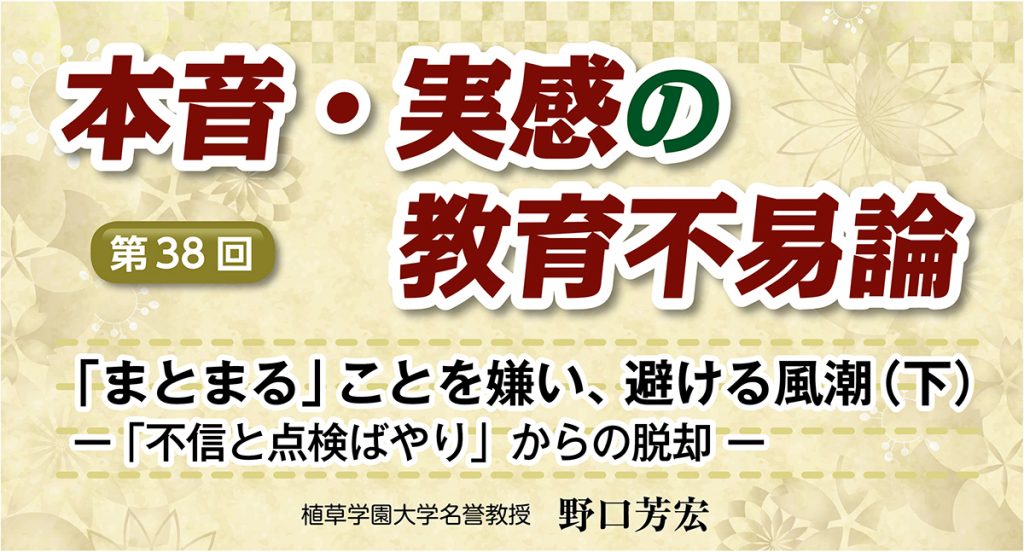
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第38回は、【「まとまる」ことを嫌い、避ける風潮(下) ー「不信と点検ばやり」からの脱却ー】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。
目次
5 プライバシーの尊重の行き過ぎ
曾(かつ)て親しい付き合いをしていた教師仲間に頼みたいことがあって、彼の勤務先の学校に電話を入れたところ、年度が変わって転出されたとのことであった。転出先の学校名を尋ねると、それは個人情報に当たるので教えられないとのことで吃驚した。転任というのは公的な人事異動であり、新聞などにも発表されている公然たる事実である。個人情報には違いないが、公人情報とも言えることだ。不当なプライバシーの侵害は許されまいけれど、転出先の校名も教えられないと言うのは妥当な考え方と言えるのだろうか。
ここには、「個人」あるいは「個」という存在や生活、立場に対する過度の「守秘」あるいは「立ち入り不安」が見てとれる。結果的に、彼の転任校へは事務の職員から連絡を入れてもらい、本人から私に電話をするということに落ちついたのだが、どうも後味が悪かった。もはやこのことは10年近くも昔のことなので、今はそのような対応が一般的で望ましいあり方として広まっているのかもしれない。
もう一つ、ある知人が引越しをしたというので新しい転居先を訪ねた折のことである。そこは集合住宅形式のアパートだったのだが、驚いたことにどこの部屋にも表札が全くなかったのだ。所番地は聞いてあったので見当はついたが、不安のままノックをして知人の苗字で確かめる仕儀となったが、これもまた何となく釈然としない思いが残ったことだった。
個人情報を不特定の人に対して公開する必要はない、という考え方も分からないではないが、表札も出さないというのでは郵便や新聞の配達、あるいは宅配便の届けなどには不親切にならないのだろうか。
社会生活をしていく上に、それほどまでに他者を恐れ、警戒し、自分のことを隠さなければならないというのは望ましいことなのだろうか。「不信の時代」は残念だ。
昔は当然のことのように、新しい年度が始まると学級ごとの電話連絡網が配られ、クラスの子供や家庭のことが一通り分かり合えたものだったが、今はそれもできなくなったと聞く。
学級連絡網は、そう頻繁に使われた訳ではないが、担任からの連絡や、ちょっとした友達の家との連絡などの折に便利であった。お互いが繫がり合っていることの安心感が連絡網によって保たれていたとも言える。お互いに知り合うことによって絆が生まれ保たれ、相互の親しみも増したのだったが、今はむしろ「知られることの恐れ」「知られることの煩わしさ」「知り合いたくない」という思いの方が強くなってしまったのか。
教育という立場からは、このような人間関係の変化をどのように捉え、解釈すべきなのだろうか。それは、決して良い変化とは言えまい。むしろ、そのような「不信」に基づく人間関係を改めて、昔のような「信用」「信頼」が生む「親しみ」「和合」の世の中に戻していく努力が必要なのではないだろうか。私はそのように考え、そのような教育への復帰こそが重要なのではないかと考えるのだが、私のような考え方は教育者としては時代錯誤、時代遅れということになるのだろうか。
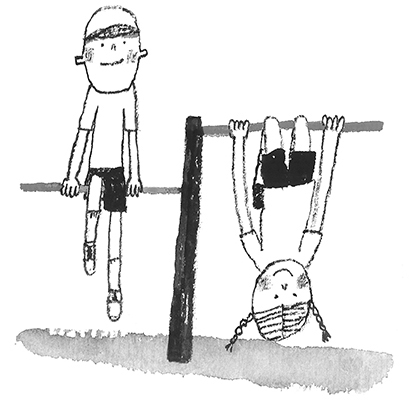
6 家庭訪問の今昔
新しい担任学級が決まると4、5月頃に「家庭訪問週間」が定められ、それぞれの子供の家庭を担任が訪問したものだったが、今はどうなのだろうか。
家庭訪問無用論が出始めたのは昭和の40年代の頃からだったように思う。都会からこの傾向が生まれたようだ。「子供の家庭を担任が見にくる必要はない。迷惑だ」というような考え方が始まりだったように思うが、その頃から「プライバシー」へのこだわりも生まれてきたようだ。
昭和41年というのは、私にとっては忘れられない年である。各県に男子師範学校と女子師範学校がそれぞれ附属小学校を持っていた時代がある。それぞれが統合され、現在の西千葉の千葉大学キャンパスに移転したのがこの年だ。私は昭和38年に公立小学校から旧女子師範の附属第二小学校に転じていた。この学校は千葉市の大空襲に遭い全焼したので、四街道町にあった陸軍砲兵学校の校舎に急遽移転していた。その際校区を四街道町内の一部に定めたので、国立の小学校にしては珍しく学区の子供を無試験で全て入学をさせていた。そこでは、一般公立校と同じくごく普通に家庭訪問がなされていた。
しかし、昭和41年に統合した附属小学校になると雰囲気が一変した。入学試験で合否を決める学区はほぼ通学1時間以内ということになったので、小学校としてはかなり広くなり、家庭訪問をすることが困難になった。また、プライバシー重視の考え方も台頭し始めたこともあって、ごく自然に家庭訪問という慣行もなくなってしまった。禁止をされた訳ではない。
附属第二小学校に転じて間もなく、家庭訪問週間になった折に先輩が、「そろそろ、あの庭の柿が実り始めるねえ」と、子供に話しかけられるような関係が、教師と子供を結び付けるんだよ、と話してくれた。小学校の教育というものは、要するに人間的な心の繫がりが一番大切なのだということであり、今になっても忘れられない一言だ。
どんな家に住んでいるのか。家庭環境はどんな様子か。周囲の様子、地域の様子、子供部屋、家族の人々などの有り様などに包まれてその子を把握する。それが大切なのだ、と深く思ったことだった。──という訳で私は担任をする子供の家庭は全て訪問しつづけた。
統合附属小学校になってもそれを貫いた教員は私だけだったが、どの家庭も喜んで迎え入れてくれた。千葉県の教育長をされた鈴木勲先生(後の文化庁長官)も私の訪問に合わせて在宅されたのには恐縮した。
学区が広いので歩いての訪問は難しかったので、都合のつく範囲で自家用車でのお手伝いをお願いしたが、どなたも快く引き受けてくれた。個人面接などの折に、訪問時の思い出を話したりすると「よく覚えていてくださった」と喜ばれ、親しまれた。
そういう間柄になれるのも家庭訪問の功である。プライバシーの侵害などと言う家庭は一軒とてなく、万事おおらかな、人と人とが信頼と親しみで結ばれていた時代だった。
夕食を供された家庭も、お酒まで共にして歓談した家庭も、お爺さん、お婆さんも総出で歓迎された家庭もあった。私もまたざっくばらんにその仲間に入って出合いを楽しんだ。孫の学校の話もこうして家族みんなで共有できたのだろう。教室の子供からお爺さんやお婆さんの話を楽しげに聞かされたこともある。
そんなことは一切無用。教室に来た子供に授業をし、学校で決められたことだけをやればいいのだ。お互いにプライバシーには触れるべきではない。公務はビジネスなのだから──という考えもある。そういう考え方もできる。
だが、そういう風潮の世情と、不登校やいじめ、虐待の発生や増加とは全く関係がないのだろうか。「先生なんか来てくれるな」「家の様子なんか見せたくもないし、見られたくもない」というようなプライバシー主義の考え方が広まることは、教育にとって良いことなのだろうか。世情の成り行きとして仕方のないことと考えるべきなのだろうか。
今でも家庭訪問を続けている学校も多くあるようだが、そのあり方が昔とは随分変わってきているようだ。
ア、家の中に上がってはいけない。
イ、滞在時間は10分間程度。全戸平等に。
ウ、家族状況などに立ち入らない。
エ、職業、学歴、出身などは話題にしない。
オ、お茶などは飲まない、などなど。
これでは訪問ではなく、それはビジネスでありリサーチであり、チェックに近い。こんなことなら、なくもがなという気にもなってくるが──。
人と人とが信じ合い、親しみ合い、仲良くできる社会が望ましいのである。そういう社会を目指す教育こそが求められねばなるまい。そうすれば、誰だっておおらかな、ゆったりした、温かい日々が送れる。
ぎすぎすした、不信を前提とした点検と調査が増え、点検と調査のデータによってしか安心できない社会では息苦しい。そういう社会がストレスを増大させ、人の心を荒ませるのだ。犯罪や思いがけない事件の多発は、教育のあり方の根本に対する警告、告発ともとれるのではないかと思うのだがどうか。

