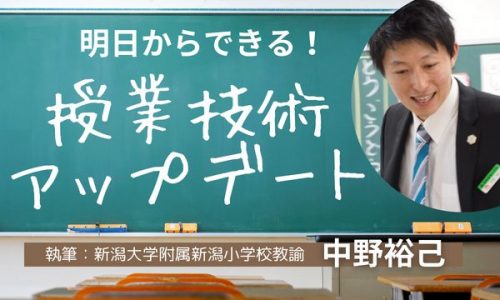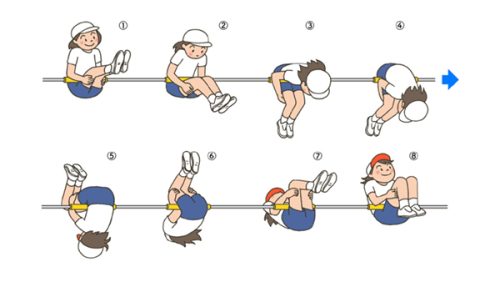小1算数「たし算とひき算」指導アイデア(1/2時)《たし算なのかひき算なのか》
執筆/福岡県公立小学校教諭・小野祐揮
編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏
目次
本時のねらいと評価規準(本時の位置 1/2)
本時のねらい
数量の関係に着目し、演算決定の根拠を図や言葉で説明する活動を通して、加法や減法を用いる問題場面の理解を深めることができる。
評価規準
問題場面の数量の関係を図で表現し、演算決定ができる。(知識・理解)

問題場面
①ひよこが11 わ、にわとりが3わいます。あわせて、なんわいますか。
②なわとびをしている人が、12 人います。一りんしゃをしている人が、5人います。
どちらが、なん人、おおいですか。
①と②の問題は、たし算とひき算、どちらの問題でしょうか。
①も②も、たし算かな。
①はたし算、②はひき算だと思う。
①の問題は、「11+3」と「11-3」のどちらだと思いますか。
(式を提示し、たし算かひき算かを挙手させる)
②の問題は、「12+5」と「12-5」のどちらだと思いますか。
(式を提示し、たし算かひき算かを挙手させる)
たし算なのかひき算なのか、どちらかな。
本時の学習のねらい
たし算なのかひき算なのか、ブロックや図を使って説明しよう。
見通し
・ブロックを使う。
・図を使う。
お話のどこを見て、たし算かひき算なのかと思いましたか。
①の問題は「あわせて」と書いてあるから、たし算。
②の問題は「どちらがなん人おおい」と書いてあるから、ひき算。
ほんとうに? たし算かひき算か、もっとわかりやすく説明できますか。
ブロックを使う。
図を描けばいい。
ブロックや図を使って、たし算かひき算かを説明しましょう。
自力解決の様子
A:つまずいている子
演算決定に、戸惑いがある。
B:素朴に解いている子
問題場面をブロックの操作や図で表現し、演算を正しく決定している。
C:ねらい通りに解いている子
問題場面の図を基にして、演算決定の根拠を言葉で説明することができる。
自力解決と学び合いのポイント
イラスト/佐藤雅枝、横井智美
『小一教育技術』2019年1月号より