保護者との意識合わせ、校長ができることは多い【妹尾昌俊の「半径3mからの“働き方改革”」第13回】
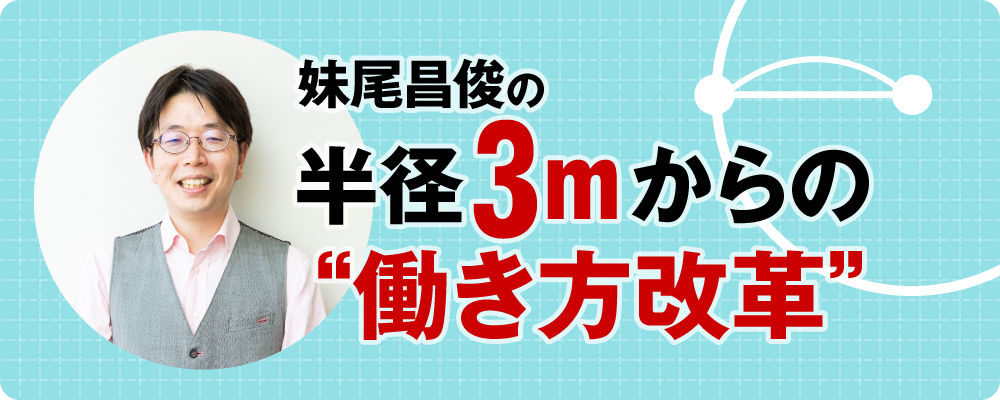
学校の“働き方改革”進んでいますか? 変えなきゃいけないとはわかっていても、なかなか変われないのが学校という組織。だからこそ、教員一人ひとりのちょっとした意識づけ、習慣づけが大事になります。この連載では、中教審・働き方改革特別部会委員などを務めた妹尾昌俊さんが、「半径3m」の範囲からできる“働き方改革”のポイントを解説します。
執筆/教育研究家・一般社団法人ライフ&ワーク代表理事・妹尾昌俊
目次
保護者、地域との接点となるのは誰か
学校の働き方改革に本腰を入れて進めると、保護者や地域の意見やニーズと時として合わなくなる。2019年に中教審でも働き方改革についての答申が出たが、当初の素案では、文部科学省が学校と社会の「バッファ(緩衝)」として機能するように、との文言だった。これが学校と保護者、地域等との対立をはなから前提としているようではおかしいなどの意見もあり、確定された答申では「起点・つなぎ役」という表現になった。
この修正の是非はともかくとしても、「あれもやりましょう、これもやりましょう」と八方美人的な学校経営や教育行政をしてきたから、今日の多忙があるのではないか、と思う。時として意見の相違や衝突があることから逃げていては、抜本的な解決にはならない。
それに、社会とのバッファにせよ、起点・つなぎ役にせよ、国の役割も大きいことは否定しないが、いちばん最前線でそうした役割を発揮するのは学校長である。ほとんどの保護者等は、文科省の役人には会ったことはないが、校長の顔なら分かるだろう。
国頼みで大丈夫か?
私が講演・研修などで、校長や副校長・教頭からよく聞くコメント・質問として、「学校は、これはしなくてよいと、国がもっと言ってくれないか」というものがある。
この気持ちはよくわかる。学習指導要領などで国はあれこれ増やしてきたのだから。だから国もしっかり反省して行動してもらいたいと強く思う。だが、同時に考えないといけないのは、国立学校でもないのに、国に頼りきるというような意識で本当に大丈夫か、ということである。
例えば、学校行事や部活動の運営については、かなり広範に学校の裁量、校長の権限が認められている。国が細かく何時数は取りなさいとか、ソーラン節はやりなさいとか、サッカー部はなくては困りますとか、言っていない。教育委員会もそういう“指導”はしていないはずだ。
ところが、行事や部活動の大きな見直しとなると、冒頭に述べたように、保護者等から往々にして反対がある。そのあたりを学校側は“忖度”して、なかなか前に進まない、進めようとしない。一方では、働き方改革、業務改善というと、決まって「会議を見直しました」と言う校長等が多い。これは、保護者も教職員も、誰も反対しないから進めやすいのかもしれない。
データでも確認できるが、行事の準備や部活動指導の時間が教師の多忙のかなりの大きい部分を占めることは事実だ(学校ごとのちがいもあるが)。会議の効率化も進めてほしいが、それだけでは足りない。辛口なことを書くようだが、現在、あなた方、校長や関係者(私を含めて)の本気度が試されていると思う。ひよっている場合ではない。

