担任が視点を変えると学級が落ち着く〈後編〉【伸びる教師 伸びない教師 第20回】
- 連載
- 伸びる教師 伸びない教師

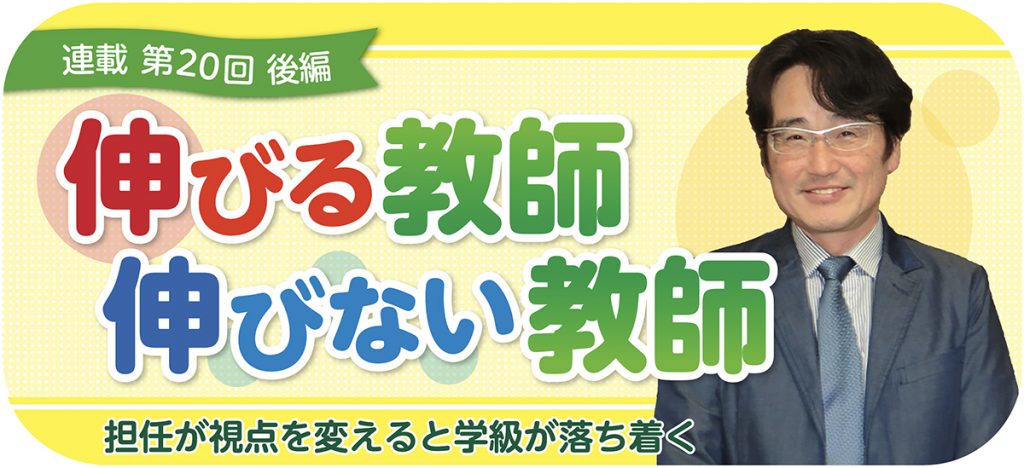
今回は、「担任が視点を変えると学級が落ち着く」の後編です。やんちゃな子供たちに目がいき、注意ばかりをしていたことから、きちんとしている子に視点を変えることによって、学級が安定してきたという話です。豊富な経験で培った視点で捉えた、伸びる教師と伸びない教師の違いを具体的な場面を通してお届けする人気連載です。
※本記事は、第20回の後編です。
執筆
平塚昭仁(ひらつか・あきひと)
栃木県上三川町立明治小学校校長。
2008年に体育科教科担任として宇都宮大学教育学部附属小学校に赴任。体育方法研究会会長。運動が苦手な子も体育が好きになる授業づくりに取り組む。2018年度から2年間、同校副校長を歴任。2020年度から現職。主著『新任教師のしごと 体育科授業の基礎基本』(小学館)。
伸びる教師は、全体を見ながら子供たちのよい点に目を向け、伸びない教師は狭い視野でできない点に目がいく。
目次
やんちゃな子供たちばかりに目がいく
教師の目は、視野を広げるだけでなく「何を見るか」という視点も大切になってきます。
私が20代の頃、担任していた高学年の学級の中にやんちゃな子供たちが何人かいました。
授業中のおしゃべりから友達への意地悪など、担任として指導することが多くありました。
あるとき、教室に入ろうとすると授業開始時刻は過ぎているのに騒がしい声が聞こえてきました。ドアを開けると2~3名の子供たちが自分の席から離れ、友達とおしゃべりをしていました。
「時間が過ぎているのに何しているんだ。出歩いていた人、話ししていた人、全員立ちなさい」と声を荒げながら厳しく指導をしました。また学級全体にも、お互いに注意をしていかなければよい学級にはならないと強い口調で話しました。
そんな日が続いたある日、保護者から「子供が学校へ行くことを渋っている」との連絡を受けました。理由を聞くと、私がやんちゃな子供たちを指導しているのを毎日聞いていて、いつか自分も叱られるのではないかと不安になり、学校へ行くのが嫌になったとのことでした。


