子どもの一日に思いをはせる【妹尾昌俊の「半径3mからの“働き方改革”」第2回】
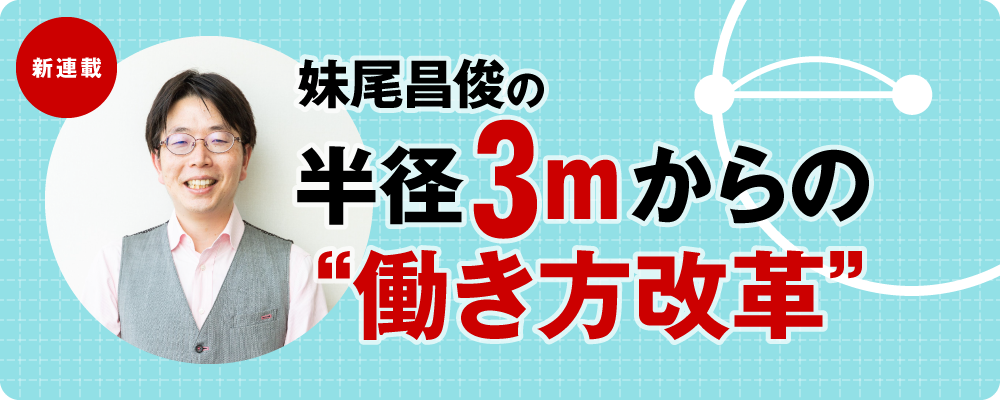
学校の“働き方改革”進んでいますか? 変えなきゃいけないとはわかっていても、なかなか変われないのが学校という組織。だからこそ、教員一人ひとりのちょっとした意識づけ、習慣づけが大事になります。この連載では、中教審・働き方改革特別部会委員などを務めた妹尾昌俊さんが、「半径3m」の範囲からできる“働き方改革”のポイントを解説します。
執筆/教育研究家・合同会社ライフ&ワーク代表 妹尾昌俊
目次
先生に覚えておいてほしいこと
新年度が始まり、4月、5月は、読者のみなさんにとって、一年でもっとも慌ただしい時期かもしれない。学級担任の先生であれば、子どもたちの名前は覚えただろうか? わたしは人の名前を覚えるのがすごく苦手なので、先生たちは本当にすごいなと思う(趣味の戦国武将の名前なら100人くらい大丈夫なのだが)。
今日は、そんなみなさんにぜひインプットしてほしいことがある。それは、子どもたちの一日を想像してみようということだ。
やりたい生徒がいるのに部活時間を規制する意味
ところで、スポーツ庁が「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を取りまとめて数年が経つ(2018年3月策定)。当時、わたしも有識者会議のメンバーとして相当積極的に発言してきた(蛇足だが、元アスリートかスポーツ指導者の委員に囲まれる中、わたしはブラスバンド部出身の文化系だった)。休養日を週2日以上設けることや、平日は2時間程度以内、土日も3時間程度以内におさめることなどを求めている(以下、ガイドラインのポイント)。
【運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの主なポイント】
・学校で行われる運動部活動を対象としている。文化部は対象外。
・中学校も高校も対象である(高校は原則、適用)。
・週当たり2日以上の休養日を設ける(平日は少なくとも1日、土曜日及び日曜日は少なくとも1日以上を休養日)。
・1日の活動時間は、長くとも平日では2時間程度、学校の休業日は3時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。
・より多くの生徒の運動機会の創出が図られるよう、季節ごとに異なるスポーツを行う活動、競技志向でなく友達と楽しみながらレクリエーション志向で行う活動なども検討する。
・大会について、中体連等は、複数校合同チームの参加、学校と連携した地域スポーツクラブの参加などの参加資格の在り方、大会の規模もしくは日程等の在り方等の見直しを行う。
・地域の実情に応じて、地域全体で、これまでの学校単位の運動部活動に代わりうる生徒のスポーツ活動の機会の確保・充実方策についても検討する。
運動部に関係する人もしない人も、ぜひ考えてほしい。なぜ、こんな規制をするのかという理由をだ。学校現場の中には(そして評論家等の一部にも)、「もっと練習したい、強くなりたい生徒もいるのに、どうして制限しようとするのだ」というもやもやとした疑問、あるいは反発もあろう。
大きな理由のひとつは、スポーツへの参加時間が長ければ長いほど、けがや障害になる確率は高くなることが、実証されているからだ。
実際、週16時間以上の場合、ないし“年齢×2時間”より多い場合は、けがの発生率が高いとの研究が複数ある。ちなみに、これは体育の時間なども含めての時間だ。
ほかにも理由はある。それが、冒頭で述べた子どもたちの一日を想像せよ、ということに関係する。わたしは、有識者会議の最終回で次の趣旨の発言をした。
7時半から朝練をして、放課後は19時まで練習する。そんな部活は全国あちこちにあります。では、その生徒たちの残された時間はどのくらいでしょうか? 通学時間を除くとあと11時間ほど。生理的な活動、つまり、めし、フロ、トイレなどに約2時間かかると残り9時間です。この中から、勉強をしたり(家庭学習や塾)、友達とラインでやりとりしたり、家族としゃべったり、ゲームなど自由気ままに過ごしたりする時間を、そして睡眠時間を捻出しないといけません。勉強時間や睡眠時間を削らないとかなり無理がある一日だと思いませんか? 部活のやりすぎはなぜいけないか。24時間は限られているのだから、部活があまりにも子どもたちの自由時間等を侵食してはいけないのです。

