日本社会がギフテッドを受容するための課題とは【ギフテッドシンポジウム in 鹿児島 #1】
ギフテッドとは、「高い知的能力を持ち、さまざまな潜在的可能性を秘めた、配慮や支援が必要な子ども」です。必要なサポートが受けられず、不登校になる子もいます。ギフテッド支援の最前線にいる研究者、教育実践家、保護者団体の代表が一堂に会した「ギフテッドシンポジウム」の様子を5回シリーズでお届けします。
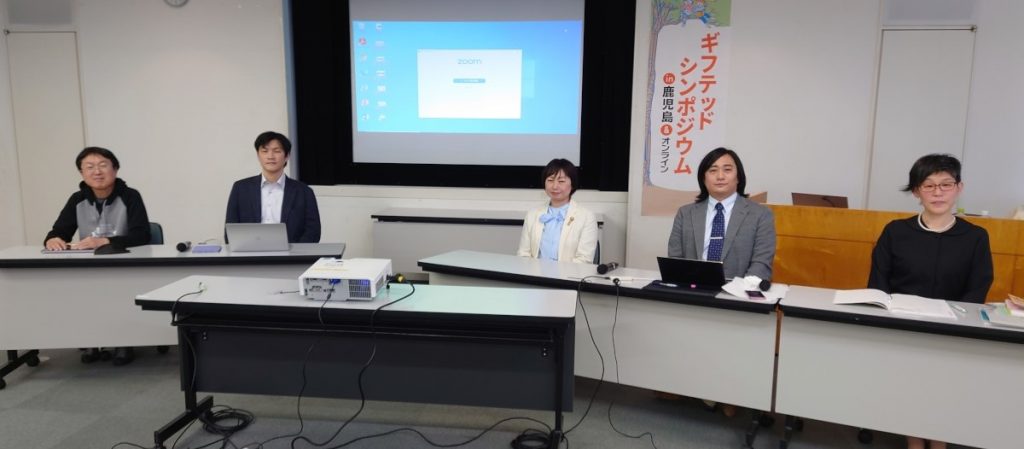
シンポジウムは、2022年3月6日(日) 鹿児島県霧島市で開催され、Youtube生配信(この記事の最後に無料配信アーカイブあり)も行われました。基調講演は、北海道大学名誉教授の室橋春光先生です。
取材・執筆/楢戸ひかる
目次
文部科学省の有識者会議で話し合われていること
室橋先生の講演は、「ギフティッドあるいは特定分野で特異な才能のある子供について」というタイトルで、文部科学省で令和3年7月から始まった「特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に対する有識者会議」で、話し合われている内容の整理から始まりました。
特定分野で特異な才能のある子供の定義は、こんな感じです。
定義
・概ねの傾向 IQなどによる一律の基準を設けず、大綱的な定義が多い。
・知能検査や認知能力検査、学力テストなどが活用されているが、教師や本人の質問紙やチェックリストなどを包括的に活用する例もある。
・才能全般的な特徴=「普通より優れた能力」+「創造性」+「課題への傾倒」。
特性
・強い好奇心や感受性、豊かな想像力、高い身体的活動性、過敏な五感など、機能間の発達水準に偏り、これらの特性に伴う困難を抱える。
・Twice-exception:2Eの存在。
(室橋先生発表資料より筆者抜粋)
有識者会議のアンケートからは、子どもたちのリアルな困難感が見えてきます。
学習に関する困難
・書く速度の遅さと脳内の処理速度が釣り合わず、プリント学習にストレスを感じていた。
・発言をすると、授業の雰囲気を壊してしまい、申し訳なく感じてしまうので、わからないふりをしていたが、それも苦痛で、授業中に自分を見出すことができなかった。
・授業がつまらないため、登校しぶり、不登校になった。
学校生活に関する状況
・早熟な知能に対して情緒の発達が遅く感情のコントロールが未熟なので、些細な事で怒られてしまったり泣けてしまったり、他の児童と言い合いになったりしてしまう 。
・学校の友達と話すとき、言葉を簡単にしなければ、話が通じ合わない。
音に敏感で通常の学校生活をおくる事が困難。
・感覚過敏のため、給食をほとんど食べることができない。
効果的な取り組み
・自己肯定感が低いので、自信をつけさせる声がけをしていただいたことが有効だった。
・ICTの活用、児童生徒の特性に応じた口述・筆記を選択できるようにして、読み書きなど学習上の困難への支援が効果的だった 。
・ 支え合う友人関係の構築や教師間の情報共有、スクールカウンセラー・養護教諭、学校司書などによる支援によって、学校生活を円滑におくる事ができた 。
(室橋先生発表資料より筆者抜粋)
子どもたちのサポートは当然として、室橋先生がとりわけ強調されていたのは、保護者サポートの必要性です。
児童生徒だけでなく、保護者も様々な悩みを抱えている。保護者へのサポートをいかにおこなっていくかという点もしっかりと視野に入れる必要がある。
文部科学省の会議では、諸外国の状況についても報告があります。
諸外国の状況から
1950年代より始まったギフテッド教育は、アメリカが先進国です。アメリカでは当初、国家がギフテッドの子を取り出して教育する「国家中心的」な教育を行っていましたが、最近は学習者に沿って進める「学習者中心」の教育に変化しています。
フィンランドでは、「学習者中心」かつ「インクルーシブ型」ですが、個々の教師の裁量に任されているので、体系的とは言えないようです。韓国、シンガポール、中国は、「国家中心的」で「取り出し型」の教育で、韓国には、「英才教育促進法」という法律もあります。
(室橋先生発表資料より筆者抜粋)

