【木村泰子の「学びは楽しい」#44】多様な子供たちの「深い学び」を確かなものに~次期学習指導要領の論点整理を踏まえて~

子どもたちが自分らしく生き生きと成長できる教育のあり方について、木村泰子先生がアドバイスする連載の44回目。今回は、2026年9月25日に文部科学省中央教育審議会より示された次期学習指導要領に関する「論点整理」について考えていきます。(エッセイのご感想や木村先生へのご質問など、ページの最後にある質問募集フォームから編集部にお寄せください)【 毎月22日更新予定 】
執筆/大阪市立大空小学校初代校長・木村泰子

目次
次期学習指導要領の基本的な考え方とは
2学期に入ってからも夏のような日々が続き、暑さの中で運動会を終えた学校も多くあるのではないでしょうか。最近の教員研修でも始まる前から眠ってしまっている人を見かけますが、ほんとに疲れているって感じが伝わってきます。このあたりでちょっと一息ついて、先のことを考えてみませんか。
現在、次期学習指導要領の論点整理が行われているので紹介します。論点整理では、「次期学習指導要領の基本的な考え方」として、以下の内容が提起されました。
「生涯にわたって主体的に学び続け、多様な他者と協働しながら、自らの人生を舵取りすることができる、民主的で持続可能な社会の創り手を 『みんな』で育むため」として、 次の三つの方向性が提起されています。
1.「主体的・対話的で深い学び」の実装
2.多様性の包摂
3.実現可能性の確保
また、この三つの方向性を現時点で端的に表現すれば、「多様な子供たちの深い学びを確かなものに」と言えるとし、第一の方向性は「深い学び」、第二の方向性は「多様な子供たち」、第三の方向性は「確かなもの」という言葉に主に託されているとしています。さらに、「みんな」が示す主体は、学校教育の未来を切り拓く中心的存在である学校の教職員はもとより、学びの当事者である子供、人口減少の中で学校を支える主体でもある、保護者や地域住民、地方公共団体の職員、民間の担い手も含まれ、「社会に開かれた教育課程」や「個人と社会のウェルビーイングの実現」といった理念とも深く関わると記されています。
また、諮問の中で「正解主義」や「同調圧力」への偏りから脱却し、民主的かつ公正な社会の基盤としての学校を機能させる必要性が指摘されていますが、その背景には社会の構造変化があるとされています。これらをまとめると、
「生涯にわたって主体的に学び続け、多様な他者と協働しながら、自らの人生を舵取りすることができる民主的で持続可能な社会の創り手をみんなで育む」ことで、「よりよい学校教育」を通じて「よりよい社会」をつくること
を示唆しています。つまり、社会を変え、未来をつくるのは「学校教育」であることが明確に言語化されているのです。
読者のみなさん、次期学習指導要領に向けた基本的な考え方をどのように受け止められましたか。いくつかお伝えしたいことがあるのですが、まず、「正解主義」や「同調圧力」への偏りからの脱却についてすぐにでも行動しませんか。多様性社会・共生社会・予測困難な社会において「生きて働く力」は、「正解のない問いを問い続ける力」です。すべての授業を通して学力の上位目標に「正解のない問いを問い続ける力」を置いて日々の授業を問い直してみませんか。
同調圧力の脱却についてはどうでしょうか。みんなと違う発言をしたり、違う行動をとったりする子どもを叱っていませんか。大人が正解をもっていたら、つい、大人の正解のワクに子どもをはめ込みたくなるものですが、これだけは問い直しましょう。この「正解主義」と「同調圧力」からの脱却は、「子どもが主語」の学びの実現に向かう手段です。常に職員室で自浄作用を高めていきたいですね。
次期学習指導要領の方向性は、これまで「学びは楽しい」のコーナーでみなさんと問い直し続けてきた内容が明記されています。ただ、言葉の一人遊びで終わらせないように、子どもの事実に返す大人の行動をアップデートしたいですね。
今回は、先に挙げた「2.多様性の包摂」について、一緒に考えたいと思います。
「多様性の包摂」について
文部科学省は、2022年4月の通知で、小中学校の特別支援学級に在籍する子供は原則として1週間の授業の半分以上を特別支援学級で受けるように求めました。この通知の影響により、今や全国の学校現場で「『ふつうの子』と『特別の子』に分かれなさい。『特別の子』は1週間の半分以上は特別の教室で支援担当から自立の支援を受けなさい」という状況になっています。この通知は、「多様性の包摂」とは対極にある手段で、多くの人は矛盾を感じているでしょう。では、現場はどうすればよいのでしょう。
この通知はあくまでも文科省の「手段」です。文科省の目的は「誰一人取り残さない学校をつくる」ことです。通知を守るために、子ども同士を分断してその目的が達成できるならやればいい。でも子ども同士を意図的に分断して目的が達成できないのなら、通知を守るという手段をとってはいけないはずです。ここは、子どもの前にいる教職員のみなさんが主体性と当事者性をもって判断することなのです。
目的は「誰一人取り残さない学校」つまり、「すべての子どもが無理をしないで行ける学校」をつくることなのです。通知ありきで子どもがそのくくりに入れられることは、「包摂」とは真逆です。何よりも「障害」のある子は自分で自分の学びの場を決めることはできないのでしょうか。それは「子どもの権利条約」に違反しています。
「この通知がおかしい!」「文科省がおかしい!」などと批判することも必要かもしれませんが、その前に学校の大人の一人一人が主体的に対話を重ね、どうすれば誰一人取り残すことのない学校づくりができるかを行動で示していくことが求められています。
義務教育期に「特別」があっても、社会に「特別」はありません。まずは小学校から学校を地域社会の「環境」にしなければ、「社会につながる力」は獲得できません。
「多様性の包摂」が実装できる学校にチャレンジを!
(参考文献)文部科学省中央教育審議会 教育課程企画特別部会「論点整理」(令和7年9月25日)
〇次期学習指導要領の三つの方向性「1.主体的・対話的で深い学びの実装」「2.多様性の包摂」「3.実現可能性の確保」を確認し、諮問でも示された「正解主義」や「同調圧力」への偏りから今すぐ脱却していこう。
〇すべての授業を通して、これからの社会で「生きて働く力」となる「正解のない問いを問い続ける力」をつけることを学力の上位目標に置こう。
〇義務教育に「特別」があっても、社会に「特別」はない。「誰一人取り残さない学校」をつくり、「社会につながる力」を育むために、大人一人一人が主体性と当事者意識をもって、対話を重ね、行動していこう。
【関連記事はコチラ】
【木村泰子の「学びは楽しい」#43】子どもと子どもをつなぐ
【木村泰子の「学びは楽しい」#42】障害に応じた対応ではなく、一人の人として
【木村泰子の「学びは楽しい」#41】「大空20祭」が教えてくれたこと
※木村泰子先生へのメッセージを募集しております。 エッセイへのご感想、教職に関して感じている悩み、木村先生に聞いてみたいこと、テーマとして取り上げてほしいこと等ありましたら、下記よりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。
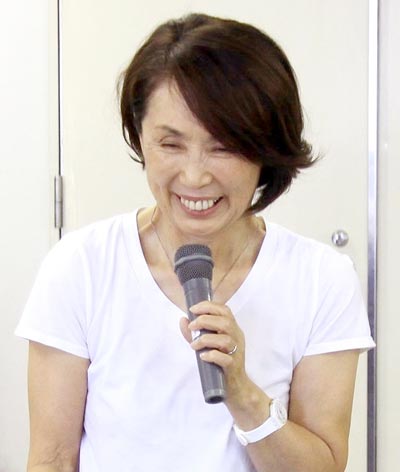
きむら・やすこ●映画「みんなの学校」の舞台となった、すべての子供の学習権を保障する学校、大阪市立大空小学校の初代校長。全職員・保護者・地域の人々が一丸となり、障害の有無にかかわらず「すべての子どもの学習権を保障する」学校づくりに尽力する。著書に『「みんなの学校」が教えてくれたこと』『「みんなの学校」流・自ら学ぶ子の育て方』(ともに小学館)ほか。
【オンライン講座】子どもと大人の響き合い讃歌〜インクルーシブ(共生)な育ちの場づくり《全3回講座》(木村泰子先生✕堀智晴先生)参加申し込み受付中! 大空小学校時代の「同志」お二人によるスペシャルな対談企画です。詳しくは下記バナーをクリックしてご覧ください。


