学んだことが実践に結びつかない! 改善策はどうする?

学級経営・特別活動を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、教育現場で見て気になったことについて、ズバリと切り込みます。
文・稲垣孝章(元・埼玉県東松山市立公立小学校校長)
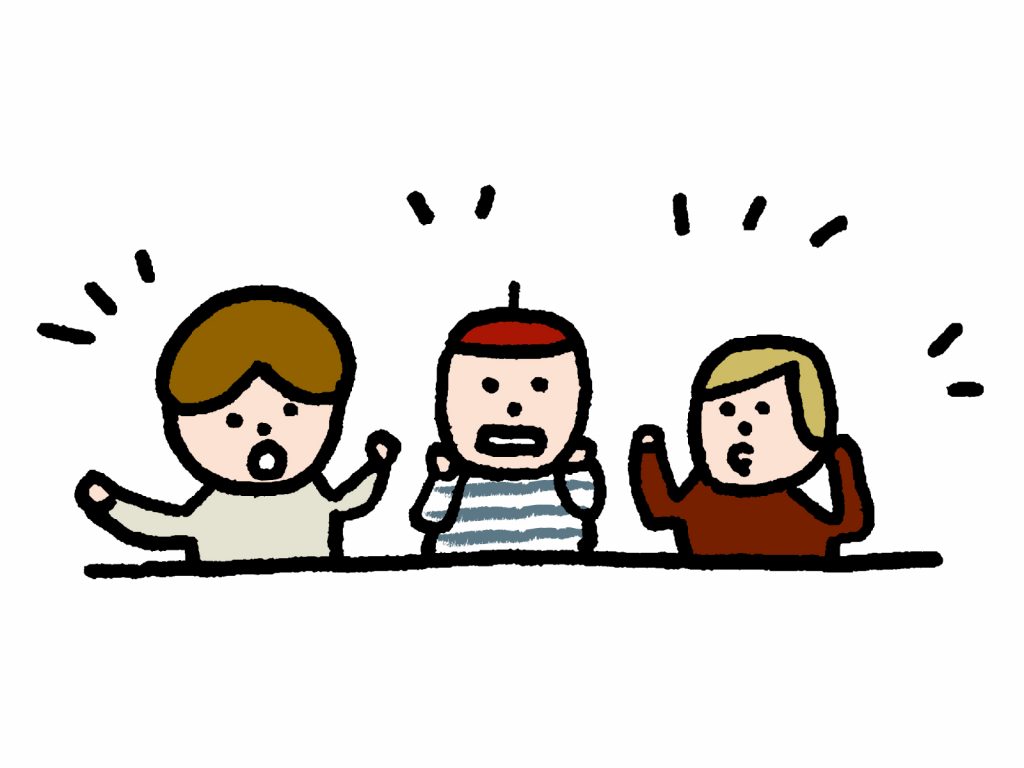
目次
講義法と集団決定法、どちらが実践に結びつく?
レヴィン(Lewin,K.)は「食習慣の変化に関する研究」で、次のような実験結果を報告しています。
13~17人からなる赤十字の6つの集団を対象に、「牛の内臓に関する食習慣の変化」について、講義法と集団決定法の比較を行いました。3つの集団には、牛の内臓の栄養的価値、経済性、料理法について詳細に「講義」し、残り3集団には、一般的な問題から入って同じテーマについて集団討議をした後に、「集団決定」を行いました。
1週間後に調査したところ、「講義を受けた集団の3%、集団決定では32%」が実際に牛の内臓を食生活に使用したということです。
この実験から明らかなように、学習を通して学んだ知識が実践として結びつきやすいのは、講義法より集団決定法であることがわかります。この視点は、まさに授業にも当てはまります。
講義法は、多くの知識を伝達するという点では効率のよい手法です。そして、学年が上がれば上がるほど、指導事項として教えなければならないことが多くなり、どうしても講義的な授業になってしまう傾向にあることは否めないという現状がみられます。しかし、教師の一方的な講義法による知識の伝達だけでは、実践に結びつく学習活動となりにくいことは、教師であれば誰もが感じていることだと思います。
ある学校の研修会で、養護教諭から次のような相談を受けました。
「外部指導者を招いたり、多種多様な資料を子どもたちに提示したりして、歯磨き指導の授業を行ってきたのですが、どうしても子どもたちの実践が継続されません」と。
そこで、次の三つの視点を授業に取り入れて、事後の実践まで根気強く指導してもらいました。
「①子どもたちが課題に対して集団思考ができる場面 ②自分なりの具体的な実践方法を自己決定できる場面 ③授業後に2週間程度、実践を毎日振り返り、自己評価できる場面」を設定するというものです。
この指導の結果、どの子も歯磨きへの意欲をもち、継続的に実践に取り組みました。ただし、実践を継続させるためには、実践後に新たな個々の課題を明確にし、具体的な行動目標を再設定することの必要性が取り上げられました。


