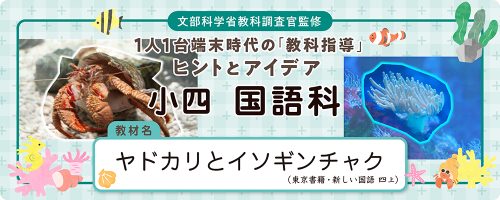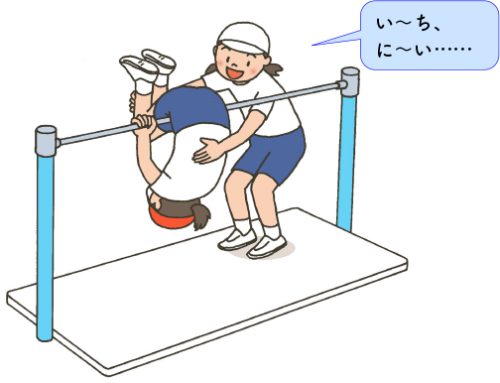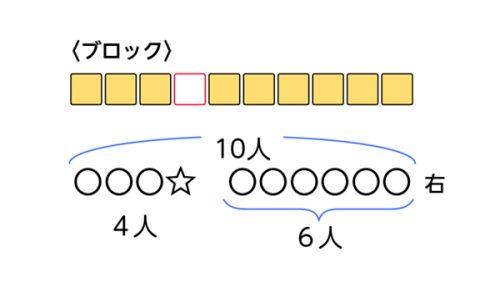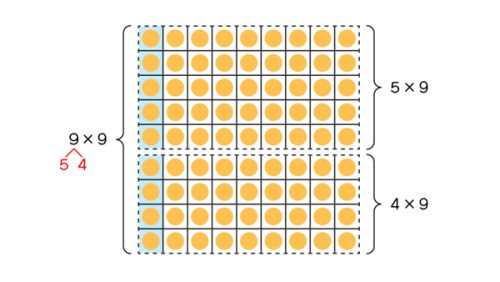小6理科「電気の利用」指導アイデア
執筆/大阪府公立小学校首席・西岡賢一
編集委員/文部科学省教科調査官・鳴川哲也、大阪府公立小学校校長・細川克寿
目次
単元のねらい
電気の量や働きに着目して、それらを多面的に調べる活動を通して、発電や蓄電、電気の変換についての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に、より妥当な考えをつくりだす力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する。
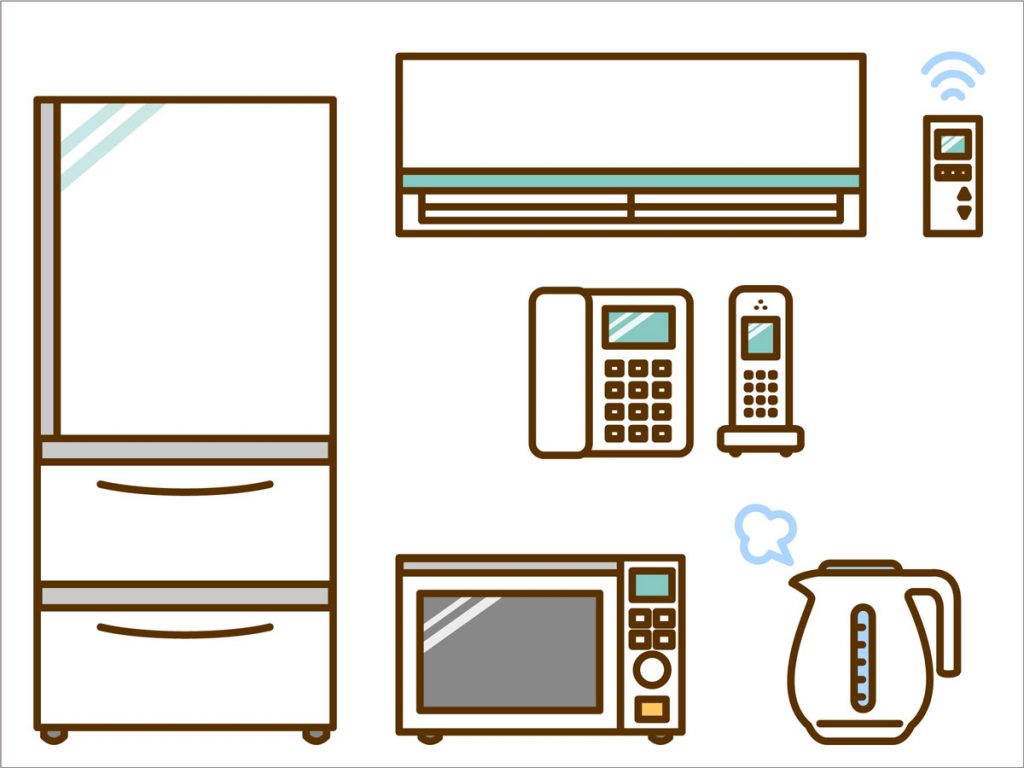
単元の流れ (四次 総時数 11時間)
一次 発電(3時間)
① 私たちの暮らしの中で、電気がどのような場面で利用されているのかを話し合う。
部屋の明かりやスマートフォン、エアコンなどたくさんあるね。
暮らしの中には、電気製品があふれているね。
電気はどうやってつくられているのかな。
自転車のライトや太陽光発電のパネルを見たことがあるよ。
② 手回し発電機と光電池を使い、モーター・豆電球・LED・電子ブザーなどの電気製品を動かすことで、発電ができるかを調べる。
子供が主体的に問題解決に取り組むために、手回し発電機や光電池を使って、身の回りの電気製品を動かすことなどによって、問題発見を行うとよいでしょう。この時、手回し発電機を回したときの手応えから、電気製品によって必要とするエネルギーの大きさが違うことを感じたり、乾電池と違って、安定して電気が得られないので、安定して電気を利用するためには工夫が必要なことに着目し、蓄電の必要性へとつなげたりすることも大切です。
二次 蓄電(3時間)
① 手回し発電機や光電池を使って電気をコンデンサーに蓄電し、電気製品を動かすことで、蓄電することができるのかを調べる。
蓄電すると、モーターなどが安定して働くね。
光を出すのは同じでも、豆電球とLED の手応えが違ったよ。蓄電して光らせても違いがあるのかな。
② コンデンサーに同じ量の電気を蓄電し、豆電球とLED の点灯時間が違うかを調べる。
三次 電気変換(2時間)
① 身の回りの電気製品は、電気をどのようなエネルギーに変換しているのかを調べる。
手回し発電機・光電池が、手の運動・太陽の光を電気に変換しているものとして捉え、身の回りの電気製品が、電気を運動・光・熱・音・磁力などに変換しているものとして捉えることで、電気を媒体とした生活へと見え方が変化していきます。
四次 電気の利用(3時間)
① センサーライトを使うことで、蓄電した電気がどれだけ長持ちするのかを調べる。 【活動アイデア例】
身の回りの電気製品は、プログラミングで制御することにより、自然エネルギーの有効活用を図っていると捉えることで、これからの暮らしについて考え、深い学びとなるようにします。
② 発電方法や生活の中での電気の利用について学んだことをまとめる。
単元の終わりに期待される振り返り
- 発電所では、手回し発電機や光電池と同じ仕組みで、自然エネルギーを電気エネルギーに変換しているんだね。
- 電気は電線をつなぐことで必要な場所に届けて、必要なエネルギーに変換して使うことができるからとても便利だね。
- いつも当たり前にあると思っていたけれど、エネルギーは大切に使わないといけないね。
授業の展開例
「電気の利用」では、エネルギー資源の有効利用という観点から日常生活を見直すことで、「センサー」や「プログラミング」に気付き、実際に体験的に学習するからこそ、内容を深く理解することにつながります。
また、プログラミング教育を行うことで、理科で学んだことが自分たちの生活や社会と関係しているという意識が高まり、理科を学ぶことの意義や有用性を実感することにつながります。
問題 センサーを使うと、どれだけ電気が効率的に使われるのだろうか。
解決方法の立案
イラスト/高橋正輝、横井智美
『教育技術 小五小六』2020年2月号より