“学級活動”こそ、性教育の“本丸”です!【教室から始める性教育~“いのち”と“多様性”を育てる授業】#3
小学校や中学校で性教育の指導に長年携わったスペシャリストである、帝京平成大学教授・郡吉範先生による連載「教室から始める性教育~“いのち”と“多様性”を育てる授業」の第3回目です。この連載では、安心して実践できる基礎的・基本的なことがらやすぐに使えるヒント、ちょっと背中を押す言葉などをお届けします。第3回のテーマは「“学級活動”こそ、性教育の“本丸”です!」。学級活動における性教育とはどのようなことかを紹介します。具体例は、郡先生の経験や現場での実践に基づくものですので、現場でのヒントにしてください。
執筆/帝京平成大学人文社会学部教授・郡 吉範
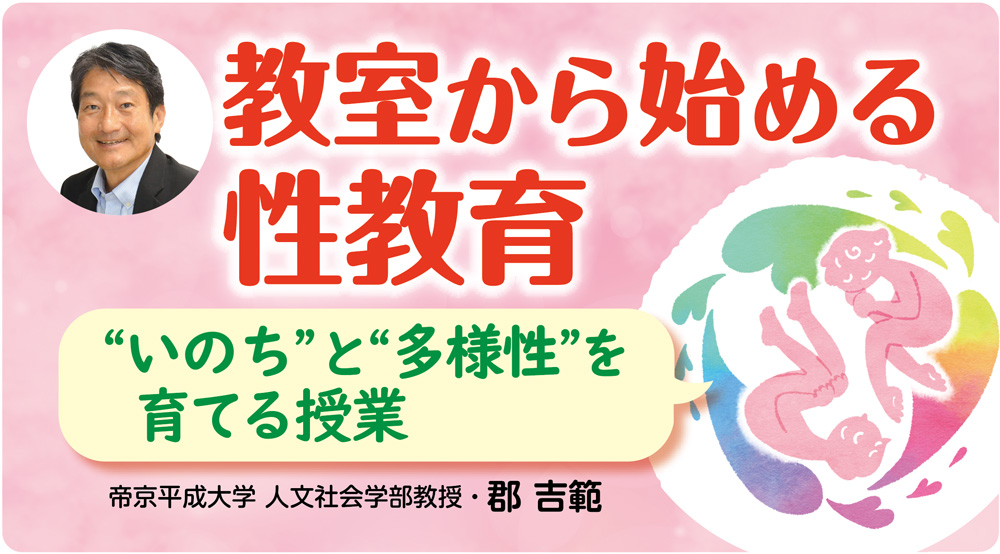
目次
実は、とても大事な「学級活動」
性教育にとって重要なのが「学級活動」です。包括的性教育の視点から見ても、この時間はまさに“本丸”とも言えるくらい大切な場面です。
ただ、ここで意外と多いのが、「毎年、学級活動やっているよ」という先生はたくさんいても、その中身が「毎年、繰り返し教えるべき内容」であることに気付いていないというケースです。
例えば、小学校学習指導要領には、以下のような項目が明記されています。
・よりよい人間関係の形成
・男女相互の理解と協力
・思春期の不安や悩みへの対応
・性的発達に関する理解
これらのテーマ、どう見ても性教育に直結していますよね。そして、これらは「どこかの学年で一度やればいい」というものではありません。むしろ、小学校6年間(あるいは中学校3年間)を通して、繰り返し、計画的に取り組むことが前提となっているのです。
実際、小学校学習指導要領やその解説には「児童の発達段階に応じた適切な指導を行うこと」や「各学年での重点的な取組に加えて、体系的・継続的に行うことの重要性」が示されています。ここが重要なポイントです。“扱ってもよい”ではなく、“扱わなければならない”のです。学習指導要領に書かれている内容は、すべての児童・生徒に対して確実に指導しなければならないものであり、それを発達段階に応じて繰り返し扱うことが求められています。
つまり、小学校でも中学校でも、性教育に関する内容は“その年限り”ではなく、児童・生徒の発達段階に応じて毎年継続的に扱わなければならない内容なのです。むしろ、それが学習指導要領の趣旨でもあるということを、ぜひ多くの先生方に共有したいところです。

「繰り返す」って、どういうこと?
ここで言う「繰り返し」というのは、決して毎年同じ教材をコピーして使うことではありません。子供たちは学年ごとに発達段階も違えば、クラスの雰囲気や悩みも変わっていきます。だからこそ、同じテーマでも、その年、その学年の子供たちに合わせて、少しずつ視点や深さを変えてアプローチすることが大切なのです。
例えば、小学校の学級活動でも示されている「よりよい人間関係の形成」「男女の違いを理解し協力すること」といったテーマ。低学年では「友達と仲良くするにはどうすればいいか」を中心に話すかもしれません。中学年になると、「男子と女子って違うところがあるけど、それって悪いこと? 面白いこと?」という気付きが生まれます。そして高学年では、ジェンダーや個人の多様性といったテーマにも踏み込めるようになっていきます。
中学校でも同様です。例えば「男女相互の理解と協力」というテーマは、中学1年生では「男の子と女の子の体や気持ちの違いってなに?」からスタートし、中学3年生では「性の多様性を認める」「個人の尊重とはなにか」といった、人権や社会性のある内容へと深まっていきます。
つまり、“同じテーマ”でも、子供たちの発達に合わせて学びを広げたり深めたりしていく──それが、学級活動における性教育の醍醐味であり、本質でもあるのです。

