「AIリテラシー」とは?【知っておきたい教育用語】
近年、「AIリテラシー」が学校教育の場で急速に注目を集めています。ChatGPTといった生成AIの普及や、社会のデジタル化・ネットワーク化の加速、情報の氾濫と偽情報リスクの高まりなど、子どもが将来直面する課題が変化してきているからです。文部科学省も「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)」を2024年12月に公表し、学校現場での生成AI活用の方向性と安全性・倫理性を踏まえた指針を示しています。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・渡辺秀貴
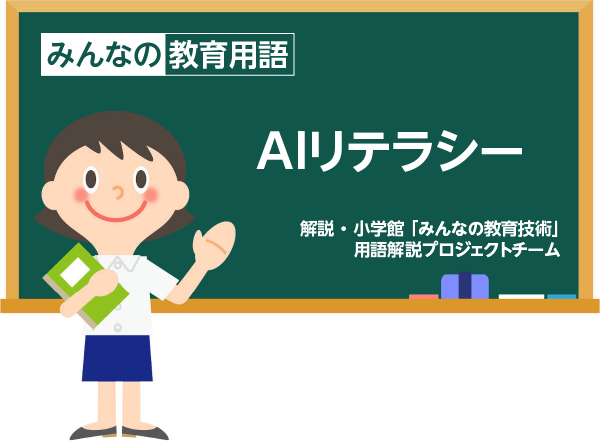
目次
「AIリテラシー」とは
【AIリテラシー】
生成AIの基本的な概念や仕組み、利用上の注意点を身につけ、効果的に活用することができる能力。
AIリテラシーについては、日本の公的文書で明確に一義的な単一定義が示されているわけではありません。内閣府や文部科学省などが共通して含めている要素を簡潔にすると上記のようになります。例えば、内閣府の「AI活用に向けたリスキリングと教育」の報告では、AIリテラシーは「AIの技術面を批判的に評価し、AIを効果的に活用(communicate and collaborate)することができる能力」とあり、「AIを理解し、活用し、監視し、批判的に考察できるスキル」を含むものとされています。
また文部科学省は、「初等中等教育段階における生成AIの利用に関するガイドライン(以下、生成AIの利活用ガイドライン)」で生成AIを含む情報技術を、「学習指導要領に示す資質・能力」の育成の観点から、「情報活用能力」を基盤とした、生成AIの仕組み・利点・限界・倫理的問題などを理解したうえでの教育利活用の検討を明示しています。
なぜ今、AIリテラシーが問題なのか
昨今の社会は、情報化やグローバル化に加え、AIをはじめとするテクノロジーの進展によって急速に変化しています。予測できない事象が増え、不確実性が高まるなかで、従来の定型的な技能だけでは社会を生き抜くことが難しくなってきています。そのため、思考力や判断力、表現力といった「資質・能力」の育成が学習指導要領においても重視されており、AI技術の進展を踏まえながら、生成AIなどを活用して、これらを育むことが求められていくことになりつつあります。
こうした動きを支える基盤として、「GIGAスクール構想」によって、小中学校における1人1台端末と高速・大容量通信ネットワークが整備されました。令和7年度には、端末の更新を予定する自治体も多く、その活用には生成AIの導入が意識され始めています。教育環境が急速に整備されるなかで、AIリテラシーをどう位置づけるかが大きな課題となっています。
一方で、AIの普及にはリスクも伴います。インターネットやSNS上には、フェイクニュースやディープフェイクなどの偽情報が氾濫しており、生成AIも虚偽の情報(ハルシネーション)を出力することがあります。さらに、個人情報の漏洩や著作権侵害といった問題も深刻です。こうしたリスクを理解し、適切に対応する姿勢を育むことは、学校教育における重要な役割の一つとなっています。
制度面でも動きが見られます。文部科学省は、「生成AIの利活用ガイドライン」をVer.1.0からVer.2.0に改訂し、技術革新やルール整備を踏まえて学校現場での実務的な指針を明確化しました。学習指導要領においては情報活用能力が基盤的な資質・能力として位置づけられ、高等学校では教科「情報」の必修化や内容の充実が進められています。
さらに、子どもたちの生活や学びの実態を見ても、生成AIは、すでに身近な存在となりつつあります。学習や遊び、将来の職業など、あらゆる場面でAIと関わる可能性がある子どもたちに対し、単に「使い方」を教えるだけでは不十分です。「どう使うか」「何が問題か」「どう判断するか」を学ぶ機会を教育のなかに組み込み、変化の激しい社会の担い手となる力を育むことが、AIリテラシー教育のめざすところだといえるでしょう。

