【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第72回】今どき教育事情・腑に落ちないあれこれ(その13) ─不登校、苛め過去最多・「良薬口に苦し(下の2)」─

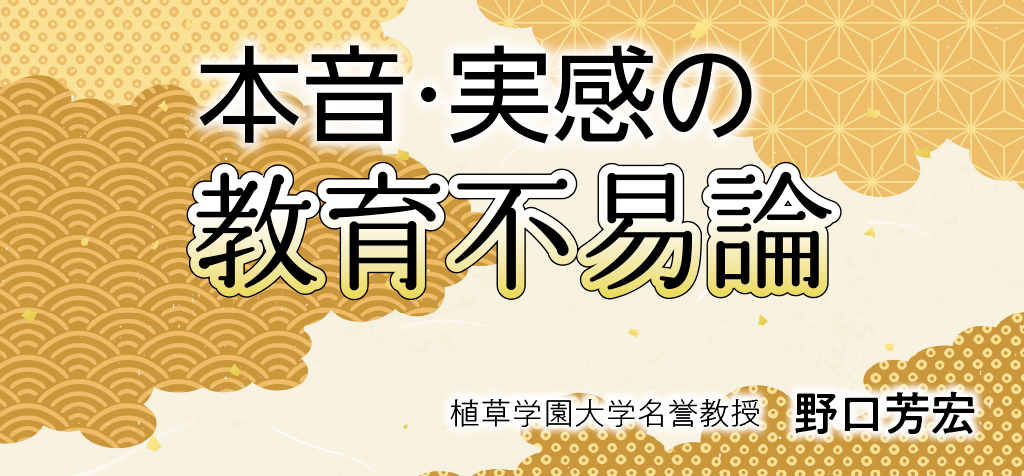
国語の授業名人として著名な野口芳宏先生が、65年以上にわたる実践の蓄積に基づき、不易の教育論を多様なテーマで綴る連載。昏迷を続ける教育界における様々な課題の根本的解決を目指すためには、日本固有の教育理念への回帰と分析が必要だ、と筆者は主張します。教育行政担当者、学校管理職に、ぜひ読んでいただきたい提言です。
執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、65年以上にわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。

目次
教育の混迷は、占領政策の後遺症 (承前)
前回までは、不登校と苛めについて、
8、被害者、受難者は子供なのだ
9、不登校、苛め、暴力は子供の告発
10、危ふきは、その元を尋ぬべし
という大筋を述べてきた。
10の「危ふきは、その元を尋ぬべし」は、これまで私が述べてきた「腑に落ちないあれこれ」の「不登校、苛め、暴力、過去最多」について、私なりの「根本的要因」を述べるのが趣旨である。私の本来の職務は、実践者としての考えに基づいて良き実践を具現することである。
これまでの歩みは、私なりに納得をしつつ進めてきたのだが、実践者としての立場を退いてから30年近くの時を経た現在の学校現場のありようを見ると、どうにも納得し難く思われる節が多く気掛りである。現職にある皆さんと、率直な話し合いをしてみたい。
──という訳で、私の「本音、実感、我がハート」に基づく直言にどうか、付き合って貰いたい。それは、私としては子供の「体を張った告発」に正対し、子供を正しい考えに立って守り、子供の「声なき声」に応えたいからである。
10、の①として、「敗戦と占領政策」を取り上げ、その「影響」を「吟味」すべく私論を述べた。要は、「占領政策の後遺症として今の混迷がある」ということである。「大和魂」という日本の精神的な宝が、見事に破壊されてしまったということだ。
教育基本法第一条「教育の目的」は、格式の高い名文だが、その冒頭に掲げた「人格の完成」とは程遠い国民性が育ってしまった。そこで、子供達は、不登校や、苛めや、暴力を伴う行動に出て、「今の教育のあり方だから、こんなことになるのだ」、「今の教育のあり方には誤りがある!」、「根本的に考え直して、本当に日本人らしい価値観を持てる教育をして欲しい」ということを訴え始めたのだ。
──というようなことを述べておいた。前回稿をお目通し願えれば有難い。
② 日本固有の教育理念への回帰、分析
「日本固有の教育理念」という言葉自体が、現在の教育界には受け入れ難いのではなかろうか。「それが不幸な戦争を引き起こし、大きな犠牲を生んだのだ」という短絡的な思考パターンが戦後80年をかけて見事に「現代の日本の教育理念」に摩り替えられてしまったからだ。むろん、敗戦に至るまでの日本が全て善であったなどと言うつもりはない。が「占領政策」の「日本国が、二度と立ち上がって世界の脅威にならぬように」するため、それまでの日本にあった美徳はことごとく破砕されてしまった感を抱く。私だけではあるまい。
次の文章に私は強い共感を覚える。筆者は大阪大学名誉教授、加地伸行先生である。
今日、個人主義を正義とするような議論が多い。しかし、個人主義は西洋の思想である。
「モラロジー、道徳教育」(No.146巻頭)より
東北アジアは家族主義なのである。日本人は、憲法という個人主義の仮面を着けているが、その仮面を剥げば、家族主義である。
家族主義と個人主義との両者に、上下の関係はない。この理解が重要である。欧米思想尊崇派は個人主義が上と誤解している。
さて、その家族主義の根本は、孝である。(中略)祖先を祭ること(祖先祭祀)が第一の孝である。次いで、現実生活において子が親を敬愛すること、これが第二の孝である。さらに子孫があることが第三の孝。それは、宗教・道徳・生活の一体化である。そういう孝の全体像を小学校から少しずつ教育して欲しいと願っている。
重厚な内容である。「家族主義」が、曽ての日本人の「固有の教育理念」の一つであり、それはまさに美徳と呼ぶにふさわしい。今は「学級崩壊」「家庭崩壊」などという言葉が、格別の危機感も持たずに口にされるようになっている。恐ろしいことだ。
私は、「孝」一つを、徹底して教えることができ、子供がそれを身につけたならば、不登校も、苛めも、暴力も大半が解消され、打開の道が拓け、「人格」を大切にする子供が育つに違いないと確信している。
なぜならば、「孝」の神髄は、「親を安心させること」であり、「親に心配をかけないこと」にあるからだ。
教育基本法の第一条「教育の目的」の冒頭は「教育は人格の完成を目指し」と始まる。これが、教育の第一義であり、全ての教育の営みは「人格の完成を目指し」て行わなければならないのである。
だが、「人格の完成を目指す」とは、具体的にどういうことなのか、それは書かれていない。抽象的かつ理念的な表現である。にもかかわらず、「不登校、苛め、暴力」は「人格の完成」には遠いことだけは誰にとっても異論はあるまい。
その点「教育勅語」は、12の徳に絞り込んで分かり易かった。分かり易いということは、具体的で実行可能ということである。
「父母に孝に」「兄弟に友に」「夫婦相和し」などとまことに具体的で分かり易い。
教育勅語は、昭和23年6月、衆参両院で失効宣言が採択され、日本の教育への影響が消えた。連合国の占領の第一に消されてもおかしくないほど、日本の教育の在り方に大きな指標となったものだ。だが、GHQは、この廃絶を命ずることはなかった。一言で言えば、その内容に非がないのみならず、どこをとっても見事な理念だったからである。GHQは、口頭をもって「自発的、自主的に、失効宣言をするように」と促し、消滅に導いたらしい。
法的には国会で決めたことだから、復活には国会の採決が必要になるから、これはまず絶対に望めまい。
一つの国家が、「億兆心を一にして、世々その美を済(な)せるは、此れ我が国体の精華にして」と謳い上げられた、自国に対する自信と自負を私は誇りに思う。今も、これからも、日本が一つにまとまることは、まず望めまい。「個人主義」「自分中心」「自主性」「主体性」「個性」「多様性」が、まことしやかな憧れとして祀り上げられているからだ。
大和魂などという言葉は、今の若者にはせせら笑いのネタになるくらいの言葉かもしれないが、卒寿の生き残りの私には、誇らしさを伴って受けとめられる。「武士道」もまた同様である。大和魂も、武士道も、そして総じて「剣道」「茶道」「華道」「柔道」など「道」という言葉でくくられる理念は「人として守るべき条理」である。「人格の完成を目指し」に直結する理念である。
現代の日本人は、概して「弱くなった」と思われる。耐える。我慢する。受け入れる。──というような、より高いレベルに己れを向上、深化させていく気概に乏しいように思われるのだ。
不登校、苛め、暴力など、子供の「いま時三悪」も、結局は「弱さ」が生み出している現象だとも言えるのではないか。「ちょっと待てよ」という心のブレーキが利かなくなっているのではないか。
不登校の「弱さ」は頷けるとしても、「苛め」は、「弱さ」というのは頷けない、という考えもあるだろうが、それは皮相の見方であろう。「克己」という、「己に勝つ」という最も困難な、本物の勇気、胆力が弱いのである。そもそも、世の中も人生も、自分の思うままになんかなる訳がない。自らの思いをコントロールできる「自律」の力が弱くなっているから、悪事に決まっている弱い者苛めに走ってしまうのだ。「弱い者を苛めて困らせる」なんてのは、「勝利」でも何でもない。下らない卑劣、愚挙以外の何物でもない。
日本人が誇りとした大和魂や武士道は、もっと崇高であり、人間の道に適ったものである。それは、まさに「我が皇祖皇宗の遺訓」であり、「子孫臣民の倶に遵守すべき所」であり、「之を古今に通じて謬(あやま)らず」、「之を中外(ちゅうがい)に施して悖(もと)ら」ざる、堂々と胸を張って公言できる理念であった。日本人としての誇りは、工業製品がメイドイン・ジャパンとして、世界から高い評価を受けてもいた。
このような、日本固有の誇るべき教育理念や美徳が、敗戦によって、あるいは占領政策によって、あるいは欧米崇拝、欧米拝跪のコンプレックスによって、見るも無残な様相を呈するに至ってしまった。こういう考え方は、ともすると右翼呼ばわり、逆コース呼ばわりをされ、声を潜めざるを得ない世相がこの世を掩っているように思えてならない。そのことが、現今の昏迷を招いているのだと私は考える。
以上が②の「日本固有の教育理念への回帰、分析」を訴えたいと考える理由である。
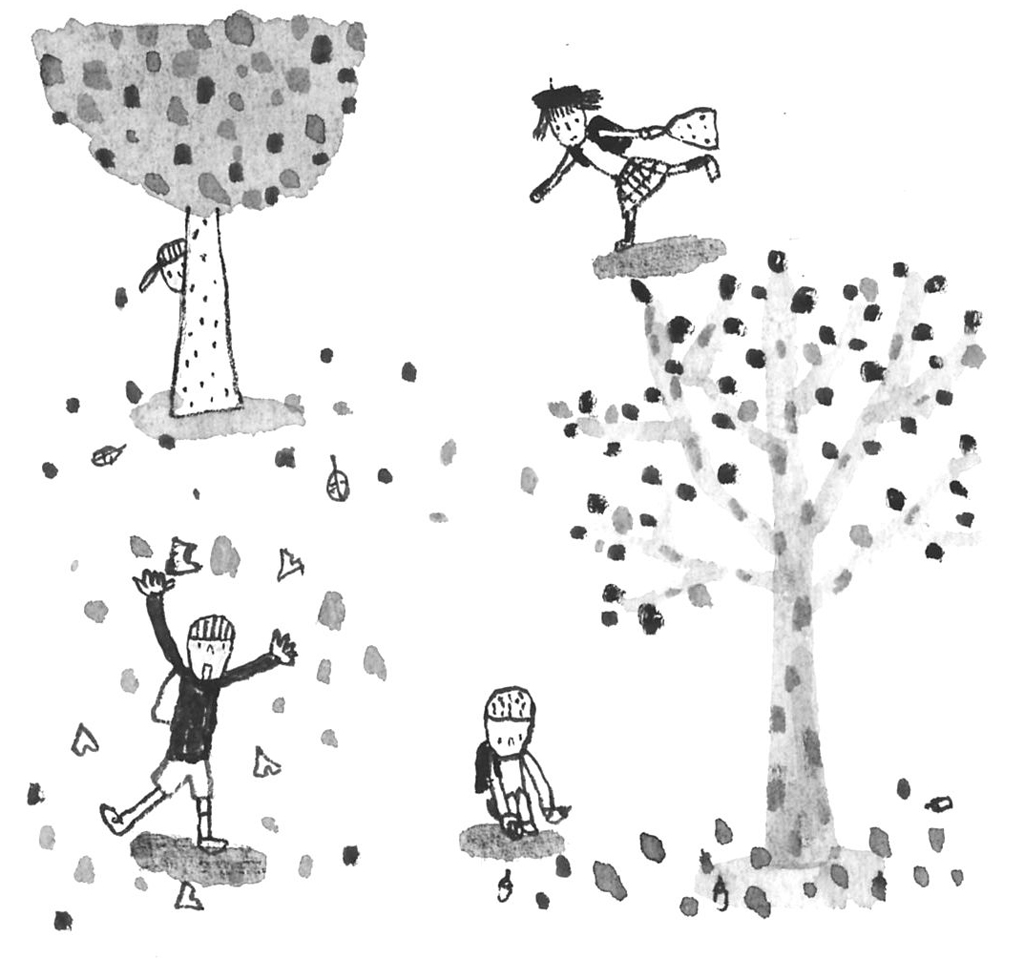
③ 西欧文化への拝跪の功罪の吟味
今回を以て「不登校、苛め過去最多・良薬口に苦し」について5回に亘った稿をひとまず閉じたいと考えている。その稿がこの③であるが、すでに述べてきた内容の中にこれから述べようとしていることとの重なりが出てこようと思われる。
10年程前の一時期、アクティブ・ラーニングという用語が大変な流行を生んだことがある。現行の指導要領のキーワードになるだろうと目されていたが、改訂の直前になって、「主体的・対話的で深い学び」という日本語に置き換えられることになった。
その詳細な経緯については分からないがこれは、典型的な教育潮流の一つだと思われる。とにかく、カタカナで表記される外来語が教育界ではもてはやされることが多い。これは、そのまま、日本の教育よりも欧米のそれの方が正しく、望ましく、日本の教育はそれらを学び、取り入れないと遅れを取る、という「思い込み」があることの証拠ではないか。「遅れを取る」ような古い教育では駄目で、絶えず「新しい」教育のあり方を目指さなくてはいけないのだ、という考え方が、教育をリードする層の(それは多く、研究者や官僚であることが多いのだが──)人々にあるのではないか。基本的には、我が国の現状と先行きへの不安が前提になっているのではないか。
30年余り前のことだが、「長く、学校のあり方に子供を合わせる時代が続いてきた。しかし、これからは、子供達に学校が合わせる時代になる。」という発言を聞き、大きく考えを揺さぶられたことがある。ナルホド!!と、私は、まさに揺さぶられたのだった。子供を主体とした学校教育の改革という「新しさ」が、私をとりこにしたとも言える。
そして、今思う。「それは間違いだ!」──と。子供の本質は「無知、未熟、未完」なのであって、それを、そのままにすることなく、教え、正し、導き、引き上げていくのが教育の本来である。その本質は不変、不動、不易なのだ。
いろいろの考えが出されるのは悪いことではないが、「新しさ」は、本質的、根本的に「時によって裁かれていない」つまり、正しいのか、良いのか、効果的なのか、子供や国民や国家を幸せに導けるのか、という「先行き」は実証されてはいないことなのだ。つまり「先行き不透明」なのだ。再々述べてきたように、「基礎教育」はむしろ「新しさ」よりも、時の裁きに耐えて今に生きる「古典」に学び、「古典」への回帰の方が、肝要なのではなかろうか。

イラスト/すがわらけいこ 写真/櫻井智雄

