子供が主役の運動会とは?【伸びる教師 伸びない教師 第58回】
- 連載
- 伸びる教師 伸びない教師

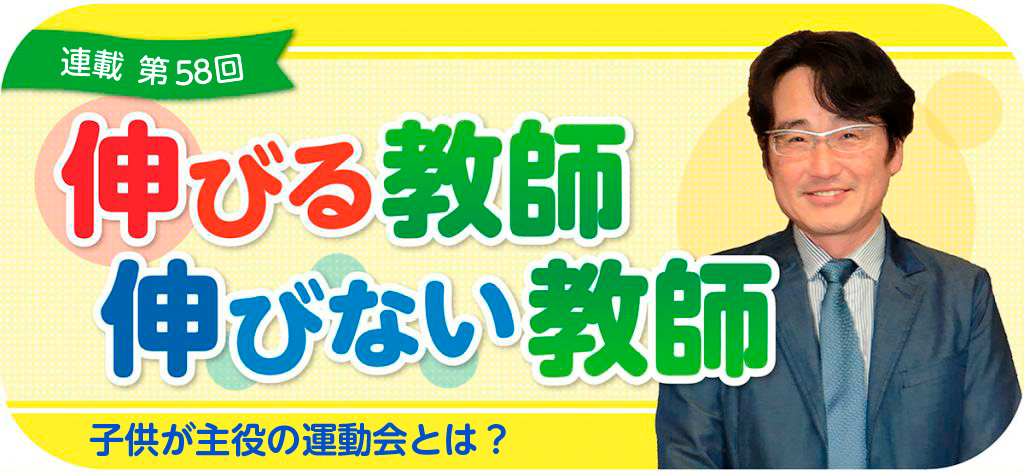
豊富な経験によって培った視点で捉えた、伸びる教師と伸びない教師の違いを具体的な場面を通してお届けする人気連載。今回のテーマは、「子供が主役の運動会とは?」です。運動会は、見せる運動会から楽しむ運動会、子供が主役の運動会に変化しています。子供が主役に見えていても果たしてそうでしょうか。子供が主役の運動会にするにはどうすればよいのかという話をお届けします。
執筆
平塚昭仁(ひらつか・あきひと)
栃木県公立小学校校長。
2008年に体育科教科担任として宇都宮大学教育学部附属小学校に赴任。体育方法研究会会長。運動が苦手な子も体育が好きになる授業づくりに取り組む。2018年度から2年間、同校副校長を務める。2020年度から現職。主著『新任教師のしごと 体育科授業の基礎基本』(小学館)。
目次
運動会は地域あげての大イベントだった
私が教員になったばかりの頃(35年ほど前)の運動会は、行進で校庭を1周してから開会式の隊形に並んだものでした。指先まで伸ばした腕を肩まで高く上げて行進できるよう4月の体育は集団行動を徹底的に指導しました。朝礼台には校長先生が立っていて、その前を通り過ぎるときは、校長先生に向かって「かしら右」をさせていたことを思い出します。競技の内容も、騎馬戦、棒倒しなど軍事色が強いものも残っていました。
地域をあげての行事だったので屋台が校庭に立ち並んでおり、昼休みには子供たちがかき氷を食べたりおもちゃを買ったりしていました。たくさんの人が集まるため町内ごとに座るところが決まっていました。また、スポーツ観戦の要素が強く、最後の紅白リレーは、自分の子供が出ていなくても大きな盛り上がりを見せました。とにかく、運動会は地域をあげての大きなイベントだったのです。そのため、人に見られて恥ずかしくない演技ができるよう、練習から教師主導で厳しく指導しました。当時は、「見せる運動会」といったイメージが自分の中にありました。
楽しむ運動会に
それから35年、応援歌をはやりの歌の替え歌にしたり、開閉会式の司会や演技の実況を子供たちにさせたりするなど、各学校で少しずつ子供たちの活躍の場が増えてきました。いつの間にか、行進、「かしら右」をしている学校は聞かなくなりました。競技の内容も、危険が伴う騎馬戦、棒倒しなどは避け、レクリエーション的要素の強いものに変わっていきました。「見せる運動会」から「楽しむ運動会」に変わってきたと自分では思っています。
こうした子供たちが中心となって活躍する運動会を「子供が主役の運動会」と呼ぶ人もいました。
ただ、自分の中では「本当にそうだろうか」という思いがありました。一見すると子供たちが主体的に活動しているように見えますが、毎年行うことが決まっていて、子供たちはその仕事をこなすだけです。例えば、係の仕事では台本が用意されていたりやることが決まっていたり、そこに子供たちの発想が入り込む余地はありません。このほうが運営はスムーズにいきますが、子供が主役とは言えません。


