食べることは生きる源「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」きっとおもしろい発見がある! #28

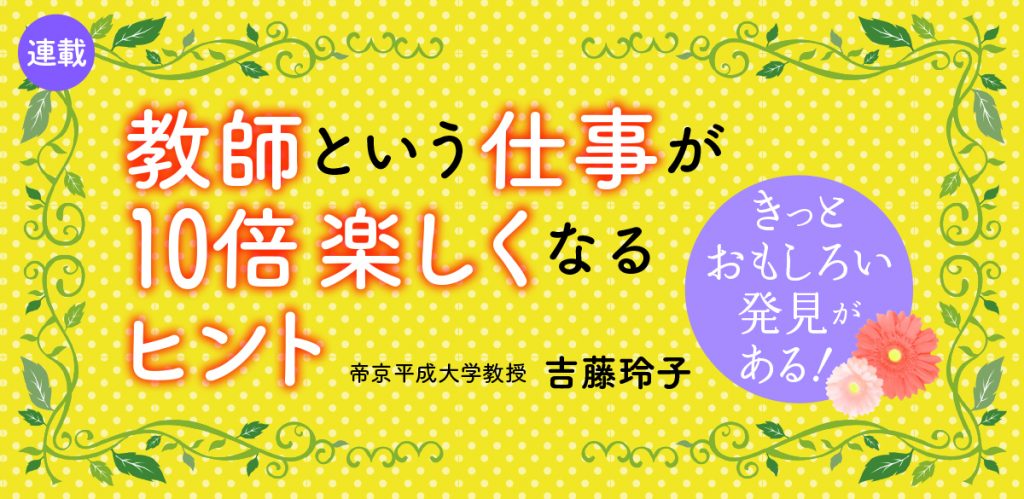
「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」の28回目のテーマは、「食べることは生きる源」です。最近の子供の食事事情やアレルギー、食育、給食、ブックメニューなど、食についてのメッセージ。今一度、食生活を見直すための様々なヒントをお届けします。

執筆/吉藤玲子(よしふじれいこ)
帝京平成大学教授。1961年、東京都生まれ。日本女子大学卒業後、小学校教員・校長としての経歴を含め、38年間、東京都の教育活動に携わる。専門は社会科教育。学級経営の傍ら、文部科学省「中央教育審議会教育課程部社会科」審議員等、様々な委員を兼務。校長になってからは、女性初の全国小学校社会科研究協議会会長、東京都小学校社会科研究会会長職を担う。2022年から現職。現在、小学校の教員を目指す学生を教えている。学校経営、社会科に関わる文献等著書多数。
目次
食生活について考えよう!
小学校入学前の就学時健康診断の面接の際に食べ物のアレルギーについて聞きますが、年々配慮が必要な子供が増えてきているように感じます。子供たちが食べられない食物もいろいろ詳細になってきていて、栄養士の方や給食に関わる主事さん、先生たちはご苦労されていると思います。移動教室に出かけても食事には配慮が必要です。90歳を過ぎている私の母は、戦時中、本当に食べ物がなくて、戦争が終わってお腹いっぱい食べられるようになって本当にうれしかったと話します。今はこの食べることが学校現場において課題になることがあります。今日は食生活の重要性について考えてみたいと思います。

最近の子供たちの食事事情
共働きの家庭が増え、子供が最後に家を出てくる家庭もあるのはないでしょうか。私の家もそうでした。小学生の娘が最後に家の鍵をかけて学校へ行っていました。子供たちは朝ごはんをきちんと食べているでしょうか。具合が悪くて保健室で休んでいるときに養護教諭が聞いてみると、朝ごはんを食べないで学校に来て気分が悪くなってしまったなどの事例が多くあります。今の若いお父さん、お母さんは自分たちもインスタントのものを多く食べ、外食などで育った世代ではないでしょうか。
「まごわやさしい」【ま:豆類、ご:ゴマ類、ナッツ類、わ:わかめ(海藻類)、や:野菜、さ:魚、し:しいたけ(キノコ類)、い:いも類】の合言葉に栄養を考えた食事が必要といっても忙しくてなかなか用意できない家庭も多いかと思います。私もこの合言葉を母から教わっていてもなかなかバランスのよい食事の用意はできませんでした。私の子供たちは、小学校のときの給食が大好きで、給食が命でした。給食のおかげで大きくなったと言っています。
食事は好き嫌いなく食べるのが一番よいのですが、学校の給食の時間に、残さずすべて食べるなどという指導を今はしません。その子のレベルでその子が食べられる分でよいという方針になってきています。ですから家庭でも好き嫌いを許してしまうと、子供たちは、嫌いな食べ物は本当に食べなくなってしまいます。また、中学校受験の準備が始まる4年生頃からは、塾で夜遅くまで勉強して、それから夕飯になるので、不規則な食生活になりがちな子供たちも多くいます。食事は生活の基本だということが分かっていても、今の子供たちを取り巻く現状は難しいものがあります。
アレルギー対応
入学前だけでなく、移動教室などに行くときもアレルギーがある子供に対応する特別食は当たり前になってきました。もし、引率する担任になって、めんどくさいと感じることがあったら、覚えておいてください。きちんとチェックしておかないと大変なことになります。こちらがきちんとチェックしておいても食品会社の間違いなどもあり、油断ができません。
私の経験で、牛乳アレルギーの子供がいたのですが、食品会社が用意したマッシュポテト用の食材粉末にスキムミルクが入っていて、気分が悪くなってしまったことがありました。幸い、初期の段階で気付いたので大事にならずにすみましたが、そのときは本当に焦りました。「牛乳を飲んでいないのになんで?」と思い、養護教諭、栄養士と細かくチェックして分かりました。
似たような例で、私が知っている学校で移動教室のときに食品会社が用意したお弁当の中のおにぎりにゴマがふってあって、ゴマアレルギーの子供が間違って食べてしまい発作を起こしたということがあります。ハイキングの途中だったので大変だったのですが、こちらも幸い子供本人がエピペンを持っていてすぐに対応できたということでした。しかし、その学校の校長は本当に焦ったと話していました。昨今の子供たちのアレルギー対応には教員は細心の注意をして当たらなくてはいけません。決して面倒だと思わずに可能な限りの情報を集めておくことをおすすめします。
食育とは
今は、栄養士でも栄養教諭の免許を持っている人が増え、食育の授業をしてくれることが増えました。食育とは、子供たちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることができるように育てることです。子供たちは栄養のバランスを教えてもらい、食べ物を好き嫌いしないで栄養をバランスよく摂ることを学びます。
子供の頃に身に付いた食習慣を大人になってから改めることはとても困難です。生活習慣病の予防などは、子供の頃の食生活からと言われています。日々の授業で忙しい担任の先生方も、ぜひ栄養士さんと協力して子供の食生活チェックを行ってみてください。しっかりしているなあと思った子供が滅茶苦茶な食生活をしていたり、日々外食が多い家庭であったりすることがあると思います。
家庭の事情にはあまり踏み込めませんが、バランスのよい食事が必要なことを子供に意識させることはできます。また、可能なら保護者会などで学年全体の保護者に向けて栄養教諭に食育の話をしてもらってもよいかもしれません。今の時代、保護者も食事について関心をもつことが大切です。
給食のすばらしさ
給食を食べるときや食べ終わったときに、どこの学校でもきちんとあいさつをします。これが日本の教育のすばらしさです。家庭などでは1人で夕飯や朝ごはんを食べている子供もいるでしょう。みんなと一緒に食べる食事はおいしいものです。コロナ禍では、前向きで何もしゃべらずに食べていましたが、今は和気あいあいと楽しく食べることができます。子供たちは給食が大好きです。しかし、給食のすばらしさには気付いていないと思います。栄養士がみんなの栄養を考え、少ない予算の中でやりくりして、安全な食事を提供してくれていること、給食室では早朝からみんながおいしく食べられるように用意をしてくれていることなどは、ぜひ子供たちに教えてほしいことです。
2023年に小学校3、4年生の夏休みの読書の課題図書に選ばれた『給食室のいちにち』(文:大塚菜生、絵:イシヤマアズサ、少年写真新聞社)という絵本は、給食について分かりやすくまとめられています。教室に届けられる前、食器を返した後の給食室について子供たちに教えてほしいです。もしかしたら、給食主事さんたちの苦労を知って、残さず給食を食べる子供が増えるかもしれません。
ブックメニューや行事食
ブックメニューとは、絵本やお話に出てくる食事を給食に取り入れることです。学校の協力体制にもよりますが、子供たちには大好評です。もし、司書教諭の資格を持っていて図書館指導などに当たっている先生がいたら、栄養士の協力を得て試みてはどうでしょうか。
自分の学校でパンを焼くことができる学校があって『どんぐりむらのぱんやさん』(作・絵:なかやみわ、Gakken)の話の中に出てくる「どんぐりパン」を実際に焼いて子供たちに提供したところ大好評だったようです。『新装版 おせちのおしょうがつ』(作:ねぎしれいこ、絵:吉田朋子、世界文化社)という絵本はおせち料理について子供たちにその意味を分かりやすく楽しく説明しています。その絵本を全校集会などで読んだあと、1月の給食のメニューに黒豆やいもきんとんなどが出れば、子供たちはもう一度お正月を繰り返すような気持ちになり、日本のおせち料理について楽しく学べます。
私が勤務していた学校では、行事や歴史的な出来事に合わせて給食のメニューを出していました。七夕集会で七夕の話をした後、その日の給食は星形の飾りのついたゼリーや天の川をイメージしたそうめんなどでした。東京大空襲の話を全校朝会などで知った後は、当時の食事を思い起こさせるすいとんの入ったメニューでした。このように出来事と関連付けて給食を楽しく食べるのもよいことだと思います。
TVをつければグルメ番組が多いのですが、忙しい日々の中で子供も大人も食べることになかなか向き合うことができません。学校の給食をヒントに、食生活を見直して健康な日々を過ごすことができればと思います。
構成/浅原孝子 イラスト/有田リリコ

