データ活用は教師の負担の大幅な軽減につながる 【次期学習指導要領「改訂への道」#25】
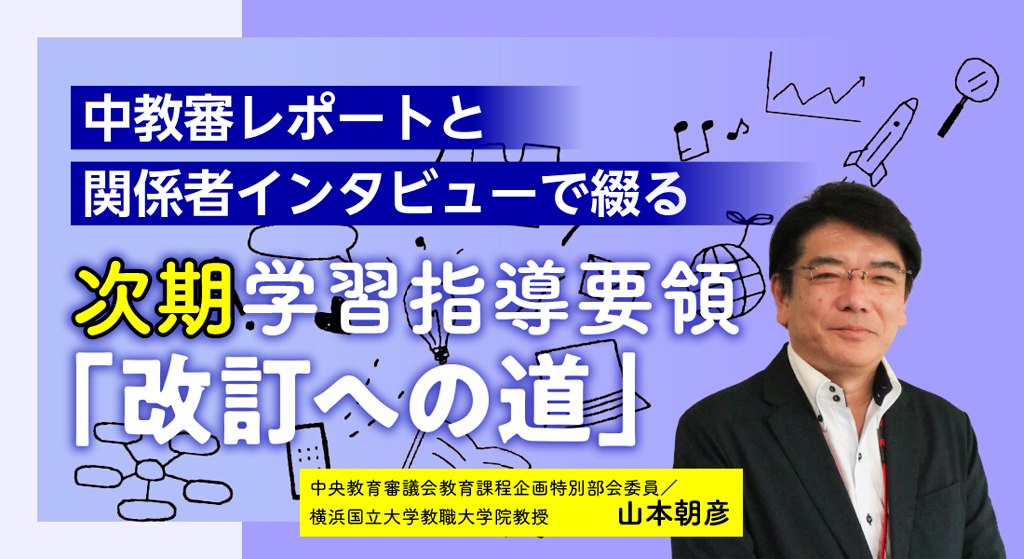
前回は、教育課程企画特別部会(以下、特別部会)の委員である、山本朝彦教授(横浜国立大学大学院・同大学附属横浜小学校校長)に、「探究の学び」とデジタル活用を中心にお話を伺いました。
今回は、「時間」の問題や「教科の探究」、さらに「教科書」などについてお話を伺っていきます。
目次
データ活用は保護者へ説明をする場合にも役立つ
前回、データ活用の話にも触れましたが、それは教師の負担の大幅な軽減にもつながると思っています。
今、教師にとって何が大きな負担かと聞かれれば、入試の内申書の作成や、通知表の作成といったことがあがってくるでしょう。これは前からもある作業ですが、今では、通知表も1文字間違うだけで、「誤記載」「記者発表」となってしまいます。教師は子どものために行う作業は大変とは思わないでしょうが、間違えることは許されない、極限まで精度をあげてミスしたら責任が及ぶことには、相当の負担を感じていると思います。子どもの成長の助けになることが目的であったのに、間違えてはいけないことが目的になってしまっている。それが、教師の時間的・精神的な負担になっていると思います。
しかも、それは(先にも触れたような)子どもの成長のある瞬間を切り取った評価にすぎません。これからは情報端末を活用して、(学習や心情、体力など様々な観点で)子供の学びの履歴が残り、病院のカルテのようになれば、受験に活用するときも、受験生を受け入れる側が、その履歴の中から必要な情報だけ取り出して活用すればよいのです。それが実現できれば、教師の最大の働き方改革になると思います。
もう一つ、保護者へ説明をする場合にも役立つと考えています。例えば、技能教科の成績では、「なぜうちの子はB(あるいはC)なのか?」と言われることもあるでしょう。そのときに、図工ならその期間に制作した作品をふり返ってみたり、B基準となる例を示したりしながら説明をすれば、学校での様子は伝わるのではないでしょうか。あるいは体育なら、跳び箱を跳んでいる動画を示しながら話をすれば、理解してもらえるかもしれません。
本当に保護者が知りたいのは、子供の具体的な日々の様子と子供の成長に向けて先生は何をしてくれたのかということでしょう。それであれば、「お子さんの様子はこうです」「改善に向けて学校ではこのように取り組んできました」「もし可能ならご家庭でもこういう取組をしてみてください」と言うことができれば、理解される可能性が高まります。そういう意味でも、探究の基盤としての「学びの履歴」を、「探究の学び」でも教科学習でもきちんと残していくことが、評価のあり方を、より子供の成長に資するものに変えてくれるとともに、教師の負担も減らしてくれると考えています。
「探究の学び」を核にしつつ各教科も探究的にできれば、時間削減にもつながる
今回の改訂の中で「働き方改革」という視点からすると、全体の内容量や時間を減らすという話になるだろうと思いますが、今までの議論の中では授業時間を5分短縮して午前中に5時間行い、午後は外部の人材も活用して「探究の学び」などに使うような事例が示されています。
各教科学習と「探究の学び」が往還して、お互いの学びを深めていくような柔軟なカリキュラムデザインが求められているのです。
教科学習も探究的に学ぶと、子供たちの興味・関心はどんどん学習指導要領の内容を超えていきます。例えば、理科で5年生が植物の葉からの蒸散について学習するとき、葉にビニール袋をかぶせておくと、翌日には水滴が付いていて、「葉から蒸散しているんだね」と気付きます。しかし、子供たちの興味や関心はそこで止まらず、必ず「葉のどこから出ているんだろう?」となるし、「顕微鏡で見てみたい」となります。ただし、それは中学校の学習内容になるため、「ここから先は中学校の生物で学ぶことだから…」となってしまうことはなかったでしょうか。しかし、それでは子供の探究の芽を摘んでしまうことになります。
あるいは、4年生の社会科で「ゴミ単元」の学習をやっているとき、地域のゴミステーションを見に行ったり、ゴミ収集車の職員に会ったりして、最終的にゴミが処分場に送られていく過程を調べていきます。教科書ではそこで終わりなのですが、子供たちは本気で追究すると、「その先、どうなるんだろうか?」と気になり始め、「分別したものって本当に別の製品になっているのかな?」などと問いを持ち始めます。しかし、それは4年生の社会科の内容ではなくなるので、「そこから先は、自分で調べてごらん」と言って、単元を終えてしまうことはないでしょうか。
私が以前、横浜市の小学校で授業していたとき、総合的な学習の時間を活用して「ぜひ、調べてみたい!」となり、子供たちが調べたら、再生工場に大量のペットボトルを固めた巨大なプラスチックのブロックが山積みになっている様子にたどり着きました。それは、処理が追い付かずに積んであるもので、子供たちは「再生すると言って、分別したけど、こんなに積んであってどうなるのだろう?」と、さらに探究が続いていき、製品化するには技術やコストがかかることにも気付いていきました。このように「探究の学び」で火が着いた子供たちの関心は途切れることがなく、子供は教師や大人の予想や計画を軽々と超えて学びます。各教科で探究的に学べば、他教科や「探究の学び」との接点も大きくなるとともに、学びもつながり拡張し、深まっていくのではないでしょうか。
このように各教科が探究的に行われると、「探究の学び」を核にして、教科学習も一緒にやれることがたくさんあると思います。重なる部分は、両方でやらずにどちらか一方で学べばよいわけで、時間の削減にもつながります。
さらに、研究開発校のような取組の枠を全国に広げてもらえれば、1単位時間を40分にするなど柔軟なカリキュラムデザインに挑戦し、その余白の時間で教材研究をしたり、児童生徒理解のミーティングを行ったりできる可能性が出てきました。多くの教師が「やってみよう」と思える、試行錯誤やチャレンジを期待しています。

