子供を助けるのは子供だ 【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #38】
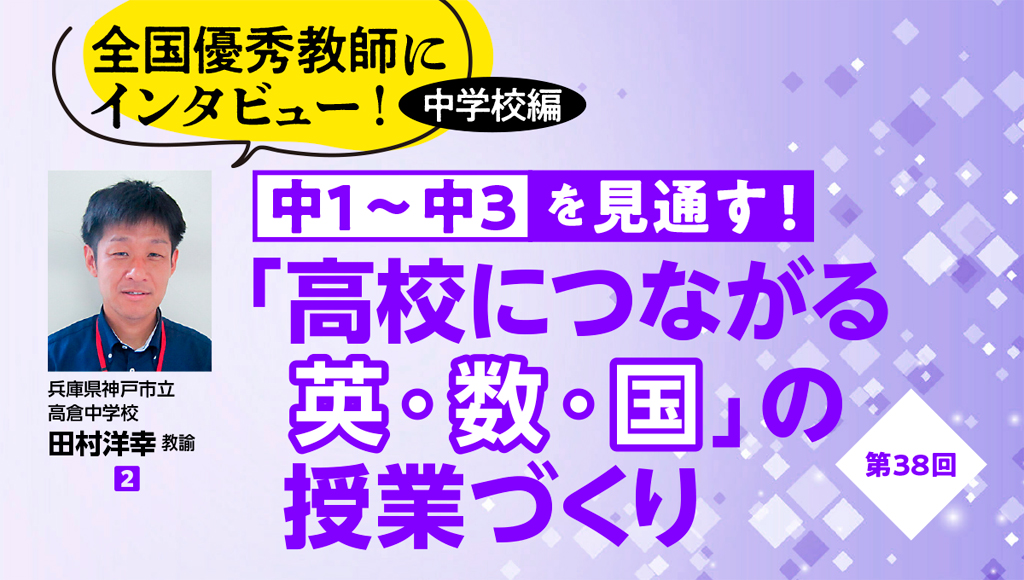
前回は、兵庫県・神戸市中学校実践研修数学グループの幹事長を務める、神戸市立高倉中学校・田村洋幸教諭の授業づくりの考え方を象徴する授業事例を紹介しました。今回は、前回紹介した、1年生の「文字式」単元の授業に表れている、対話場面を多く設定した授業づくりの考え方を中心に、田村教諭にお話を伺っていきます。

田村洋幸教諭
目次
課題に対しての探究心や、友達と学び合えるような関係性を築く
まず、前回紹介した授業が非常に対話を重視した構成になっていることについて尋ねると、田村教諭は次のように説明します。
「数学の答えは(中学校段階では)基本的に1つですが、多様なアプローチの仕方や考え方があります。そのような多様な考え方を、対話を通して友達同士で共有したり、深め合ったりすると共に、そのような関係性について数学を通して養えるような学びをしていきたいと私は思っています。
もちろん数学という教科を通して、計算ができるとか、数学的な見方・考え方ができるという力を養うことは当然大事なことです。しかし、それに加えて、その授業や単元を通して1つの課題に対して深く追究していく探究心や、その学習過程で友達とつながり合って、学び合えるような関係性を築いていけるような力も育みたいと思っています。
ですから子供同士の対話で、『この考え方にはこういう意図があり、こんな根拠があって、ここをこんなふうにしたらこんな考え方が出てきた』というように、自身の考えを表現したり、他者の考えを聞いたりし、互いの考えを共有させる場面を多くもつようにしています。そうした学習過程を通して、ペアやグループの子供たちで考え方や説明の仕方をブラッシュアップしていき、最終的にはふり返りの場面で、すべての子供が自分なりの説明できるような学習を大事にしているのです。特に、節や章の終わりにはこのような学習を設定したいと考えています。
加えて授業の最後には(前回も触れた通り)可能な限り、学習したことをふり返る場面を設定し、学習過程を整理して言語化し、より確かな知識、あるいは概念として定着を図りたいと考えています。
対話を通して学ぶことを大事にしていると話しましたが、当然、知識や技能などでは、しっかり説明する必要がある内容もありますから、考え方や概念の基本的なところは、私からていねいに話をして理解を図ります。ただし、そのような学習でも、ペアやグループで理解状況を説明し合う場面を1時間の授業中に何回かもちますし、授業のふり返りでも、『今日はどんなことが分かった? 話し合ってみて』と子供同士で話し合うことで確認させていくようにもしています。
ただし対話の場面が、ただのおしゃべりや漠然とした会話にならないようにしなければならないと思います。ですから、『この問題を解決する考え方について、事前問題の3を意識して共有してみようか』などと、問題に応じてより具体的で、子供たちが分かりやすく共有できるような投げかけ方をしています」
小学校では、数学的な言葉を使って説明させるため、「〜という言葉を使って説明しよう」と、具体的な言葉を指示して対話させるような取組もありますが、そのような方法は取らないと田村教諭は話します。
「この言葉を使ってと言うと、それを使うこと自体が目的化してしまいます。そうではなく、事前の学習を意識することで必要な知識や概念を使って説明できるよう意図しています」

