「学校の当たり前」を見直す 徹底した個への関心|インクルーシブ教育を実現するために、今私たちができること #14

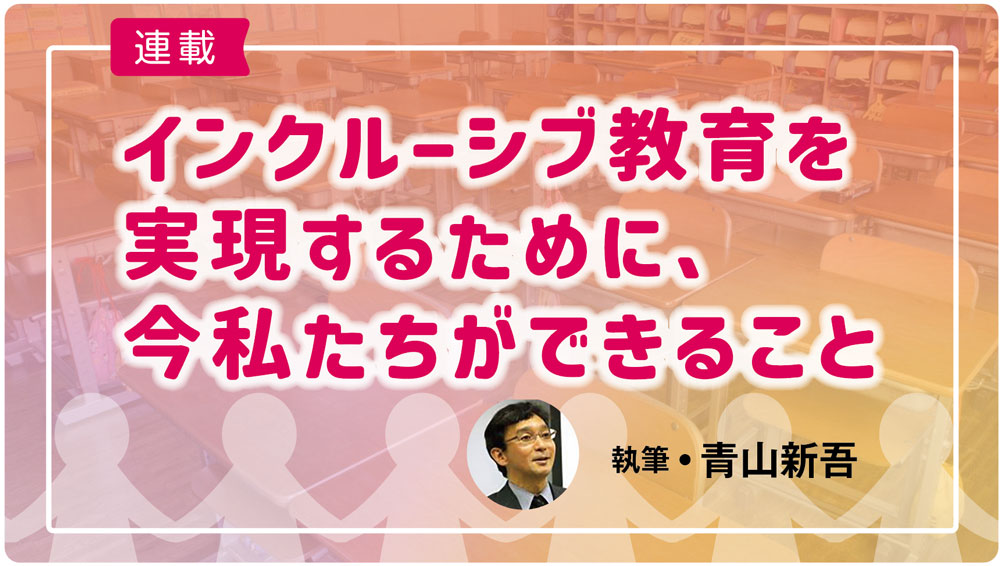
「インクルーシブ教育」を通常学級で実現するためには、どうすればよいのでしょうか? インクルーシブ教育の研究に取り組む青山新吾先生が、現場の先生方の悩みや喜びに寄り添いながら、インクルーシブ教育を実現するために学級担任ができること、すべきことについて解説します。今回は、学校の当たり前を見直すという視点から考えていきます。
執筆/ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科准教授・インクルーシブ教育研究センター長・青山新吾
目次
インクルーシブ教育とは何か
野口晃菜(2022年)は、「インクルーシブ教育」の対象は虐待をされている子ども、外国にルーツのある子ども、貧困状況にある子ども、性的マイノリティの子ども、障害や病気のある子ども、不登校の子どもなどのマイノリティ属性の子どもを含むすべての子どもたちであるとしています。そして、すべての子どもたちを包摂する教育を目指すプロセスがインクルーシブ教育であり、そのためには、これまでの教育システムを変えていくことが必要だとしています。本連載では、インクルーシブ教育を実現するためには、通常学級の教育が変わっていくことが求められているという前提に立っています。
しかし、そう簡単に教育システムが変わり、通常学級の教育が変化するとも思えません。では、今何もできないの?……と悲しくなってしまいます。でも、本当に今私たちにできることは何もないのでしょうか。そのようなことはありません。そこで、これからこの連載を通して、インクルーシブ教育を進めるために、今私たち一人一人ができることを探っていこうと思います。
「学校の当たり前」には何があるか

ある学校の前を通りかかったときのことです。たくさんの子どもたちと先生と思える大人が、校門の前に並んで、「おはようございます!」と大きな声であいさつをしています。集団でかなり大きな声を出してのあいさつです。自転車で通りかかった僕にも「おはようございます!」とあいさつをしてくれました。
日本の学校では、よく見られる光景でしょう。この光景をどのように見て、何を考えるかは、人によって違うと思います。
例えば、あいさつを、「大きな声を出してするものだ」と考えれば、あいさつ運動は好ましい光景に映るかもしれません。また、「規律を大切にする」と考えれば、あいさつ運動はきっちりした子どもたちの様子であると映るかもしれません。そして、「大きな声で規律正しくあいさつできる子どもが望ましい」と考えれば、あいさつ運動に積極的に参加し活動できる子どもはよい子だと評価されるようにも思えます。
まさに、あいさつ運動は、日本の「学校の当たり前」の1つであると言ってよいでしょう。

