多様性問題、現行学習指導要領の路線維持、デジタルが今回の審議課題 【中教審レポートと関係者インタビューで綴る 次期学習指導要領「改訂への道」#06】
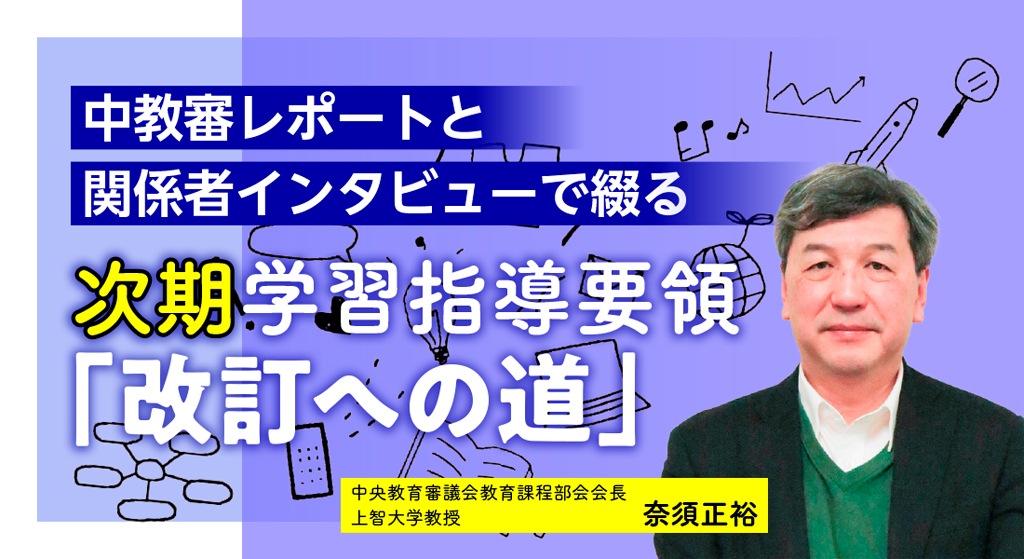
2025年1月末から中央教育審議会で本格的に学習指導要領改訂の議論が開始され、各教科等の具体的な議論に先立ち、教育課程企画特別部会において、全体の方向性について議論が行われ始めたところです。
そこで、この企画では教育課程企画特別部会の親部会であり、同部会の委員の人選にも携わった教育課程部会の奈須正裕会長(上智大学教授)に、改訂の方向性などについて聞いていきます。3回目となる今回は、諮問文の構造やそのポイント、さらにデジタル関連について紹介していきます。
なお、学習指導要領改訂の諮問文については、下記URLよりご覧ください。
https://www.mext.go.jp/content/20241225-mxt_soseisk01-000039447-01.pdf
目次
4要素の議論とともに、条件整備や教員養成についても議論
今回の諮問文の構成はとてもよくできており、ここで改めて諮問文の全体を見てみると、諮問事項の前に3つの課題が示されています。その1点目が多様性の公正な包摂の実現。2点目が概念としての知識の習得や深い意味理解など、資質・能力基盤の学力論。3点目は、デジタル学習基盤の効果的な活用ですが、デジタルが1点目と2点目の課題のよりよい解決を強力に後押ししてくれるのではないかとの期待を込めてのことだと思います。
この3つの課題について端的に言えば、1点目は「令和の日本型学校教育」の答申で提起されたこと、2点目は「現行学習指導要領」の理念、3点目は「GIGAスクール構想」で推進されてきたデジタル学習基盤です。つまり、この10年ほどの間に取り組んできたことが整理されているのでしょう。
その後に、4つの諮問事項が示されており、これらに沿って次の教育課程の基準について議論し、考えていくのだと思います。
ちなみに、教育課程(カリキュラム)というのは、古典的に言えば「何を教えるのか」という内容の選択と配列、つまり内容論が中心です。そのほかに、「何のために教えるのか」という目標論、「どのように教えるのか」という方法論、「その営みがうまくいっているか」を確認する評価論があり、1940年代からこれがカリキュラムの4要素であるとされてきました。
今回はこの4要素の議論とともに、それをうまく動かしていくための条件整備や教員養成などについても並行して議論していくことになります。古典的には内容の選択と配列であった教育課程の議論が、これほどまでに広がっているわけです。
実際に諮問事項の4番目には、「教師の負担」「入学者選抜」「教科書」などが示されています。これら一つ一つの要素は相互作用的に動くものであり、それをどのようにしていけばよいか、これから教育課程企画特別部会の委員間で知恵を出し合って議論することになるのでしょう。
もちろん、連載の第1回で取り上げた、中核的な概念を中心とした目標と内容の構造化などは、ブルーナーによる「構造」主義以来、半世紀以上が経つわけですし、参考にすべき知見はたくさんあります。各教科等の「見方・考え方」と、そこから導き出される内容の系統性を大切にすることや、単元を基盤に授業づくりを考えるということにも異論はないだろうと思います。

