「授業中の積み木から考える~一人一人が大切にされるための場づくり~」インクルーシブ教育を実現するために、今私たちができること #10

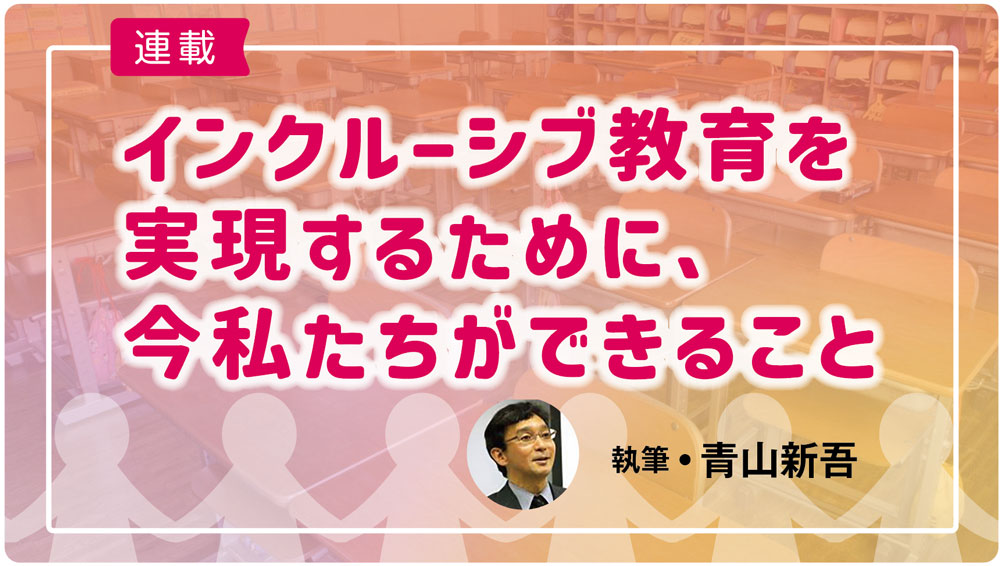
「インクルーシブ教育」を通常学級で実現するためには、どうすればよいのでしょうか? インクルーシブ教育の研究に取り組む青山新吾先生が、現場の先生方の悩みや喜びに寄り添いながら、インクルーシブ教育を実現するために学級担任ができること、すべきことについて解説します。
本連載では、インクルーシブ教育とは、貧困状況にある子どもや性的マイノリティの子ども、外国にルーツのある子ども、不登校の子ども、障害や病気のある子どもなどのマイノリティ属性を含むすべての子どもが対象だとしています。そして、すべての子どもたちが包摂される教育を目指すプロセスがインクルーシブ教育であり、そのためには通常学級の教育をもっと豊かにしていくことが求められているという前提に立っています。
今回は、一人一人が大切にされるための場づくりについて考えます。
執筆/ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科准教授・インクルーシブ教育研究センター長・青山新吾
目次
ある学校にて
ある小学校の教室を訪れました。その学校には、各教室の横に、フリースペースとして、教室の面積と同じくらいの空間がありました。スペース的には、1つのクラスが教室2つ分に近い空間を使用しているという感じでした。
各学年の各クラスとも、その空間を自由に使用できるようでした。そのため、各クラスによって、空間のデザイン、使い方が自由になっていました。とは言っても、結局は子どもたちの机や椅子は半分の空間(教室)に置かれており、残りはフリーの空間となっていたので、各クラスによってそう大きくは変わらないデザインだったと言えます。
似ているようで違っている
この学校は、各教室にたくさんの小型積み木(KAPLAブロック)が置いてありました。各教室にある数は、それぞれ1000個程度だったでしょうか。
ここまでは、各教室のデフォルトであり、どこも同じ仕様です。
ただ、実際に各教室を回ってみると、その風景は異なっていました。
ある教室では、休み時間に使われていたと思われるブロックも、授業が始まる時には、大型ケースの中に美しく片付けられ、ケースはフリースペースの隅にきれいに置かれていたのです。まさに、これから始まる授業に積み木は必要なく、美しく整った空間といった感じでした。
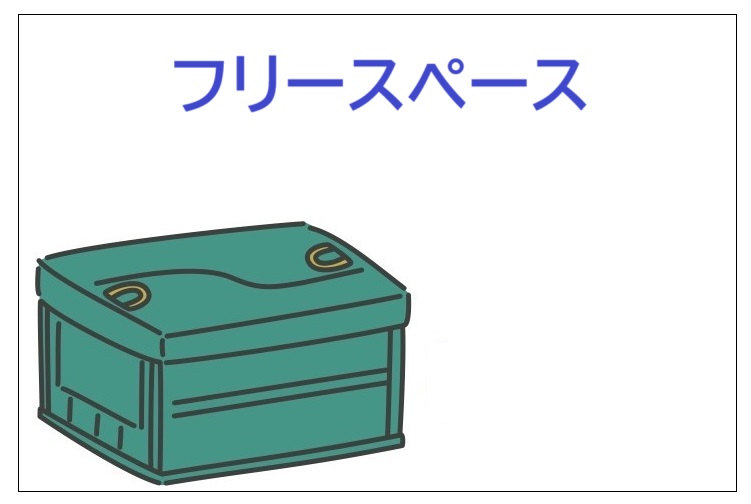
別の教室を訪れてみたところ、フリースペースの隅に置かれたロッカーの中に、積み木を収納する大型ケースがきれいに押し込まれています。先程の教室と似ていますが、さらに収納感が際立つ感じであり、恐らく、あまり使用されていないのではないかという感じに見えました。
また違う教室を訪れました。そこにはなんと、休み時間に子どもたちが積み上げたと思われるタワーが、そのままの状態で立っていました。そんなに不安定な感じではありませんが、結構な高さに積み上げられており、そばにいる僕にも「崩さないようにしなくては……」というちょっとした緊張感が走ります(笑)。タワーの近くには、使用されていない積み木がたくさん転がっています。収納用の大型ケースは床に置いてはあるものの、あまり片付けられていない状態です。まさに「さっきまで作っていたものが、そのままの状態で残っている中で始まっている授業」といった感じでした。
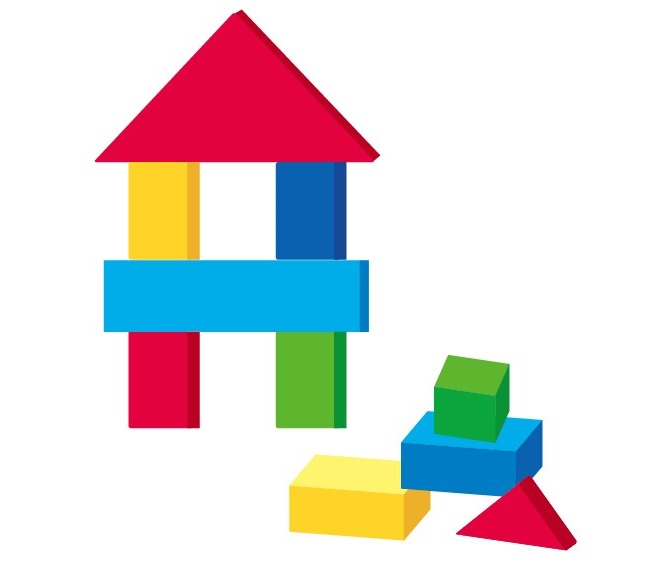
そして、また違う教室を訪れたところ、積み木が床にたくさん転がっています。一見、無造作に投げ捨ててあるように見えますが、よく見ると、床には積み木で作られた平面のデザインや文字が置いてあるのです。先程の教室と違うのは、積み木に立体感がないことですが、「さっきまで作っていたものが、そのままの状態で残っている中で始まっている授業」の風景であるところは似ているなと思えました。

