「哲学対話」をしよう|対話型授業と自治的活動でつなぐ 深い絆の学級づくり #11

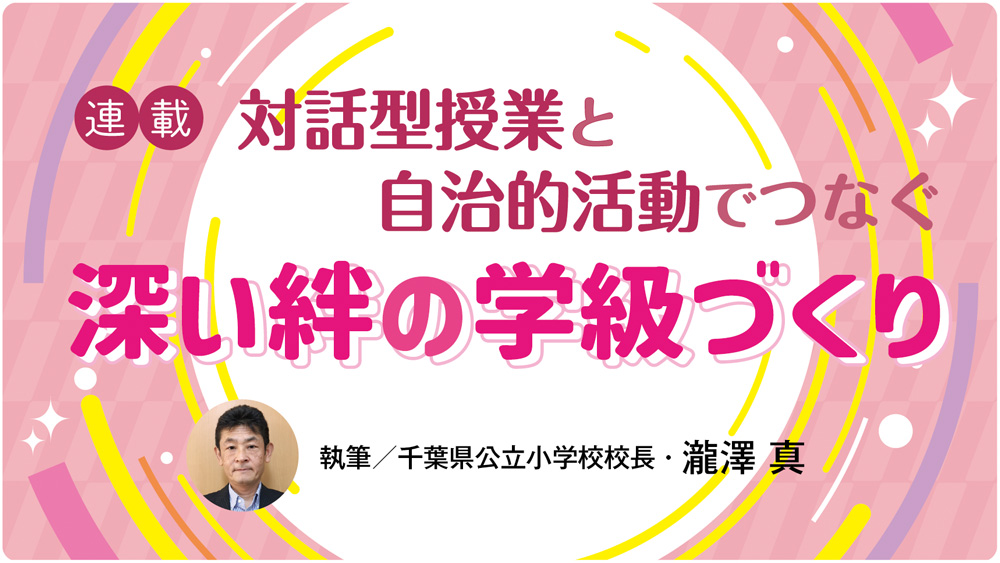
コロナ禍以降、コミュニケーションに苦労する子供や人間関係の希薄な学級が増えていると言います。子供たちが深い絆で結ばれた学級をつくるには、子供同士の関わりをふんだんに取り入れた対話型授業と、子供たちが主体的に取り組む自治的な活動が不可欠です。第11回は、「哲学対話」について解説します。
執筆/千葉県公立小学校校長・瀧澤真
目次
「哲学対話」とは?
対話型学習の取組として私が注目しているのが、「哲学対話」です。
哲学対話は、近年小学校でも活用されるようになってきたものです。源流はアメリカで始められた「こどものための哲学(p4c)」だと言われ、日常生活の中にある哲学的な問いを、対話によって深めていく活動です。
哲学というと難しいものという感じがするかもしれませんが、「何のために勉強するのか」「人生って何だろうか」「幸福とは何か」というように、「~はそもそもどういうことか」を、自由に話し合っていくものです。
哲学対話については確定した型があるわけでなく、実践者によってその進め方は様々です。ここでは私がやりやすいと思っている方法を一例として示します。各自で取り組みながら、よりよい方法にアレンジしてください。
「哲学対話」導入の授業
話し合うグループは10人から20人が適正と言われますが、まずはイメージを共有するために、1回目は学級全員で行うとよいでしょう。
形式的には、以前紹介した「クラス会議」に似ていますので、「クラス会議」を経験している学級であればさほど抵抗なく導入できるでしょう(まだ導入していない場合は、ぜひ取り組んでみてください)。
なお、ここでは45分で行うことを想定して目安の時間を書きますが、子供たちの様子を見て、早めに切り上げたり、延長したりするなど、柔軟に対応してください。
①全員で輪になる【5分】
机を教室の後ろに寄せるなどして、椅子だけを持って集まり、輪になります。
②問いづくりをする【10~15分】
哲学対話では問いを立て、それについて話し合っていきます。ですので、問いづくりが重要であり、できるだけ子供たちに自由に話し合って決めてもらいたいところです。ですが、慣れるまでは、教師がテーマを示すとよいでしょう。
「幸せとは何?」「なぜ学校に来なければいけないの?」「友達は多いほうがいいの?」など、子供の素朴な疑問のようなものでいいでしょう。
何回かやって、活動に慣れてきたら「そもそも~はどういうことか」というテーマで、問いを自由に出してもらいましょう。教師はファシリテーターとして、子供の発言を板書しながら、同じような意見をまとめたり質問を促したりして、考えが深まるように努めます。様々な問いが出たら、話し合いたいことは何かについて意見交換して決めていきます。
③対話をする【15~20分】

クラス会議では「トーキングスティック」というものを使いますが、哲学対話でも同様に、誰が話をするのか、視覚的に分かる物を用意します。一般的な哲学対話では、毛糸玉を使用し、これを「コミュニティボール」と呼びますが、小さなぬいぐるみのようなものでも、おもちゃのマイクでもかまいません。それを持っている人が発言者です。
次に発言したい人は挙手します。発言が終わったら、挙手している人の中から次の発言者を選び、コミュニティボールを渡します。なるべく全員が話をできるように、教師は一定の人ばかりが発言しないように進行していきます。
なお、対話のルールは以下の通りです。
・正解はないので、人を傷つけることでなければ何を言ってもいい
・否定的な発言、態度をとらず、肯定的に聞く
・発言せずに、ただ聞いているだけでもいい(小グループの時は除く)
・発言に対してできるだけ質問をする
・なるべく経験したことを入れて話す
・話はまとまらなくていい、結論が出なくていい
・意見が変わってもいい
・よく分からなくなってもいい
※『考えるとはどういうことか 0歳から100歳までの哲学入門』著・梶谷真司(幻冬舎新書)を参考に作成
要は、自由に互いの考えを交流できればいいのです。流暢な話合いではなく、時には立ち止まり、停滞するような場面があってもよいでしょう。教師はキーワードを板書しながら、ファシリテーターとして、話の整理をします。また、ポイントとなりそうなことを全員に問い返します。ですが、きれいにまとめようとしたり、結論に導こうとしたりするようなことは慎みましょう。教師もまた子供と一緒にじっくりと考えを深めていきましょう。
④話合いを振り返る【10分】
どんなことを考えたか、どんなふうに考えが変わったのかなどを話し合ったり、ノートに書いたりします。また、新しい発見や新しい考えなどが出てきた子に発表させるのもよいでしょう。

