【木村泰子の「学びは楽しい」#34】対話を通じて学び合う環境をつくっていますか?

子どもたちが自分らしく生き生きと成長できる教育のあり方について、木村泰子先生がアドバイスする連載の34回目。今回は、読者の方の声をもとに、多くの学校で今起こっている問題の原点と対話の大切さについて考えていきます。(エッセイのご感想や木村先生へのご質問など、ページの最後にある質問募集フォームから編集部にお寄せください)【 毎月22日更新予定 】
執筆/大阪市立大空小学校初代校長・木村泰子

目次
最優先すべきこととは
「子どもにとって一番いいことは何かを真っ先に考えなくてはならない」
これは子どもの権利条約の第3条です。
みなさん方の学校はどうでしょうか。「子どもにとって最善の手段は何か」を常に最上位に置いて、教職員で対話をツールに「子どもにもっともよいこと」を生み出して行動しているでしょうか。
ともすると、「責任はだれがとるのか」「周りの子どもが文句を言うのではないか」「保護者の理解が得られないのではないか」「うまくいかなくなったら裁判をされて学校が負けるのではないか」などの考えが先行して、結果的に困っている子どもだけではなく、周りの子どもたちも学校に不信感を抱き、学校に行く意味がわからなくなるといった状況に現在の学校は陥っている気がします。これらの結果が「自死」「不登校」「いじめ」過去最多の子どもの事実につながっているのではないでしょうか。
自分が校長だったら……
読者の方からメッセージをいただきました。すべてを伝えることはできませんが、みなさんが(この学校の校長だったら……)と自分事に置き換えて考えをもってください。
私の子どもは小学校2年生で発症し、退院後の学校生活からは病気のことを子どもたちや教職員に開示して、現在6年生になります。
食事のための医療行為が必要で、自分の病気を受け入れた子どもは、これまでは保健室や職員室で行っていた医療行為を、教室で行いたいと希望しました。
この子どもの声に対して、学校や教育委員会は、安全上の理由や市の慣例を理由に拒否しました。中でも、周りの子どもたちに聞いてみてほしいとのお願いには、周りの子どもがどう受け止めるか、口には出さなくてもいろんな思いを抱えてしまう子どももいるので話合いはさせられないとの回答だったそうです。
結果的にこの子は学校が安心できる場所ではなくなり、主治医からも自死をする可能性が高いと告げられたとのことです。
もちろん、学校の対応を批判するために今回のテーマがあるのではありません。現在の学校現場には同様のことが山積みの状態ではないでしょうか。学校としてできるかできないかの判断で事を進めると、学校と保護者が分断され、その間にいる子どもが困ってしまいます。
みなさんがこの学校の校長ならどんな行動をとりますか。
目的と手段を混同しない
学校での学びは、社会につながる学びが不可欠です。子どもたちは、自分との違いをもつ様々な友達とともに学び合うからこそ「社会で生きて働く力」を獲得するのです。
私には直接この学校の状況は分かりません。一部の情報しか知らないでしょう。でもね、最優先に考えることは、病気の治療を余儀なくされているこの子が「教室で医療行為を受けたい」と言った目的はどこにあったのかを、まずはこの子に教えてもらうことです。この子の声を学校は聞かせてもらうことから始めないと、何一つ「学び」に変えることはできないでしょう。「教室で受ける」ことを「学校が認めるか認めないか」などといった次元で校長や市教委が保護者との話合いを進めている以上、「プロ」ではありません。
学校の中に警察官や裁判官は不要です。この子が求める医療行為はあくまでも手段であって、保健室から教室に変えたいと申し出るこの子の思いや願いは必ずこの子の中にあります。
学校の立場として結果的に教室で医療行為ができないとの判断であれば、まずはこの子の心の底にある声を聴かせてもらって、この子の願いを実現できる他の手段を周りの子どもも含めて考えていくことが必要でしょう。その過程が、すべての子どもに不可欠な「社会につながる学力」なのです。
学校や市教委が「困っている子ども」の障壁になるのは残念すぎます。「校門をくぐっても子どもの権利条約を」に立ち返りませんか。
人と人をつなぐツールは対話です
人はみんな違っていることが当たり前で、できるかできないかの結論を出すことが解決ではありません。対話を通して、初めて互いの理解し合えないところが見えてきて、豊かな思いや方法が生み出されます。
大人は対話がとても苦手です。これまでの学校教育の中で体験していないからです。だからこそ、子どもたちには普段の授業の中で「対話」をツールに学び合う環境が必要なのです。
読者のみなさんの中に「先生」が多くいらっしゃると思います。「先生」の仕事は「子どもの声を聴く」ことからしか始まらないというスタート地点を再確認しませんか。
日本の学校教育の最大の課題は「主体性」と「当事者意識」の欠如であると言われる理由は、ここにあるような気がします。
みなさん、今年もご一緒に学ばせていただいてありがとうございました。どうぞよい年をお迎えください。
〇学校において最優先すべきことは何なのか、子どもの権利条約に立ち返って考えてみよう。
〇困っている子どもの声を聴き、その願いを実現できる道をみんなで考える過程こそが「社会で生きて働く力」につながっていく。
〇人はみんな違って当たり前。対話を通して、互いを理解し、学び合える環境をつくっていこう。
【関連記事はコチラ】
【木村泰子の「学びは楽しい」#33】子どもの人権について考えたことはありますか?
【木村泰子の「学びは楽しい」#32】現状に悩んだら、学校のシステムを抜本的に見直しませんか
【木村泰子の「学びは楽しい」#31】見えないところを見ようとする大人に
※木村泰子先生へのメッセージを募集しております。 エッセイへのご感想、教職に関して感じている悩み、木村先生に聞いてみたいこと、テーマとして取り上げてほしいこと等ありましたら、下記よりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。
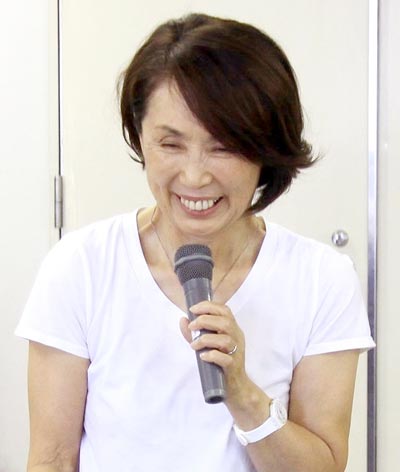
きむら・やすこ●映画「みんなの学校」の舞台となった、全ての子供の学習権を保障する学校、大阪市立大空小学校の初代校長。全職員・保護者・地域の人々が一丸となり、障害の有無にかかわらず「すべての子どもの学習権を保障する」学校づくりに尽力する。著書に『「みんなの学校」が教えてくれたこと』『「みんなの学校」流・自ら学ぶ子の育て方』(ともに小学館)ほか。

