システムを変えるーサラマンカ声明から出発して「選択」を考えるー|インクルーシブ教育を実現するために、今私たちができること #7

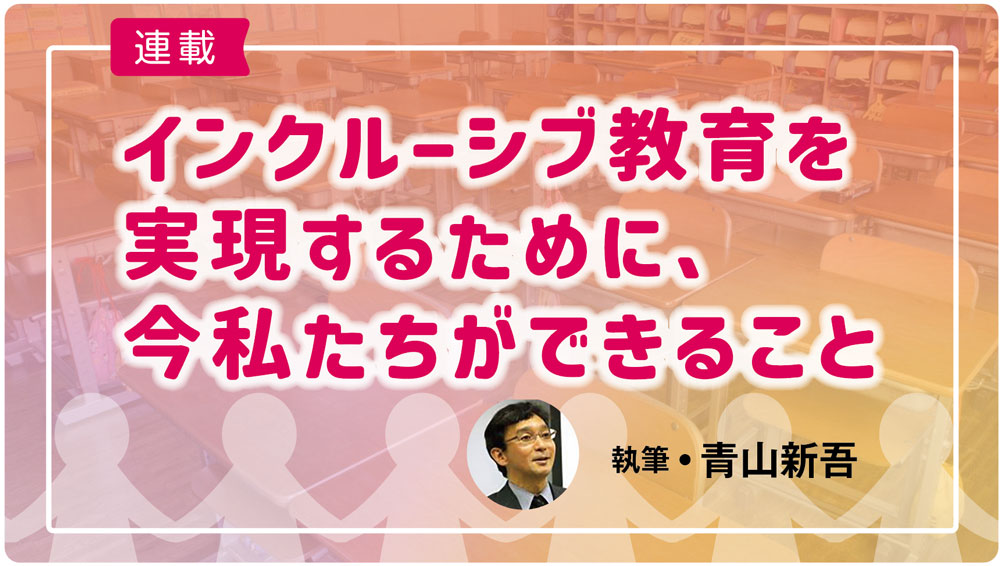
「インクルーシブ教育」を通常学級で実現するためには、どうすればよいのでしょうか?インクルーシブ教育の研究に取り組む青山新吾先生が、現場の先生方の悩みや喜びに寄り添いながら、インクルーシブ教育を実現するために学級担任ができること、すべきことについて解説します。
本連載では、インクルーシブ教育とは、貧困状況にある子どもや性的マイノリティの子ども、外国にルーツのある子ども、不登校の子ども、障害や病気のある子どもなどのマイノリティ属性を含むすべての子どもが対象だとしています。そして、すべての子どもたちが包摂される教育を目指すプロセスがインクルーシブ教育であり、そのためには通常学級の教育をもっと豊かにしていくことが求められているという前提に立っています。
今回は、「選択」する場面の検討を通して、教育システムを変えることの意味について考えてみます。
執筆/ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科准教授・インクルーシブ教育研究センター長・青山新吾
目次
サラマンカ声明
サラマンカ声明とは、スペインのサラマンカにおいてUNESCO(国際連合教育科学文化機関)とスペイン政府によって開催された「特別ニーズ教育世界会議」において採択された宣言のことです。ここでは、インクルーシブ教育についての原則、「万人のための学校」の必要性が示され、世界的にインクルーシブ教育が注目されるきっかけになったと言えるでしょう。
この声明の中に以下の一節があります。
「学校というところは、子どもたちの身体的・知的・社会的・情緒的・言語的もしくは他の状態と関係なく、『すべての子どもたち』を対象とすべきであるということである。これは当然ながら、障害児や英才児、ストリート・チルドレンや労働している子どもたち、人里離れた地域の子どもたちや遊牧民の子どもたち、言語的・民族的・文化的マイノリティーの子どもたち、他の恵まれていないもしくは辺境で生活している子どもたちも含まれることになる。これらの状態は、学校システムに多様な挑戦をもたらすことになる。」(訳/国立特別支援教育総合研究所)
インクルーシブ教育を進めていく際に、学校システムに多様な挑戦とはどのようなことでしょうか。
どの子も選択できる工夫

ある小学校でのことです。6年生の算数の授業でした。
クラスには、算数の得意な子ども、苦手な子ども、集中が続きにくい子ども、一人で取り組みたい子ども、友達と一緒に取り組みたい子ども等々、いろいろな子どもがいます。その中でも、特に算数が苦手な子どもも一緒に学べる授業を目指して、意欲的な取組がなされていました。
この場合、個別の支援を細かく想定するのかと思いきや、授業を拝見すると少し違った構想がなされていたのです。
この授業では、子どもたちが学習を進めるための「ヒントカード」が用意されていました。ヒントカードは2種類ありました。
・モノクロのカード
・要素ごとに色分けされたカラーのカード
※ヒントは2つとも同じ内容。
この授業では、苦手な子どもだけに支援をするのではなく、どの子どももヒントカードを自分で「選択」できるようにされていたのです。もちろん、ヒントカードを使わないことも考えられます。
ヒントカードは教室の前に置かれていて、子どもたちは自席から動いて、各自でカードを取ってくるスタイルになっていました。
また、授業の最後に応用問題に取り組む展開となっていました。その応用問題も、複数用意されていました。それぞれ難易度に違いがあり、子どもたちは各自で、自分が取り組もうと思う問題を「選択」できるようにされていたのです。
これらの授業スタイルは、同じ問題に同じペースで全員が取り組むのではなく、各自のペースで、各自のやり方で学べることに挑戦していこうとする明確な意図が感じられるものでした。

