新学期が始まっても生活リズムが戻らない子への接し方|9月【特別支援学級の学級経営】
- 連載
- 特別支援学級の学級経営

文部科学省からは、すべての新任教員が10年以内に特別支援教育を複数年経験するよう努めるように通知が出されています。特別支援の知識や経験が乏しいまま、手探りで特別支援学級を担任している先生も多いことでしょう。この記事では特別支援学級でよくあるケースを挙げて、その道の専門家がポイント解説します。今回は、夏休み明けで生活リズムが戻らない子どもについてのお話です。
構成・執筆/兵庫県公立小学校校長・公認心理師・特別支援教育士スーパーバイザー 関田聖和
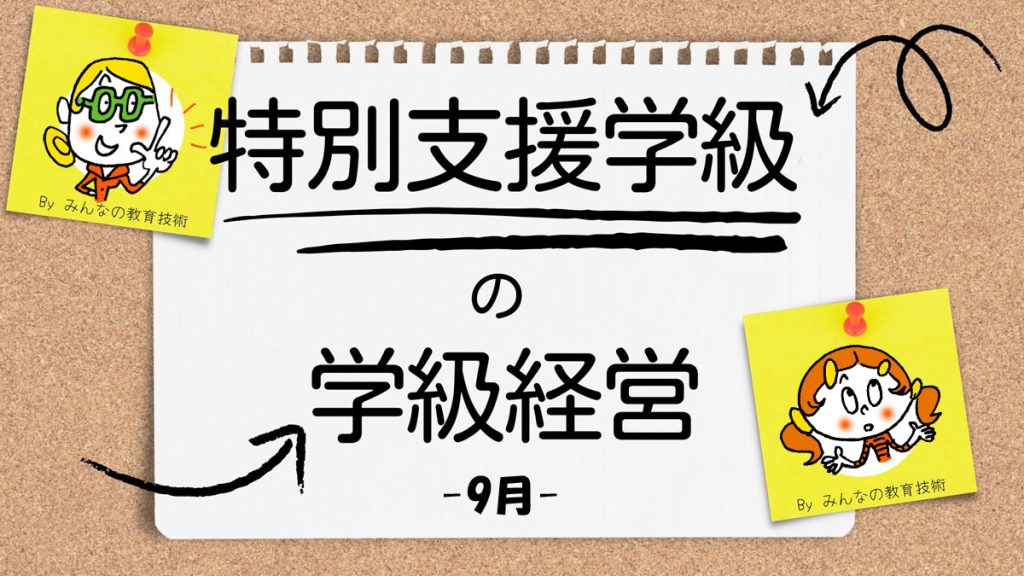
目次
登場人物
皆川先生:自閉情緒クラス担当。教師生活25年のベテラン。特別支援学級主任・特別支援教育コーディネーター
島原先生:知的クラス1担当。教師8年目。特別支援学級担任1年目
根本先生:知的クラス2担当。教師3年目。特別支援学級担任2年目
しゅんたさん:皆川先生担当。独特な自分の世界をもっていて、彼なりのルールがある。他人とは打ち解けるまでにかなり時間がかかる。粘土や工作などは緻密で動物などは本物そっくり、大人顔負けの作品を作りあげる。
長期目標:同じクラスの友だちといっしょに作品作りをすることができる
短期目標1:大人といっしょに作品作りをすることができる
るなさん:島原先生担当。よく動く。出し抜けにしゃべる。思いついたことをすぐに伝えてしまう。言わないでいいことまで言ってしまうことがある。発想が豊か。次から次へと案が浮かぶ。
長期目標:会話のキャッチボールを楽しむことができる
短期目標1:先生としりとりなどの遊びに取り組むことができる
ゆうかさん:根本先生担当。不注意。衝動性が高い。よく忘れてしまう。様々なことが気になってしまい、失敗することが多い。いろいろなことに気が付いてくれるので、友だちが忘れていたことを思い出してくれるようなことがある。
長期目標:タブレットで記録を取ることができる
短期目標1:タブレットで必要な事柄を写真に撮ることができる

