多様性や違いを大切にした取組をしよう~ー「マイノリティ」と「マジョリティ」ー|インクルーシブ教育を実現するために、今私たちができること #6

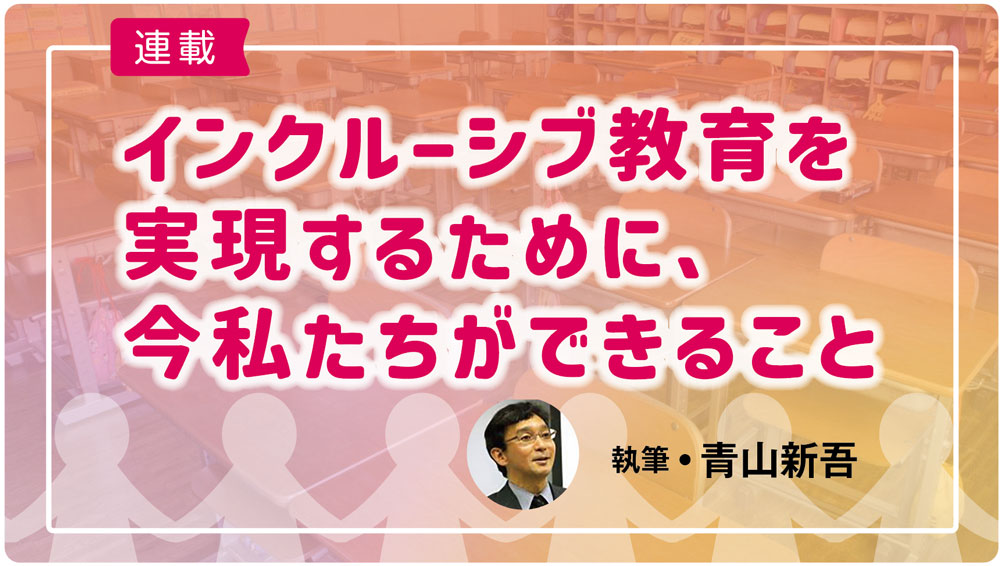
「インクルーシブ教育」を通常学級で実現するためには、どうすればよいのでしょうか? インクルーシブ教育の研究に取り組む青山新吾先生が、現場の先生方の悩みや喜びに寄り添いながら、インクルーシブ教育を実現するために学級担任ができること、すべきことについて解説します。
本連載では、インクルーシブ教育とは、貧困状況にある子どもや性的マイノリティの子ども、外国にルーツのある子ども、不登校の子ども、障害や病気のある子どもなどのマイノリティ属性を含むすべての子どもが対象だとしています。そして、すべての子どもたちが包摂される教育を目指すプロセスがインクルーシブ教育であり、そのためには通常学級の教育が変わっていくことが求められているという前提に立っています。
今回は、多様性や違いを大切にした取組について考えてみましょう。
執筆/ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科准教授・インクルーシブ教育研究センター長・青山新吾
目次
「マイノリティ」と「マジョリティ」

インクルーシブ教育を考える際に重要な概念の1つに「マイノリティ」と「マジョリティ」があります。「マイノリティ」に思いを寄せて支援しようなどという文脈で示されることもあるように思います。そもそも、この「マイノリティ」と「マジョリティ」とは、どのように捉えればよいのでしょうか?
一般的には、これらを「少数派」と「多数派」として捉えることがあるように思います。例えば、障害のある人を少数派の「マイノリティ」として捉え、障害のない人たちを多数派の「マジョリティ」として捉える場面が思い浮かびます。
しかし実際には、「マイノリティ」と「マジョリティ」は単に少数派と多数派として捉えられるものだけではありません。ある少数グループが、権力、影響力、優位性などを有して、コミュニティ全体に強い影響力を持っていれば、それが「マジョリティ」として機能することがあるからです。と、このように書いてみたものの、大学の授業の中での学生たちの様子を見ていると、すぐには具体例が思い浮かばない様子でした。
学校の中で
そんなある日、1人の学生が、高校時代のあるエピソードを寄せてくれました。授業時に用意しているオンライン上のパーソナルなメッセージ欄には、時折、大切な話が寄せられるのです。
高校時代、体育の授業時には、授業開始前に必ず着替えて整列しておかないといけなかったというのです。しかし、休憩時間は10分しかなく、運動場は少し離れたところにあったため、自分も含めてみんなは、必死に走って移動していたそうです。ある時、前日に降った雨の影響で道が濡れていたために、友人が転んで怪我をしてしまったといいます。あまりに理不尽だと考えて教師に伝えに行ったところ、「これから気を付けろ」と言われて終わったという話が綴られていました。
読み終えた僕は、なんとも言えない感情に苛まれながらも、あることに気付いておりました。それは、このエピソードが、「マイノリティ」と「マジョリティ」を単に少数派と多数派に捉えない例として分かりやすいということでした。このエピソードにおいては、権力そして優位性をもっているのは明らかに教師サイドです。でも数を考えれば、教師は少数派であり、圧倒的多数は生徒サイドなのです。つまり、少数派の教師が「マジョリティ」であり、多数派の生徒が「マイノリティ」として位置付けられていると言えるのです。
学校の中で成立しているこの関係性を、あちこちの学校教育現場の事実に即して、丁寧に読み解いていきたい気がします。

