今どき教育事情・腑に落ちないあれこれ(その4) ─腑に落ちない漢字指導の現実─【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第63回】

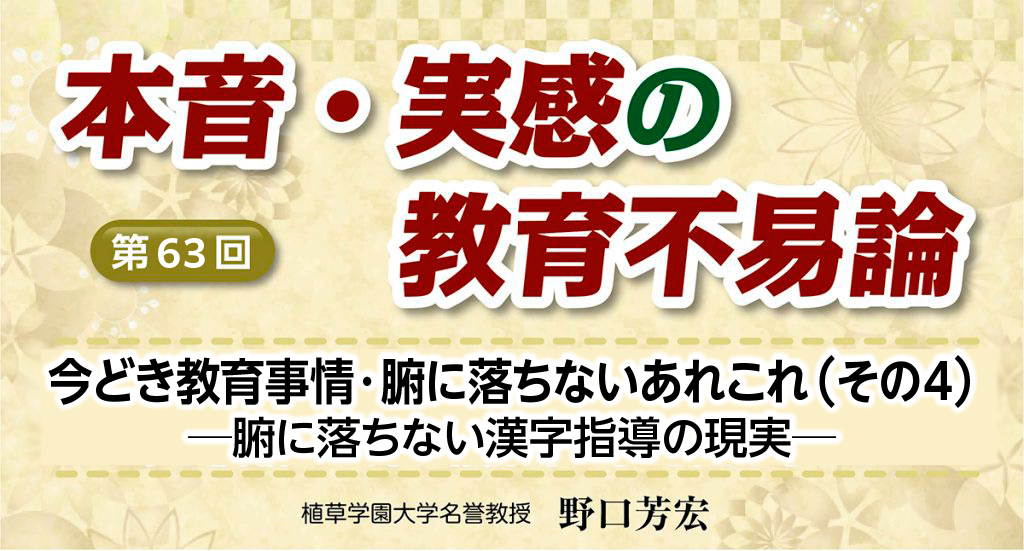
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第63回は、【今どき教育事情・腑に落ちないあれこれ(その4)─腑に落ちない漢字指導の現実─】です。
執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。

目次
1、小学校から高校までの国語勉強会
65歳で第二の定年退職を迎えた折に、これからは暇になるだろうと考えた。私と一緒に学びあう仲間があったら嬉しいと思い、「授業道場 野口塾」という会を立ち上げた。全国各地で年一回、それぞれの事務局が好きなように運営することにした。コンセプトとしては「言葉の教育」と「心の教育」をセットにすること、地元の実践発表を加えること。もう一つは、子供の為の講座ではない、教師自身の向上を目的とする修養、教養講座を一齣(こま)入れること。そして終了後には差しつ、差されつの懇親会を持つことを申し合わせて出発した。
これが、今では何と470回、年数にして23年も長寿を保って今も続いている。尤(もっと)も、この内200回余りはコロナ禍の影響下のオンライン野口塾で、各回は3.5時間程である。オンラインの常連はざっと7・8人という小人数で、その大方は退職した面々である。退職をしても熱心に野口塾に顔を出すほどの勉強好きの仲間なので、殆(ほとん)どが毎回全員出席する。小人数であることを活かして大いに討論が高まり、対面と変わりのない密度と親しみが生まれ、盛り上がりを見せる。
教材は、小学校から高校までの国語教科書からほぼ均等に採用している。長い間、高校の教材とは縁が遠くなっていたので、鷗外の『舞姫』や、漱石の『夢十夜』などとは新鮮な出合いになる。高校の論説文や詩教材となると、その高度なこと、難解なレベルであることなどに驚くことが多い。
そうなると、念入りに、かなり真剣に向き合わないと教材そのものが理解できない。辞書を引きながら、あるいはネットも駆使しつつ、議論が熱くなるのもしばしばだ。その過程で、教科書の教材としての在り方や位置づけ方、また、教材化の意図などに話が及ぶこともしばしばで「教え方」以前の教材論、素材研究論への関心も高まる。「これでは、国語の学力形成の上からは疑問だなあ」と思うことも当然出てくる。それらを思い出しながら小学校から高校までの国語教科書のあり方についていくつかの提言をしてみたい。大方の御批判が戴ければ幸いである。
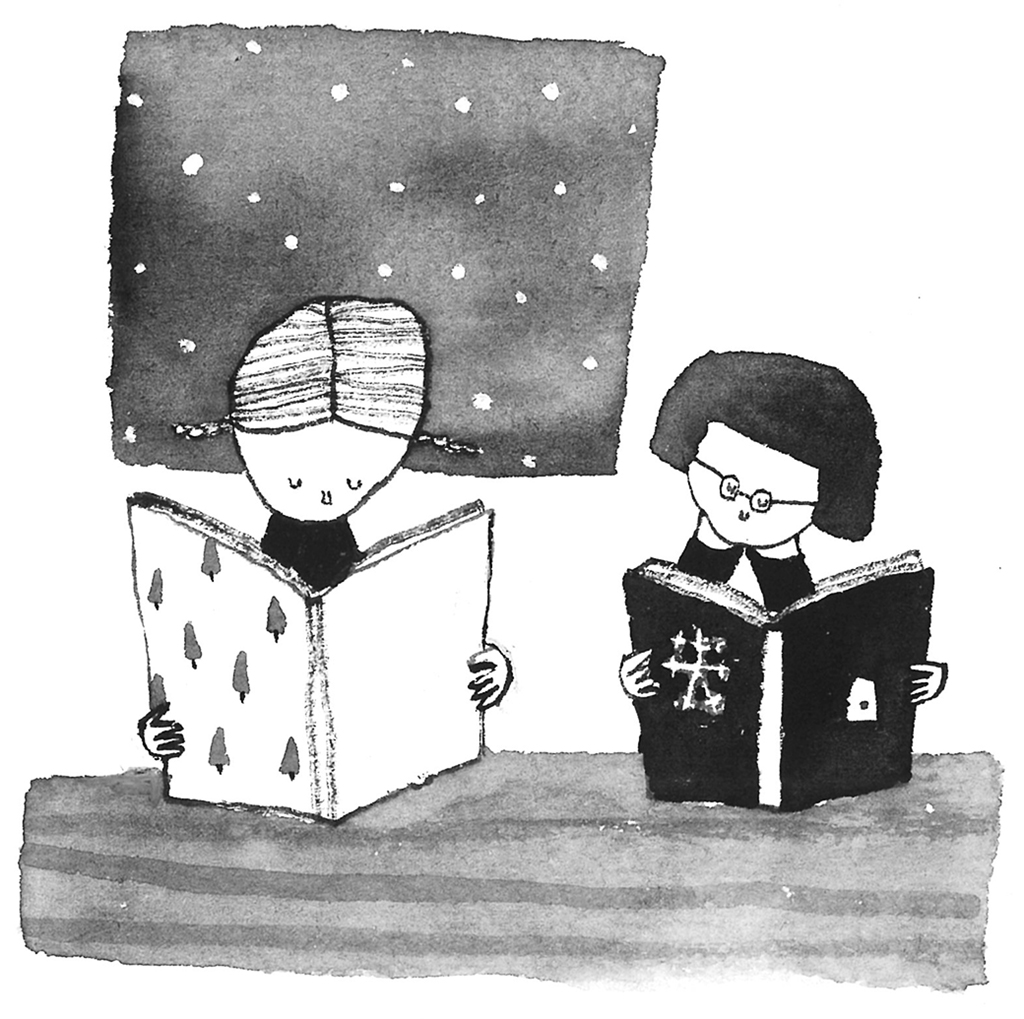
2、漢字が多く読めることの重要性
学年別漢字配当表は、小学校教材の表記のあり方を強く規制している。これが国語学力の形成、向上の枷にもなっている。むろんのこと、学力の評価という観点に立てば、学年別の漢字を特定しておかなければならない。しかし、それは「少なくともこれだけは身につけさせなさい」といういわば最低限の到達基準であり、さらに高い学力をつけてはならないということではない。
また、漢字の学力としては読む力としての読字力と、書く力としての書字力との二つがあり、言うまでもないのだが読字力の方が重要である。その故にこそ、学年別配当漢字については、配当された学年では読字力を完全に習得させ、書字力については一年上の学年で完全習得をさせればよいことになっている。これは理に適ったことだ。
我々大人にもこの原理は当てはまる。憂鬱(ゆううつ)や顰蹙(ひんしゅく)は大方の大人が読めるだろうが、これを書ける人は大人でも少ない。書けなくても困らないからだ。書く時には辞書を引けばいいのだ。但し、読めないのでは困る。読めて意味が分かれば日常の用は足りるのである。読めたのだが意味が分からないのでは用が足りない。
読んだ時に「あの事だな」と理解するのは、その言葉を聞いたことがある、知っている!と思い出せたからである。これが「語彙力」である。沢山の言葉を知っていることが重要な国語の基礎力である。読めなかった漢字が読めた時に「あのことなんだ」、と納得するのである。逆に「あの言葉はこういう漢字だったのか!」と知って驚くこともある。
一般に仮名は表音文字、漢字は表意文字と言われているが、塩原経央氏は、「漢字は表語文字だ」と言っている。つまり、多くの漢字が読めるということは、そのまま沢山の言葉、語彙を知っていることになる、というのである。表語文字とは名言だ。
この理屈がわかってくれば、多くの漢字が読めるようになることがどんなに大切なことかということに気づくだろう。
3、読字力の形成原理「早くから、何回も」
言葉の教育、心の教育の振興を求める有志の勉強会を全国各地で開いて23年になる、その回数は470回を超えた。ここに集う仲間はこれまでに述べた理屈を理解しているので普段の各教科の授業の中で漢字を多用することに努めている。特に板書にその主張がよく表れる。
例えば、教科書には「おおきなかぶ」と書いてあるが、板書では「大きな蕪」と書く。「蕪」は、人名漢字には出てくるが、常用漢字外であり、当然教育漢字にはない。それなのに一年生の子供が「かぶ」と読める。それは教科書に「おおきなかぶ」と書いてあるからだ。一年生でもこの漢字がすぐに読めるようになる。但し、すぐに忘れる。だから繰り返し板書で出合わせるのである。「教えたことは思い出す。教えないことは知らない」これは私の仲間の合言葉だが当然の原理、原則である。だから「知らないのは子供の罪ではない。教えない側の罪である。」良いこと、必要なことはどんどん教えた方が良いのである。
ところが、この頃は「教えないで考えさせろ」という俗論が広がっているようで理解に苦しむ。教わったことを元にして初めて考えられるのだ。「考えろ」ということも教えていることの一つではないか。つまらない教育論にごまかされてはいけない。
教師の板書は子供に注目、注視されている。ノートにも視写される。力のある子は漢字を好んで書くようになる。それを制止する必要はないが、書くことはさせなくてよい。平仮名で十分だ。まず身につけたいのは読字力であり、書字力ではないからだ。読めて読めて読み飽きるようになれば、殆ど自然に書けるようにもなる。自分の名前が漢字で書けるのはこの実証的現象である。
多くの漢字が読めるようにしてやることの効用、効果は大きい。多くの文章や本が難なく読めるようになるからだ。多くの本を読む子の学力が高いのは周知のことだし、読書が昔から大事にされるのはこの為だ。近頃の子供や若者の「活字離れ」「読書離れ」が問題になっているが、その大きな原因の一つに読字力の低下(漢字が読めないこと)があることは殆ど言われていない。
さて、その読字力を高める原理は実は至って簡単、明快である。それは次の一点に尽きる。
早くから、何回も
早い時期から、何回も繰り返し出合わせることによって、どの子も難なく漢字をいっぱい読めるようになる。自分の家の表札の漢字が読めない子はいない。それは要するに「早くから、何回も」見ているからだ。
4、漢字の読字力向上には石井方式
中国や台湾の子供は全て漢字で書かれた絵本に親しみ、楽しみ、読み、喜んでいる。これも「早くから、何回も」の原理が生む事実である。日本では、学年別漢字配当表に対する誤解がこの原理の適用、活用を阻んでいる。残念かつ滑稽で悲しい現実である。「早くから、何回も」という原理を発見し、それを実証し、実践して見せた偉大な研究者が教育学博士石井勲先生である。石井博士の大発見に対する評価は世界的には高いのだが、残念ながら国内では低い。学年別漢字配当表に対する根強い誤解が学校現場に「定着」してしまっているからだ。
石井式とも石井方式とも呼ばれる石井勲博士の漢字指導法は、今でも学校教育界では「目の仇」にされ、無視、敵視され広まらないままである。だが、幼児教育の世界では必ずしもそうではない。漢字を多用した絵本や読本が、なんの抵抗もないどころか、大歓迎されて子供に迎えられ、喜ばれ、楽しまれているのだ。但し、それも「早くから、何回も」の原理を理解する力のある園長に恵まれた幸せな少数の園に限られることだが──。
蛇足ながら、なぜ幼児教育の世界では歓迎されたかということについての解も単純かつ明快である。幼児教育の世界では断然私学が多く、そこには教育委員会や行政の管理や規制が強くは及ばないからである。言うまでもないようなことだが、学年別漢字配当表が不介入、無用の世界なので、そこでは存分に独自の教育が花開いているという訳だ。
5、幼児の音読、作文コンクール異聞
幼児教育では教科教育は行われていない。教科がないのだから、当然教科書はない。だから、読み、書き、計算の指導はしなくていいし、してはならないと考えている園が大多数である。読み、書き、そろばんは小学校に入学してからのことだ。幼児の教育は「遊び」が中心であるべきだ、と考えている園が多い。こういう考え方は「自由保育」と呼ばれている。
その反対が、明確な指導目標と計画を作って教育をしている「設定保育」であり、「計画保育」、「一斉保育」とも呼ばれている。これらは少数派である。この少数派は私立の学校法人や福祉法人が運営する保育園、こども園、幼稚園が断然多い。公立の園では皆無、あるいは例外的に少ないのが現実だ。
設定保育を進める幼保園の子供は、漢字の絵本や読本をどんどん楽しんで読み、日記や作文も書いている。それらの水準を高めるべく、全国的なコンクールが音読でも作文でも開かれていて、その応募者は年々増加し、当然ながらそのレベルも向上している。
さる文部大臣の経験者が幼児作文コンクールの審査員になり、そのレベルの高さに驚いて文部大臣賞も考えたいとの意向を持たれ、同省の担当者に話したところ「とんでもない!」と大反対されたという笑えない笑い話もあった。文部省は幼児の読み書きの指導を認めていない立場にあるからだ。その立場で文部大臣賞を出したら「とんでもない」ことになるという訳だ。よく筋の通ったこぼれ話ではある。
幼児教育の大切さを否定する者は一人もあるまいけれど、その「教育」とは何か、という実情、実態となると正反対の考えが存在しているのである。「教育しないという教育」「教えないという教育」が、「子供を尊重すること」であり、「子供の主体性を育てることになる」と考えている人は驚くほど多く存在する。そのような考えに賛同し、支持し、敬服し、疑わない人の数は、更に、更に多い。但し、多数の考えが正しいとは言えないことも少なくない。再三、再四私が引く格言がある。ここでも引いておきたい。
好きか、嫌いかは自分が決める。
良いか、悪いかは社会が決める。
正しいか、正しくないかは歴史が決める。
この格言の重みを、教育に関わっている全ての人が共有すべきである。そうなれば教育というものの、些末や枝葉に囚われることなく、教育の「根本、本質、原点」に立ち返って考える骨太の実践が生まれることになるだろう。
執筆/野口芳宏 イラスト/すがわらけいこ
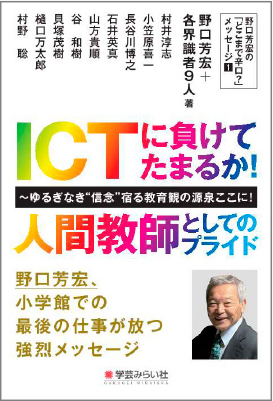
<野口芳宏先生、新刊のご案内>
この直言連載の中から9編分を厳選した野口芳宏先生の最新書籍『ICTに負けてたまるか 人間教師としてのプライド ~ゆるぎなき “信念” 宿る教育観の源泉ここに!』(学芸みらい社)は2月14日発売予定です。ぜひ、お読みください。

