ほくとが幸せな学校にしよう【玄海東小のキセキ 第10幕】
- 連載
- 玄海東小のキセキ
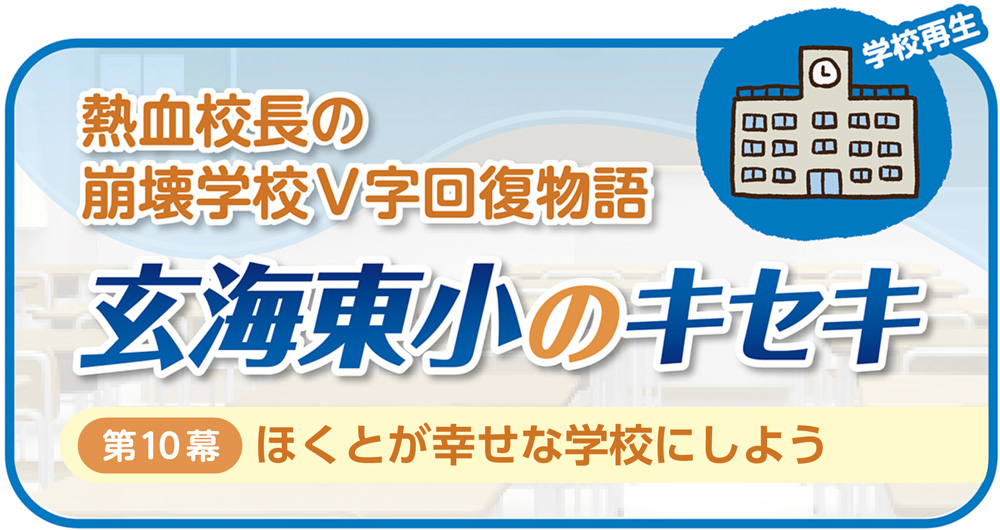
学校下の交差点で朝の挨拶を交わすうちに、脇田に親しみを感じた子供たちが校長室を訪れるようになります。脇田は5月から学級会と縦割り遊びを開始しました。集会活動では、けんかが起きてしまいますが、縦割り遊びでは、下級生を思いやる遊びをして、6年生がリーダーシップを発揮します。
目次
校長室はクールダウンの場所

校長室で宿題をしていたほくとは、迎えにきた北崎とともに教室へ向かった。
4月の就任早々、脇田は校長室の廊下側のガラスを入れ替えた。すりガラスだったのを透明なガラスに変更し、校長室のドアを開放したままにした。
脇田は学校を見て回っていたから、校長室を不在にすることが多いが、子供たちには、いつでも気軽に会いに来てほしかったからだ。通りがかった子供が覗いたりしたら、すぐに声をかけられる。
同じ校内にいるといっても、教室で子供と接する担任と比べれば、校長と子供の距離は遠い。校長室を触れ合いの場にすることで、子供たちの変化が自分にフィードバックされることを狙ったのだ。
そうすると、4月半ばくらいから子供たちがちょくちょく校長室を覗きに来るようになった。
脇田は給食ができあがると、すぐに給食の検食を行うのが日課である。給食の中に異物が混入していないか、食品が適切に加熱され、または冷却されているかなどを確認するのである。
脇田が校長室で検食していると、そこへ何人かの1年生が侵入してきた。
「もう食べてる~」
脇田を指さしてそう言いながら近づいた1年生が、「なんで先に給食を食べとうと?」と尋ねる。
「腐っていたら、大変でしょう。それを確かめているんだよ」
「えーっ!」
1年生は腐っているという言葉に食いつく。ちょうどそこへ慌てて入ってきた担任の女性が咎(とが)めた。
「校長先生、驚かさないでください。さあ、教室に戻りますよ」
担任に叱られた脇田は、1年生になったような気がした。
バタバタと足音が近づいてきた。1年生たちと入れ替わりに、子供が校長室に飛び込んでくる。4年生のほくと(仮名)だった。学校下の交差点では、最初から挨拶を交わしてくるような人懐っこい男の子で、短髪でめがねをかけている。校長室に来るのは初めてだった。
「校長先生、こんにちは~」
ほくとは投げやりな口調で挨拶して、大きな会議用テーブルの下に潜り込んだ。ブツブツ文句を言っているようだが、うまく聞き取れない。
「ほくとくん、こんにちは」
脇田はそう言ったまま、書類に目を通している。ほくとは、すぐかっとなり、拗(す)ねるところがあるから、こんなときは放っておくに限る。
「校長先生、さようなら~」
「はい、さようなら。また、おいで」
落ち着きを取り戻したほくとは教室に帰っていった。「友達と言い争いでもしたのかな」と思いながら、書類から目をはずした脇田は、ほくとを見送った。
それから幾度となくほくとは校長室にやってきた。遠くから足音が聞こえてくると、脇田は「ほくとだな」とわかるようになった。校長室が彼のクールダウンする場所になっていた。
6月に入ったころ、1時間目が始まる前にほくとが校長室に入ってきた。挨拶もせずに応接ソファにごろっと寝転ぶ。「登校早々にけんかしたのか」と脇田は思った。いつもならばクラスの巡回に向かうところだが、それを止めた。
1時間目のチャイムが鳴った。応接ソファに寝転がっていたほくとが起き上がり、デスクに向かっている脇田の傍まで歩んできた。
「校長先生、今日ね……」
ほくとはうつむいたまま、しゃべりはじめた。
「どうしたん?」
脇田はほくとのほうを向いた。
「ばあちゃんから言われたと」
「なんて?」
「ぼくはだめな子なんよ」
「だめなことがあるもんか」
その言葉で、ほくとは初めて脇田の顔を見た。
「だって、かあちゃんに捨てられた子って、ばあちゃんから言われた」
そんなことを言われたので、ほくとは朝から機嫌が悪かったのだ。
脇田はほくとの家庭事情を知っていた。ほくとが3歳のとき、家族が祖母の暮らす実家に戻ると、すぐに母親は子供を置いてどこかへ出奔(しゅっぽん)してしまった。行く先は皆目わからない。ほくとの入学式に母親は現れなかったと聞いた。父親は漁師をし、祖母は小さな食堂で働いて生計を立てていた。
「ほくとはだめな子やなか。友達とけんかしても、自分を抑えようと頑張るいい子やないか。おばあちゃんはほくとのために一生懸命に働いてくださっているのだから、本気でそんなことを思っておられんよ」
ほくとの肩に手を置きながら、脇田はそう言うのが精いっぱいだった。
その日の終礼の時間に、脇田は20人ほどいる教職員に向かってほくとの話をした。
「私たちはどれだけ頑張っても、ほくとの母親を連れ戻すことはできません。でも、この学校でできることがありますよね」
ほくとの家庭事情を知っているのは、4年生担任の北崎と脇田のふたりだけである。いつもざわざわとしている夕暮れ時の職員室はしんとなった。その呼びかけに教職員たちの視線は脇田に集まった。
「せめて学校にいるときくらいは、ほくとを幸せな気持ちにしてやりませんか。頑張って、子供ひとりひとりが楽しいと思える学校をつくっていきましょう」
初めてその話を聞いた教職員たちは「そうだな」という感じで、黙って肯(うなず)いていた。
依然として子供たちは騒がしく、授業に集中していなかった。子供たちの状況の悪さに加えて、4月末に行われた家庭訪問では、子供の家庭事情まで担任の目が行き届いていないことが判明した。
家庭訪問があった日に、ある母親から脇田に苦情の電話がかかってきた。その母親は家庭訪問に訪れた担任から、「子供が宿題をやってこない。お風呂も入っていない。しっかり家庭教育をしてください」と言われたというのである。しかし、夜遅くまで働いているので、勉強を見ろと言われても見られない、子供と一緒に風呂に入る時間もないと母親は脇田に訴えた。
「ああ、こんなところに子供の指導が通じない原因があるのかな」
学校教育を行うのが学校の先生で、家庭教育を行うのは保護者だと割り切って考えている担任が多いのかもしれないと脇田は思った。
校区には、経済的に苦しい家庭やシングルマザーの家庭が少なくなかった。子供を見つめていれば、子供が背負っている生活の厳しさが見えてくる。そうであれば、保護者と会ったときに担任の口をついて出るのは、「しつけてください」ではなく、「頑張って育てておられますね」という言葉であってほしかった。
保護者に共感する担任の場合には、保護者と共同して子供を育てていくことができる。しかし、そうでない担任の場合には、親に対して平気で苦言を呈したりしてしまうので、保護者の反感を買ってしまう。こんなところにも指導の浸透力に差が出る要素が潜んでいるのである。思いがけず担任の指導力に対する懸念が表面化した。
「子供が背負っている生活の厳しさに目を向けてください。それに共感するところから指導を始めましょう」
家庭訪問を終えた日の終礼で、脇田が担任たちに厳しく釘を刺すという出来事も起きていたのである。
校長に就任して以来、脇田の寝つきは悪かった。ほくとの告白があった日の夜中には、「捨てられた」というほくとの言葉がリフレインして眠ることができなかった。

