提言|合田哲雄 教師という仕事の価値は下がるどころか、むしろ高まっている 【教師という仕事の価値を高め、失われた自信と信頼を取り戻すために 今、求められる教師像とは? #01】
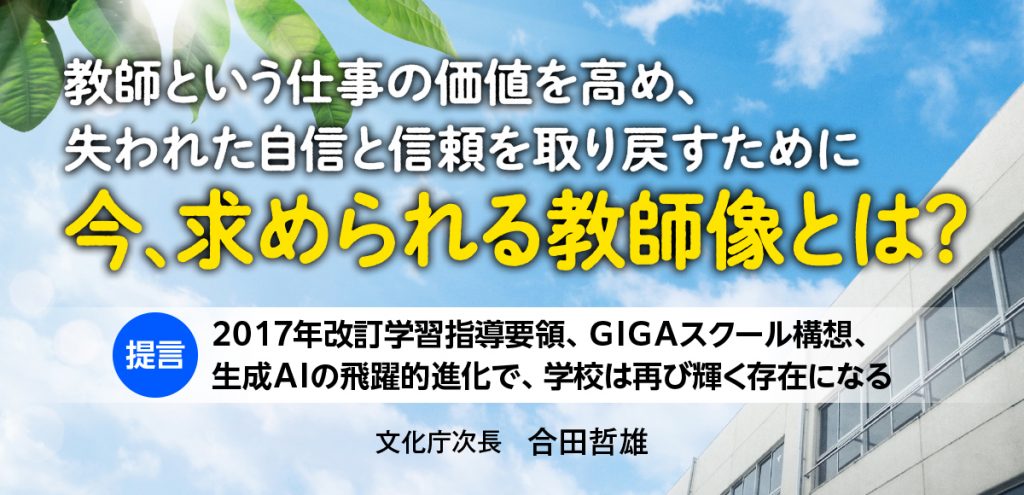
世間からは「学校はブラック」だと思われ、保護者対応の難しさから自信を失い、教師という仕事に対する価値が以前よりも下がったのではないかと、感じている方もいるのではないでしょうか。そこで、どうすればその価値を上げられるのかを考えてみることにしました。教師たちの失われた自信と信頼を取り戻すために、今、求められている教師像を明らかにする8回シリーズの第1回目です。今回は、現在の学習指導要領に書かれた内容を実現するために求められる教師像を明らかにします。二度の学習指導要領の改訂に携わり、現在は文化庁次長の合田哲雄さんに話を聞きました。

合田哲雄(ごうだ・てつお)
1970年生、岡山県倉敷市出身。1992年に旧文部省に入省し、初等中等教育局教育課程企画室長、NSF(全米科学財団)フェロー、高等教育局企画官、初中局教育課程課長、同財務課長、内閣府・審議官などを経て、2022年より現職。兵庫教育大学客員教授、東北大学講師。2008年、2017年の学習指導要領改訂を担当。東京都目黒区立小学校(3年間)、中学校(3年間)でPTA会長を経験。共著に『学校の未来はここから始まる』(教育開発研究所、2021)、単著に『学習指導要領の読み方・活かし方』(同、2019)がある。
目次
教師という仕事の価値は下がっていない
この特集のタイトルは「教師という仕事の価値を高めるために」とあります。その背景には教師の仕事の価値が下がっているという認識があるのかも知れませんが、私は教師という仕事の価値は全く下がっておらず、むしろ高まっていると思っています。私たち文部科学省の職員の仕事は、政治家や財務省主計局などに対して、資料や説明ぶりを工夫して説得し、教育や文化、学術やスポーツに対する投資を拡大することです。国会答弁もそのために行っていますし、デモクラシーの黒子としてこれらのロビイングや国会答弁を行うことについては一定の知識と経験があると自負しています。しかし、もし国会での答弁が終わった後に、「次は、近くの小学校へ行って、3年生の子どもたちの注目を引きつけ、知的関心を引き出し、深い学びとなる授業を行え」と指示されても、私には絶対にできません。自分にできないことができる人に敬意を払うのは当たり前のことではないでしょうか。発達の段階に応じて子どもたちの知的好奇心を刺激し、学びを深めていくという教師の専門性を私は心からリスペクトしていますし、それを教師の社会的な価値と呼ぶのなら、低下するどころか、ますます高まっていると思います。
教師に対して厳しく注文をつけたり、一方的に批判なさったりする方のなかには、教師とは誰にでもできる簡単な仕事だと思っているのかもしれませんが、30人や35人といった集団の子どもたちに対して、ゲストティーチャーではなく一定期間教諭としてご自分で授業をなさってみたらその難しさがお分かりになるのではないでしょうか。教師は、人が学ぶとはどういうことか、子どもの発達とは何かを押さえた上で、教科といった土俵の上で子どもと対話し、理解の質を高める専門職です。誰にでもできることではないですし、その専門性はますます大事になっています。認識を変えるべきなのは、私も含めた社会の側だと思います。文部科学省には、教師とは固有の専門性を持った専門職であることをより明確に発信し、その認識が社会において広範に共有されるように発信することが求められています。
社会構造の変化の中で、学校は再び輝けるのか
近代学校制度を定めた学制が発布されたのは1872年ですから、本年(2023年)は学制151年目にあたります。それまで存在していなかった近代的な社会制度としての「学校」が小さな労働力だった子どもたちを集めて学ばせることには、当時大きな違和感が生じたことでしょう。実際各地で「学制反対一揆」が起こりました。しかし、高田宏の小説『言葉の海へ』(新潮社、1984)が示すとおり、「新政府のなかでも異様なくらいの革新性を示していた」当時の文部省は、近代建築物、ホワイトカラーである教師、当時最先端のメディアだった活字の教科書・ノート・鉛筆・黒板・チョークなどでキラキラ感を演出し、義務教育就学率を途上国としては異例の早いスピードで高めました。また、司馬遼太郎が『坂の上の雲』(文藝春秋、1969)で指摘しているように、基本的に親と同じ職業にしか就けなかった封建社会とは異なり、学校で記憶力と根気があることを示せば親とは異なる仕事に就くことができて、自分の人生が変えられるという希望は我々の想像を越えた大きさで、学校を輝かせていたと思います。
ただ、記憶力と根気を示す方法としては、文字情報を読んで、ペーパーテストに鉛筆で答えを書くことが偏重されました。なぜならば、当時の技術水準ではそれが最も公正に採点できる方法だからです。その結果、子どもたちには、読むこと、書くこと以外に、話すこと、聞くことが得意だったり、音やダンスなど文字情報以外の表現方法に優れていたりと様々な特性や得意・不得意があるにもかかわらず、記憶力と根気を示す手段として、読むことと書くことが偏重されたことが今、生成AIの飛躍的進化といった社会の構造的変化のなかで、いろいろな意味でズレを生じさせていると思います。霞が関には、この『坂の上の雲』時代から150年間続いている「記憶力と根気競争」の勝者で溢れていますし、私も論理や概念など言葉が得意な特性がありますから、国会答弁といった仕事をなんとかこなせているのだと思います。ただ、全くの仮定の話ですが、明日から、立法府において大きな方針転換があり、政府参考人による国会答弁は身振り手振りや音楽、映像なども織り込んで行うことになったら、私は大いに苦戦することでしょう。
また、かつて輝いていた学校施設も最近まで、「公共施設で空調と洋式トイレとWi-Fiがないのは学校だけ」などと言われていました。しかし、2019年からGIGAスクール構想が動き出し、今はすべての子どもが情報端末を持っているわけですから、情報端末の普及という意味においてはいまや世界でトップクラスに躍り出ています。
そこに2022年末から生成AIの飛躍的進化という大波がきました。生成AIを学校においてどう使うかも大事な論点ですが、今のスマホと同じように生成AIが私たちの日常生活で当たり前のように使われる社会において、人間に求められている力に思いを致す必要があると思います。
それは、理化学研究所の中川裕志チームリーダーが指摘なさっておられるとおり(日本経済新聞、2023年5月8日付朝刊)、一つ目は、生成AIが紡いだ文章や情報の正否を判断する力です。生成AIは、正しい情報ではなくもっともらしい表現を生成しますから、誤りもありますし、偏りもあります。使う側の人間がその正否を判断しなくてはならず、そのためには、思考の軸や自分なりの知識の地図が必要です。
二つ目は、問いを立てる力です。生成AIはプロンプト、つまり、立てた問いによって答えが全く違ってきます。今までのように、与えられた問いにできるだけ短い時間で答えを出す力以上に、問いを立てる力が大事になってきます。
三つ目は、身体性で、AIになくて人間にあるものです。知性とは、脳以外の身体感覚が総合して生まれるものです。例えば、ふわふわしたぬいぐるみは触覚と視覚から人間の感情に影響を与え、その感情が言語となって表現されます。身体性に基づいて知性を生み出すのは人間の強みです。
四つ目は、対話から知性を生み出す力です。1人だけで考えるのではなく、対話、しかも相手との関係性を踏まえて対話することの中で、知性が生まれてくるからです。AIは、文章や発話は情報としかとらえていないので、そこから知性が生まれることはありません。
以上の四点は、生成AIが今のスマホのように当たり前になった時代に、子どもたちに必要なものであり、これらを育むには、2017年改訂の学習指導要領が重視している「主体的・対話的で深い学び」こそが必要です。
つまり、社会構造の変化の中で、「主体的・対話的で深い学び」を目指した2017年の学習指導要領改訂、2019年から動き出したGIGAスクール構想、2022年末から顕在化した生成AIの飛躍的進化という要素が揃ったなか、私は150年前と同様に、学校は再び輝く存在になれるし、ならなければならないと思っています。

