提言|赤坂真二 大学と学校は今、何を変える必要があるのか 【緊急検証! 教員のなり手不足問題、私はこう考える! #3】

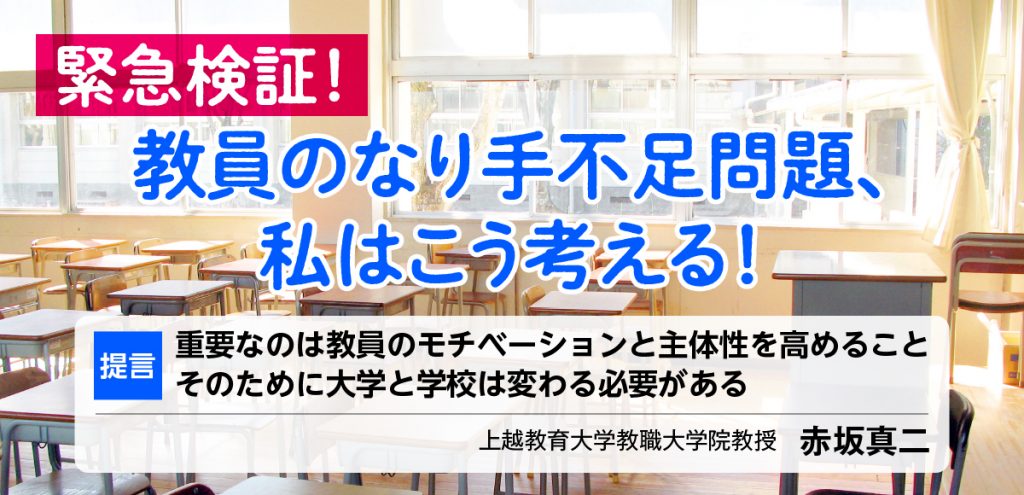
教員のなり手不足問題は深刻であり、日本の学校にとってその解決が目下の急務です。現在、文部科学省が進めている働き方改革や給特法に関する議論は確かに重要ではありますが、果たしてそれだけで解決となるでしょうか。教育関係者がその他にできること、するべきことは何かを考える7回シリーズの第3回目です。元小学校教諭で、現在は大学で現職教員や大学院生の指導を行っている上越教育大学の赤坂真二教授に話を聞きました。

赤坂真二(あかさか・しんじ)
新潟県生まれ。19年間の小学校での学級担任を経て2008年4月より現所属。現職教員や大学院生の指導を行う一方で、学校や自治体の教育改善のアドバイザーとして活動中。2018年3月より日本学級経営学会、共同代表理事。『学級経営大全』(明治図書出版、2020年)など著書多数。
■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全7回予定)
●提言|玉置崇 大学、教育委員会、学校が今、すべきことは?
●提言|川上康則 学校や教員が、今すぐ考えたい5つのこと
●提言|赤坂真二 大学と学校は今、何を変える必要があるのか(本記事)
目次
ハードルを下げることへの懸念
教員のなり手不足問題に対して、今行われている主な対策は、教員免許を取りやすくすること、教員採用試験を受けやすくすることなどであり、中には教員免許がなくても受験が可能になるケースもあるなど、受験コストを下げる方向へと向かっています。そうやって教員になるためのハードルを下げていくと、何が起きるでしょう。
結局、「受けやすい」という理由で教職を選ぶ、それ相応のモチベーションの方々が集まってくる可能性が高まるのではないでしょうか。その結果、教員になっても長続きしないことが考えられます。そうなると現場では短期で人が入れ替わることになりますから、教育実践の質が上がらなくなります。なぜそう言い切れるのかというと、子どもの変容は教員の一貫した、継続した働きかけによって高まっていく、というエビデンスが多数あるからです。
「受けやすさ」を重視する今の採用方針の陰に見え隠れするのは、各自治体の、とりあえず見掛け上の採用倍率を上げたいという意図です。そのような採用のしかたをしていて、現在の高レベルの学習指導要領で求められていることを実現できるのでしょうか。
教員のなり手不足問題を解消していくためには、ただ人数を集めればいいわけではなく、大事なことは、意欲があって、本気で教職に取り組みたい人たちを集めることです。そのために変わる必要があるのは、教員養成系の大学と学校です。具体的に何を変える必要があるのかを提案していきます。
大学の教員養成課程が変えるべき4つのこと
大学の教員養成課程に変えてほしいことはいくつかありますが、今日は4つお話しします。1つ目は、志を育てることです。なぜこれが必要なのかというと、「教師になること」を目的にしてはいけないからです。重要なのは、「何を成し遂げたいがために教師になるのか」です。しかし、実際は「教師になること」を目的化している学生が少なくありません。そのような人たちは、教師になった時点で目標を見失い、モチベーションが下がってしまいます。
それを防ぐ意味でも、大学では志を育てることを意識した目標設定をしていく必要があります。志とは、一生涯かけて貫きたい目標と捉えています。それははるか遠くにあるので、その前に小さな志がいくつかあって、それらを1個1個クリアしていくと、大きな志に近づいていく、という形が理想です。具体的には長期目標を立てたら、そこにたどりつくための短期目標を設定し、それに基づく実践をし、振り返り、新たな短期目標を設定し、実践、振り返り、これをサイクルとして繰り返しながら、志を育てていく、そういった教員養成過程にしていく必要があります。
さらに、現場には志を実践しようとしている教員や、志に向かって努力している教員がたくさんいます。そういう方々をゲストティーチャーとして大学に招いて学生に話をしてもらい、どんな志を描いて、どんなことを為そうとしているのか、そのために日々どんな努力をしているのかを学ぶ時間をつくってはどうでしょう。その人たちをロールモデルとして、志をもって何かを為していく教師のあり方を、学生が自分なりに考えていくカリキュラムがあるといいと思います。
2つ目は、大学で労働としての教職を学ぶ機会を作ることです。労働や給与など、教員のリアルについて学ぶ場が、今の大学のカリキュラムにはほとんどなく、学生はそれらを知らないまま教員になります。以前は各学校にある労働組合が、教員の勤務に関して知っておくべき情報を流してくれていたのですが、学校では労働組合の組織率が低下しています。それに伴い、労働に関する学習の機会が減っているのです。つまり、教員養成の段階でも、教員になってからも学ぶ機会がないので、労働や給与に関して、多くの教員は無頓着な状態になっています。実際に、教員の中には給特法の内容を知らない人が多いのです。知らないからこそ、「定額働かせ放題」のような、分かりやすくインパクトのある言葉が出てくると、それに便乗して「私たちは損をしている」と言いだし、被害者のような気持ちになりがちです。
例えば、給特法は諸悪の根源のような言い方をされることが多いですが、そもそも教員の時間外勤務にどう対応するかという発想から、教員の権利を守るために作られたものです。それが、現状の働き方に合わなくなっているから、「定額働かせ放題」になっているのです。それならば、どこに問題があって、どう変えればいいのかを教員が自分たちで考える必要がありますし、働き方を改善していく必要があるはずです。しかし、無知であるがゆえに、知らず知らずのうちに現状維持バイアスがかかっていて、自分たちでなんとかしようという意識にはなっていかないのです。
公立学校の教育公務員の勤務時間や勤務条件は、一部の規定を除き、労働基準法が適用されます。1日8時間、週40時間以上の勤務を上限に定め、それ以上働かせると使用者、つまり管理職は罰則対象になります。もしもすべての教員が、このことを知っていたらブラック化は起こらなかったかもしれません。このことを知って管理職になっていたら、それを前提とした学校づくりをしたのではないでしょうか。
このように労働や給与、権利などに関する無知が、ブラック状況の温存に一役買っているのではないでしょうか。つまり、教員の勤務のブラック体質は養成課程から始まっていて、それを温存、維持するための仕組みができてしまっているのです。
この現状を変えるためにも、教員養成課程で労働や給与、権利について学ぶ必要があります。それで終わりではなく、すでに様々な努力によって、ブラック状態を克服しようとしている学校はどの地域にもあるでしょうから、そのような学校の関係者から話を聞くなどして、勤務状態の改善の方法を知り、自分に何ができるかを考えるような演習をすることもできるでしょう。
3つ目は、子どもの発達をカリキュラムの中心に据えることです。教員養成課程には、教職コアカリキュラムと呼ばれるものがあり、2019年度から教員免許を取得するためには必ず履修しなくてはならなくなりました。その単位数を見てみますと、圧倒的に教科指導の授業が多いのです。例えば、特別支援教育に関する授業は、一種免許の場合、59単位中、たった1単位です。つまり、そのほとんどの単位数が、教科の指導法にあてられていて、その指導法に合わない子どもたちは、ダメな子、できない子、不適切な子とされてしまうのです。
ところが、発達を元に子どもを見ると見方が変わります。言われたことができない、 駄々をこねる、不適切な行動をする、などの行為はすべて発達の課題として捉え直すことができます。子どもが新しい壁にぶつかったときに、彼らがそれを乗り越えるために、教員に何ができるのか、その考え方と方法を学ぶことができます。
教員が効果的な発達支援ができるようになれば、子どもとの関係が良くなるでしょう。なぜなら、子どもの問題行動に対して、叱ったり注意をしたりするのではなく、発達を支援し、成長を促すという発想に変わるからです。一人一人の子どもに向き合い、その成長に寄り添えることは、間違いなく教員のモチベーションの向上につながります。教員が子どもに寄り添っていけば、当然、その保護者との関係も良くなります。子どもの発達を支援し、成長に寄り添い、助言してくれる教員に対して、保護者は信頼を寄せるからです。
今後、私たちが発想の転換をしなければならないのは、「教育者の専門性」についてです。これまでは教科指導法をたくさん知っているなど、教科、教材に対して詳しい教員が「専門性が高い」とされてきました。それが今は、個々の子どもをいかに育てるかが大事な時代になっています。これからの教員養成課程は、発達心理学、教育心理学、教育学など学習者の研究をカリキュラムの中心に据え、「教えること」だけでなく「育てること」に対する「専門性」を育てるべきではないでしょうか。
4つ目は、教育実習を変えることです。今の教育実習の問題点は、学生がお客様のような扱いをされていることです。例えば、学級経営が比較的うまくいっているクラスに配置された学生は、そこで授業をさせてもらい、子どもから「先生、先生」と慕われて感動して帰ってきますが、自分が担任になったときに、そのときの経験はあまり役に立たないかもしれません。なぜなら、新採用の教員が最初からそのような素晴らしいクラスをつくれるものではないからです。彼らが担任になったときに役立つような、もっと実践的な内容を学べるようにする必要があります。
ポイントは、チーム型にすることと、問題解決に取り組むことです。
教育実習の担当授業時数は今と同じぐらいでいいので、期間を2か月ぐらいに延ばしてはどうでしょう。そして、教育実習生の育成に対して意欲とスキルを持っている教師を指導教員として、その指導教員の学級に5、6名の教育実習生を配置し、複数の学生が一緒に学ぶのです。1日の実習が終わると、実習部屋に教育実習生が集まり、指導教員を中心にみんなで1日を振り返り、こうだった、ああだったと話し合いながら、うまくいったこと、うまくいかなかったことなどを整理し、翌日、実際にやってみるのです。
それに加えて、指導教員から、「このクラスにはこういう問題があるんだけど……」「授業でこういう課題があるんだけど……」などの課題をもらい、他の実習生たちと意見交換をしながら、実際に問題解決をしていきます。それによって、「自分もうまくいかないことがあるかもしれないけど、こういう風にすれば解決できるんだ」という問題解決方略を学べるので、教育実習生はある程度のモチベーションを維持したまま、教職の道に進んでくれるはずです。

