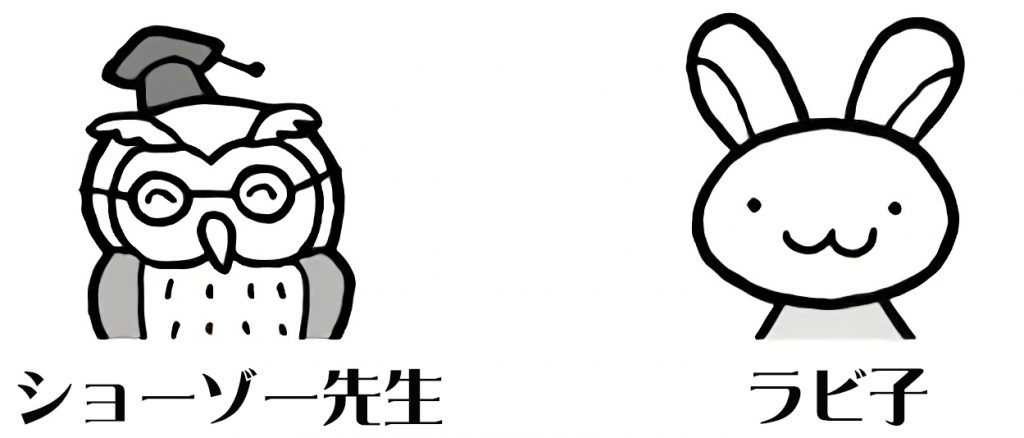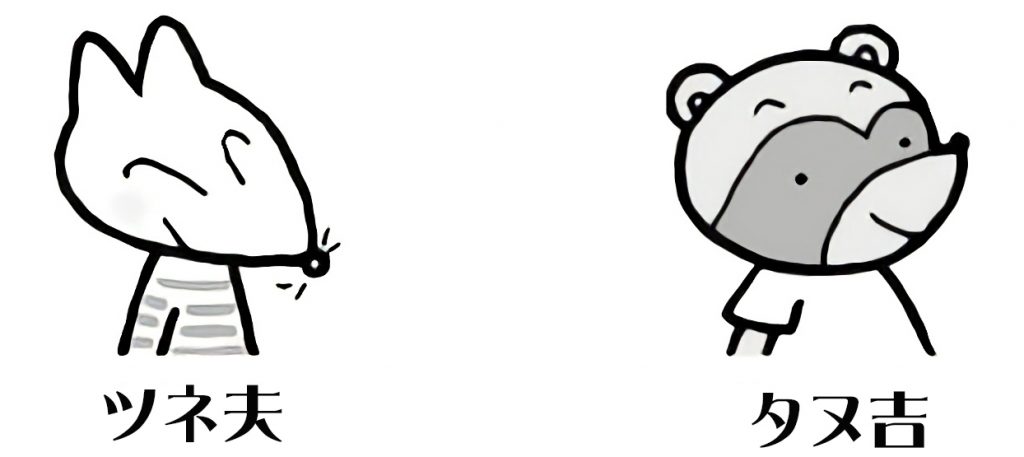菊池省三の教師力UP道場:「15分1セット構成力」で授業が変わる!
- 連載
- 菊池省三の教師力UP道場

菊池省三先生が伝説の授業の達人(鳥?)であるフクロウのショーゾー先生となって、ラビ子・ツネ夫・タヌ吉の3人、いえ3匹の教師のタマゴたちに「生きた授業技術」を伝授するお話。第7回は、「1時間」(1単位時間)を見通した授業力についてのお話。45分を15分1セット×3 として授業を組み立てることがコツだと、ショーゾー先生は言います。
監修/菊池省三
きくち・しょうぞう。1959年愛知県生まれ。2014年度まで福岡県北九州市の小学校教諭を務め、退職。現在、教育実践研究サークル「菊池道場」主催、高知県いの町教育特使、教育実践研究家。『菊池省三の学級づくり方程式』(小学館)ほか著書多数。

目次
スモールステップで学ぶ「授業ライブ力」とは!?
みなさんは、今の授業に満足していますか?
大学や初任者研修などで学んだ教育技術だけでは不十分だと感じたことはありませんか?
もっと子どもたちを引きつける充実した授業をつくりたいと思いませんか?
ラビ子、ツネ夫、タヌ吉の3人、いえ3匹も、そんな思いをもっている教師のタマゴたちです。
この連載は、3匹が「森の大学」の伝説の授業の達人(鳥?)であるフクロウのショーゾー先生のもとで、大学では学びきれなかった「生きた授業技術」を悪戦苦闘しながら学んでいくお話です。