ほめ方、𠮟り方について教えてください(前編)【教師の悩みにピンポイント・アドバイス 田村学教授の「快答乱麻!」#9】

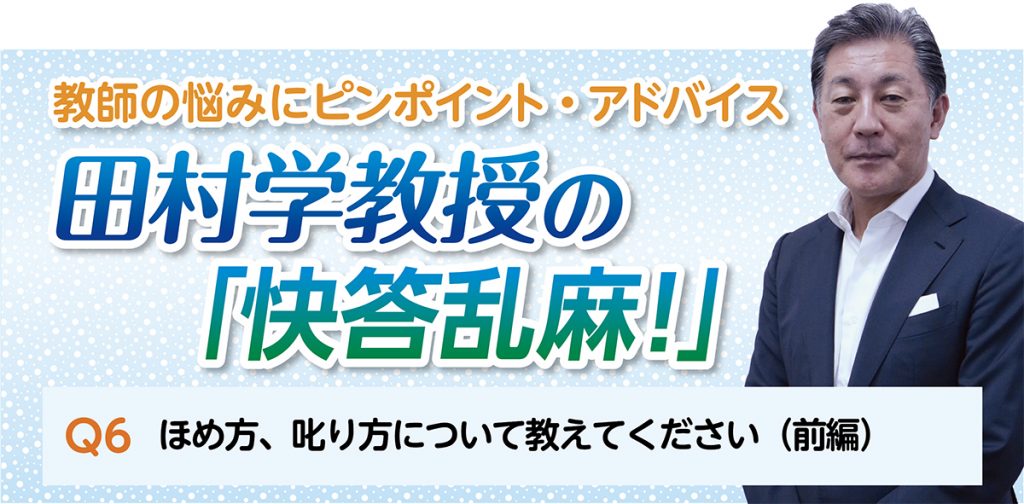
先生方のご相談について、國學院大學の田村学教授にお答えいただくこの企画。今回は、子供のほめ方、叱り方をどうしたらよいか考えている先生のご質問に対して「快答」していただきます。
※
Q6 昨年度、同じ学年を組んでいた先生はとても厳しい方で、授業中によく隣の教室から子供を叱る(怒る?)大きな声が響いていました。そのたびに、「ああ、あんなに厳しく叱らなくてもいいのに。私はなるべく子供たちをほめて育てたい」と思っていました。ただ、子供たちを成長させるには叱ることが必要な場面もあると思います。そこで、子供たちを伸ばしていくための、ほめ方、叱り方について教えてください。(20代・小学校)
プロセスをほめ、尺度を決めてから叱る
A ほめ方、叱り方について考えるためには、まず、なぜほめたり叱ったりするのかについて考えることが必要でしょう。我々が教育を行う過程で、なぜ子供たちをほめたり叱ったりするのでしょうか? それは、子供たちに期待する行動や行為を安定的、持続的にしてほしいと願うからでしょう。例えば、「誰とでも仲良くする」というような、期待する好ましい行動がいつでもできたほうがよいし、その先もずっと継続的にできたほうがよいのです。そのために、ほめたり、叱ったりするわけですよね。
そのように、子供も含めた私たちの行為がより安定的で持続的なものになるにはポイントが2点あると思います。それは自覚と実感です。
まず一つには、自分のどういう振る舞いや行為が適切で望ましいのかということを、本人が自覚していなければおそらく再現はできないわけです。「いろんな人と仲良くできていたよね」と自分自身が気付いて分かっていなければ、持続的に再現はできないわけです。もう一つは実感ですが、(望ましいと考えられている)行為を行ったときに、楽しかった、嬉しかった、気持ちがよかった、心地よかったなどの、快適な状態だという手応えをつかめることが重要です。
つまり期待される、望ましい行動をしたことを子供自身が自覚し、そこに好ましい手応えが付与されると、そういう望ましい行為をまたしてみようとか、もっとやってみたいという態度化が生まれてくるのだと思います。多分、私たちはそれを期待して、子供たちをほめたり、(それとは逆の行為に対して)叱ったりしているのではないでしょうか。
そう考えると、ほめることは大事だし、時には叱ることも必要なのだけれど、基本的には自分の行為が自覚でき、そこに手応えを付与したいわけですから、ほめられるほうが子供にとってよいだろうと考えられます。ですから、第一優先としては、まずほめることを増やしましょうということになるわけです。

その上で、具体的にどのようにほめたらよいかを考えてみましょう。
最初に、自覚と実感という原理にのっとって考えてみると、まずほめるときには具体的であることが大事だと思います。子供自身が何をほめられているのか分かるということです。自分の行為のどういうところが期待されているのか、自覚できるからこそ再現も可能になるわけです。先生はほめているのだけれど、本人は何をほめられているのか分からなければ、自覚できないし、実感ももてません。それでは再現はできないですよね。
次に、結果や成果(プロダクト)よりも過程(プロセス)をほめることが大事だと思います。できた、できないよりも、そこに至る過程で、子供が繰り返し取り組んだとか、自ら挑戦し続けているという過程を評価してほめることが大事だと思います。もちろん、最終的な結果もほめたほうがよいと思いますが、途中にある取組や行為をほめてあげることができると、教師にとってもほめる対象が広がりますし、何よりも子供にとっても最終的な結果だけではないものが価値として見いだせると思います。一生懸命がんばってもできないことはありますし、実際に「毎日チャレンジしたけれど、逆上がりはできなかった」という子供だっているでしょう。そうすると、できた、できないの判断だけでほめたのでは、余りにも表面的で薄っぺらなものになってしまいます。ですから、過程をほめることが大事になってくるわけです。
加えてもう一つ、ほめるときに良し悪しでほめるのではなく、教師としてとても嬉しいというように気持ちを付随させるほめ方がよいだろうと思います。善悪を判断するのではなく、「そんなふうにがんばってきたことは、とてもすてきだよね」とか、「何度も失敗したけれど諦めずに挑戦していて、かっこいいと思ったよ」というようなほめられ方をしたほうが、「あなたのやったことは正しいよ」とほめられるよりも、子供たちは嬉しいはずだと思います。とりわけ子供たちを日々見続けていて、信頼もあるはずの先生から、そのようにほめられたほうが、嬉しくて「また、がんばろう」という気持ちになるのではないでしょうか。

