提言|川上康則 学校管理職に気づいて欲しいのは「学校が子どもに合わせる時代」になったこと 【発達障害8.8%をどう受け止めるか #1】

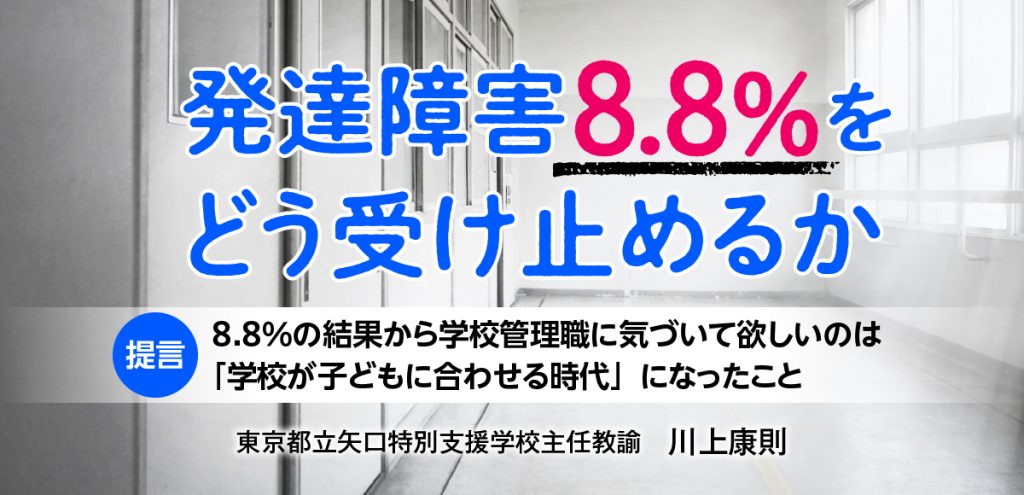
「通常学級の小中学生の8.8%に発達障害の可能性」という調査結果を専門家たちはどう受け止めているのかを知り、学校の未来を考える7回シリーズの第1回目です。特別支援学校の教員として障害のある子どもに関わりながら、特別支援教育のあり方を問い続けてきた川上康則さんに聞きました。

川上康則(かわかみ・やすのり)
1974年、東京都生まれ。公認心理師、臨床発達心理士、特別支援教育士スーパーバイザー。障害のある子どもたちに対する教育実践を積むとともに、小中学校等からの相談にも応じている。主な著書に「教室マルトリートメント」(東洋館出版社、2022年)、共著に「一人一人違う子どもたちに『伝わる』学級づくりを本気で考える」(明治図書出版、2023年)などがある。
■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全7回予定)
●提言|川上康則 学校管理職に気づいて欲しいのは「学校が子どもに合わせる時代」になったこと(本記事)
目次
気になるのは残りの91.2%の子どもたち
通常学級の小中学生のうち、「8.8%に発達障害の可能性」という調査結果が出ましたが、この数値自体は妥当なのではないかと感じます。だからといって、8.8%の子どもたちに対して特別支援教育の個別対応をすれば、それだけで学級の運営がうまくいくわけではありません。私が気になるのは、「残りの91.2%の子どもたちには発達や成長についてのニーズがない」と勘違いされてはいないだろうか、ということです。彼らも教師からの温かなまなざしや、前向きな言葉を求めています。この子どもたちに対して、十分な対応ができていると言えるでしょうか。そうでなければ学校という枠からはみ出る子どもが、今後はもっと増えるだろうと思います。
子どもたちの姿は多様化・複雑化しています。今回の調査では、8.8%を構成している発達障害として、学習障害(限局性学習症)、ADHD(注意欠陥・多動性障害)、ASD(自閉スペクトラム症)などを捉えていますが、今回の質問項目には場面緘黙、吃音症、不安障害、気分障害、愛着障害、発達性協調運動症(DCD)、起立性調節障害(OD)などの子どもが含まれていません。このほかにも、LGBTQ、外国にルーツがある、ヤングケアラー、不登校、ゲーム依存、ネット依存などの要素を持つ子どももいます。保護者がギャンブル依存やアルコール依存のケースもありますし、生活保護世帯の子どももいます。これらの多様な子どもに対して、現場の対応が追い付いていないと感じます。
おそらく、多くの先生たちの心の中に「最近は学校に合わせられない子どもが増えた」という意識があるのではないかと思うのですが、そうではなく、今の子どもたちの姿に、学校が合っていないという事実をもっと真剣に考えないといけないと思います。子どもたちが学校に合わせるのではなく、学校が子どもに合わせていかなければいけない時代になったのです。学校は対応力をもっと高めていく必要があります。
特別支援教育の個別対応だけをしても問題は解決しない
まずは学級担任が対応力を高めるためのポイントを4つご紹介します。一つ目は、集団的なアプローチの仕方を変えることです。
発達障害の子どもたちに問題が生じやすい状況として、主に4つの場面が考えられます。
①全体を一斉に動かそうとすると、時間やペースのずれが出やすい
②同じレベルのものを求めると、能力差が出やすい
③みんなが協力しなければならないときに、相手に合わせることの苦手さが出やすい
④挙手指名で一人の意見を求めるときに、待てない子ども、自分とは無関係と思ってしまう子どもが出やすい
このように集団的なアプローチを取るときほど問題が生じやすいのではないでしょうか。そうだとすれば、発達障害の子どもに対してだけ特別支援教育の個別対応をしても何も解決しないのです。見直す必要があるのは、集団的なアプローチの仕方です。
今まで先生たちは、集団的なアプローチを取るときには、学級の中間層に焦点を当てていたと思うのですが、そうすると、枠から外れる子ども、はみ出す子どもが必ず出てきます。例えば、授業中、理解が早くて「浮きこぼれ」てしまう子どもは退屈し、自分の能力の高さを利用して周りをコントロールしようとすることがあります。授業を潰したり、いじめをしたりするのです。その一方で、授業についていけない子どもたちは、分からないし、恥ずかしいという思いから、努力しない方向に向かいます。「どうせ頑張ったってうまくいかない」という気持ちが強くなり、努力が報われなければ努力そのものをしなくなっていきます。どちらのタイプの子どもも放置してはいけないのですが、彼らを枠にはめようとすればするほど、先生たちは苦しくなります。ここは発想を変えて、中間層ではなく、そこから外れている子どもたちに焦点を当てて、彼らをつなぐ授業をしてみてはどうでしょうか。
例えば、挙手指名というスタイルで、「この問題の答えが分かる人」と言ったときに、ほぼ全員の子どもの手が上がったとします。そのときは、「全員立ちましょう。隣の子と30秒話してみてください」と、一気にガス抜きをする方法があります。「分からない」と言っている子どもがいたら、「分からないと正直に言えるのは素晴らしいよ」という話から始めて、「皆でわからなさを解決していこう」というふうに授業をシフトしていくのもいいでしょう。
学級担任の対応力を高めるポイントの二つ目は、先述の通り、8.8%以外の91.2%の子どもが大事にされているのかを確認することです。例えば、先生に一声掛けて欲しい、先生ともっとコミュニケーションをとりたい、友だちと良好な関係をつくりたいなど、すべての子どもが持っている発達ニーズに学級担任は十分に応じているでしょうか。もっといえば、クラスの子どもたちが信頼関係で結ばれているかどうか、何かをやらせるのではなくて子どもがやりたくなるような授業になっているかどうか、一人一人がそのクラスで必要とされているかどうか、それらがベースとなります。その部分に十分な対応をしないで、8.8%の子どもだけに個別対応をしても、空回りするに決まっています。
ポイントの三つ目は、障害の有無には関係なく、すべての子どもとの瞬間の関わりを大事にすることです。マックス・ヴァン・マーネンという教育学者は、「教育的瞬間」という言葉を使っていますが、その瞬間ごとに、「今、この先生にこのような声をかけて欲しい」、「今、この先生にこのように関わってほしい」などの、子ども側のニーズがあります。一方で、先生側にも、「この頑張りを認め、声をかけてあげたい」、「失敗から立ち直ろうとしているときに応援してあげたい」などと感じる瞬間があると思うのです。そのような子どもとの瞬間の関わりを逃さないことが重要であり、瞬間のニーズを満たしていくことの延長線上に、特別支援教育があります。
四つ目として、学級担任に改善を求めたいことを付け加えておきます。それは、職員室での先生同士の会話の中でありがちなことなのですが、特定の子どもを「障害名+ちゃん付け」で呼ぶことは、すぐにやめてほしいのです。例えば、「自閉ちゃん」などと、揶揄するような言い方をする方がいます。親しみを込めているつもりなのかもしれませんが、大抵は適切な関わりができていないときに、それを隠すために使われています。うまくいかないことがあったときに、その子どものせいにするのは絶対にしてはいけないことです。職員室内での会話は、先生自身のマインドを作り上げますし、子どもたちの前に出たときの行動にも現れます。職員室では、子どもや保護者に対するリスペクトを忘れずに発言してもらいたいのです。

