Q2 自分の授業力向上に生かすための研究授業の見方は?(後編)【教師の悩みにピンポイント・アドバイス 田村学教授の「快答乱麻!」#4】

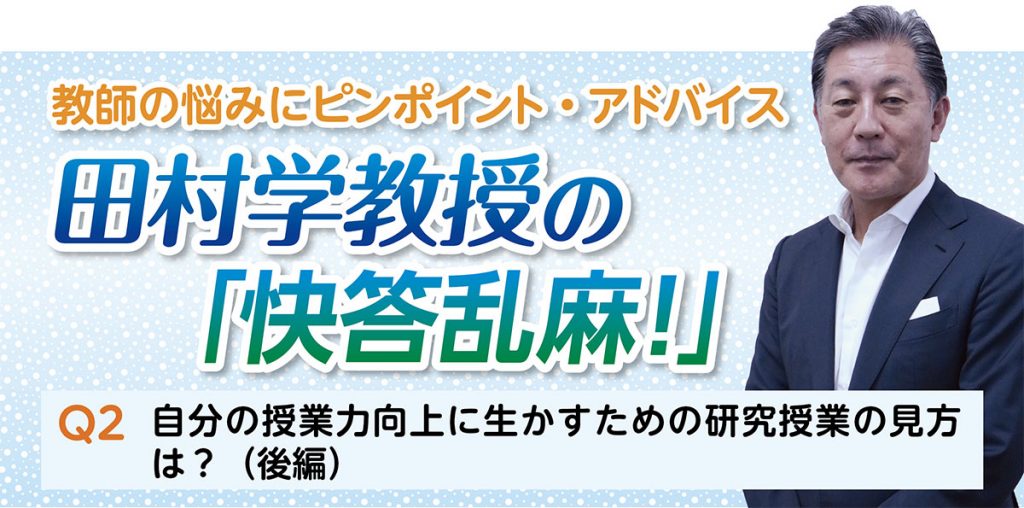
先生方のご相談について、國學院大學の田村学教授にお答えいただくこの企画。今回も研究授業の見方と、それを自分の授業に生かすための方法について「快答」していただきます。
※
Q2 コロナ禍以降、中止、縮小傾向だった研究会が、昨年から徐々に再開され、研究授業を参観する機会も増えてきました。毎回、研究の協議にも参加して学んでいるつもりですが、それがはたして自分の力になっているのか今一つ実感が湧きません。そこで教えていただきたいのですが、研究授業を見るときに、何をどこからどのように見て、どう記録・活用すれば、自分の授業力向上に生かすことができるのでしょうか?(小学校・20代)
子供の姿を見とりつつ、そこでの言動を子細に記録することが大切
A 前回は研究授業の場において、何のために何をどこから見るかといったことをお話ししましたが、今回は、研究授業の場をきちんと先生自身の力量形成の場にするために、何をしていけばよいかについて話をしていきたいと思います。
前回、子供の姿を見とることが第一優先だとお話をしました。しかし、ただ見ていても45分なり50分なりで子供たちに起こる多様な出来事を、すベて記憶していくことは不可能です。ですからまず、子供の姿をていねいに見とるとともに、そこで見た言動を子細に記録していくことが大切だと思います。それは、指導案のわきにちょっとメモを取るというレベルではなく、ノートや用意した白紙などに先生が何と言って、それに対して子供が何を言い、どんな様子だったかといったことを可能な限り詳細に残していくということです。そうして、書いて、書いて、書いていくうちに、次第に子供の学びの様子が見えてくるようになるはずです。
その記録は当然、授業後の協議会で必要な資料になりますから、時間軸に沿って、教師の行為と子供の言動を記していきます。そこには子供の固有名詞があったほうがよいでしょう。やはり、誰がどう言ったのかが分からないまま、何となく「こんな感じのことを誰かが言っていたよね」と言ってみても、なかなか分析には寄与しません。ですからもし名前が分からなければ、どの席の子がということを記しておけばよいと思います。その記録を基にしながら、協議会の場で、「このときAさんが(あるいは窓側の前から何番目の席の子が)こう語ったよね。その後、先生からこんな問い返しがあり、全体の対話の場でBさんの意見にこう同意していて、学習のまとめでは、ノートにこんなふうに考えを記していたね」というように話していくわけです。端的に言えば、協議会の場では固有名詞と事実で語るということが重要だということですね。
そうでなければ、協議が互いの勝手なイメージや想像をぶつけ合う空中戦のようなものになってしまいます。「きっと、こうだったんだろうね」というような想像の話に終始したのでは、分析できないわけです。だからこそ、時間軸に沿って、固有名詞(あるいはそれが分かる座席)を残しながら、可能な限り詳細に事実を記録していくわけです。


