リレー連載「一枚画像道徳」のススメ #35 「だれでもピアノ」開発に込められた思い|肥後漱一郎 先生(埼玉県公立小学校)

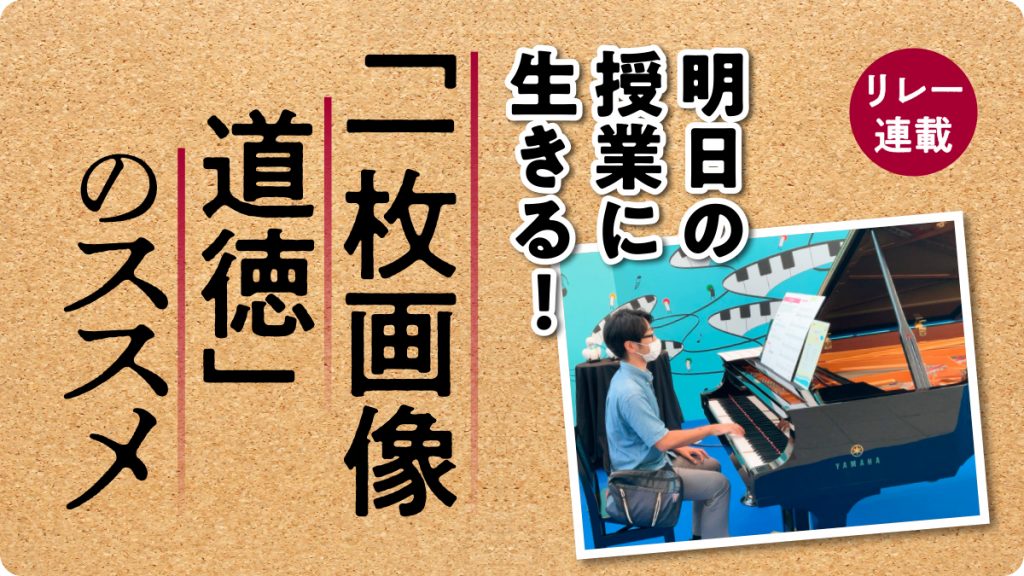
子供たちに1枚の画像を提示することから始まる15分程度の道徳授業をつくり、そのユニットをカリキュラム・マネジメントのハブとして機能させ、教科横断的な学びを促す……。そうした「一枚画像道徳」実践について、具体的な展開例を示しつつ提案する毎週公開のリレー連載。今週は肥後漱一郎先生のご執筆でお届けします。
執筆/埼玉県戸田市立笹目東小学校教諭・肥後漱一郎
編集委員/北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和
目次
1 はじめに
はじめに、実践を考えるきっかけとなった授業についてお話しさせてください。
それは、第4学年「総合」の研究授業での出来事です。テーマは福祉。
「肢体不自由な方の生活をよりよくするために、私たちができることはなんだろう」ということを考えていました。
子供たちは両手を思うように動かせない人のために、口に装着することで手が使えなくても字を書くことができるようになるマスクなどを考案し、実際に工作をしていました。
音楽の授業で関わっている子供たちが、「障がいのある人に役立つものをつくりたい!」と真剣に学習に取り組む姿に感動しました。そして、「総合」の学びに繋がるような授業をしたいと思いました。
子供たちが真剣に学習する姿に加えて、授業を考える大きな原動力になったものがあります。
それは、研究授業後の研究協議会で話題となった内容です。
【子供たちの発明は本当に肢体不自由な方が望んでいるものなのだろうか】【健常者の私たちが、頭の中で想像した障がい者像をもとにして「かわいそうだから助けてあげよう」という考えで学習を進めてしまっているのではないか】という課題が生まれました。
課題を解決していくための代案の一つとして、「肢体不自由な方をサポートする製品を発明した人の話を聴く」というものがありました。
そこで、障がいのある人でも自分一人で演奏できるピアノ【だれでもピアノⓇ】を開発された新井鷗子さんにインタビューをさせていただきました。
これからご紹介する実践は、新井さんへのインタビューや執筆された書籍をもとに考えています。
「総合」「道徳」「音楽」をつなぐ実践として参考にしていただければ幸いです。
2 授業の実際〜「だれでもピアノ」Ⓡ開発に込められた思い〜
対象:小学4年
主題名:「だれでもピアノ」開発に込められた思い
内容項目:B-10 相互理解
以下の写真を提示します。

写真を提示すると、「先生が写ってる!!」「ピアノを弾いてる!」といった声がありました。
「この写真に写っているピアノは、笹目東小学校の音楽室にあるピアノとは違う特別なピアノなんだよ。先生が体験してきた動画があるから見てみよう」と以下の動画を見せます。
「すごい!ピアノが自動で動いてる!」
「先生は右手しかつかってないのに……!」
上記のようなことに気付いていました。
発問1 このピアノの名前はなんでしょう? ○○○○ピアノの○○○○に当てはまる言葉はなんだと思いますか?
●かんたんピアノ
●ゆうれいピアノ
●マジックピアノ
●自動演奏ピアノ
●だれでもピアノ
このような答えが返ってきました。
動画を見た子供たちから「先生には見えない腕があるんですか?笑」という反応があるくらい、ピアノの鍵盤が自動で動いていることに驚きがある様子でした。
その驚きが子供たちが考えたピアノの名前に反映されているなと感じます。子供の考えを聞きながら、以下のように説明をしました。
説明
●「だれでもピアノ」Ⓡという名前であること。
●2015年に東京藝術大学の教員だった新井鷗子さんらが開発を始めたということ。
●「だれでもピアノ」は、宇佐美 希和さん(当時、桐が丘特別支援学校の生徒であった)との出会いをきっかけに開発が始まったこと。
「みんなは総合の時間に、思うように体を動かすことのできない人の役に立つものをつくろうとがんばっているよね。新井さんは、障がいのある方でも自分一人で演奏できる楽器をつくろうとしたんだよ。」
子供たちが総合で学習していることを想起させたうえで、次のように発問しました。
発問2 新井さんは障がいのある方が自分一人で演奏できる楽器を開発するにあたって、筑波大学附属桐が丘特別支援学校の生徒さんたちに会いに行ったそうです。新井さんは、「生徒さんとの出会いを事件と呼ぶほど衝撃を受けた」と語っていました。それはなぜだと思いますか?
●肢体不自由ではないので、障がいのある人の辛さや大変さを理解していなかったから。
●生徒さん(宇佐美 希和さん)が「体を自由に動かせないけど、ピアノを弾きたい!」 と思っていたから。
●思うように指を動かせない姿が可哀そうだと衝撃を受けたから。
ただ驚いたのではなく「事件と呼ぶほど驚いた」という表現から、子供たちは「なんでだろう?」と考えを広げようとしていました。子供たちとのやり取りのあと、新井さんがどうして事件と呼ぶほどの衝撃を受けたのかを伝えるために、以下の教材文を配布します。
教材文を読んだ後に、次のように説明しました。
「新井さんは、思うように体を動かすことができない障がいのある人が、プロと同じ楽器のピアノを演奏することは難しいだろう……と考えて、ピアノは開発対象から外していたんだね。だからこそ、『ピアノを弾きたい!』という宇佐美さんの強い思いに衝撃を受けたそうなんだ。」
【はじめに】で述べましたが、子供たちは総合の授業で「障がいのある人に役立つものをつくりたい!」と学習に取り組んでいます。
しかし「それは本当に障がいのある人が強く望んでいるものなのか……」という相手意識が不足しているのではないかという課題がありました。
発問2は、そんな子供たちに対して、新井さんが開発をするにあたって相手意識を強く抱いた出来事について伝えたいと思って考えたものです。

