師を持ち、師に学ぶ ー最も有効な修業法ー【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第34回】

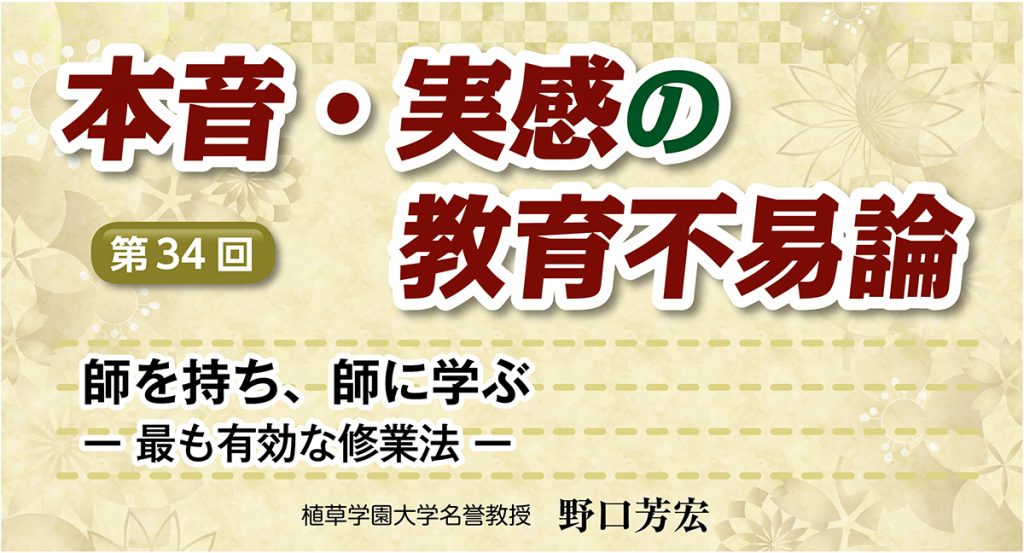
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第34回は、【師を持ち、師に学ぶ ー最も有効な修業法ー】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。
目次
1 自己成長の三原則
名言、至言というものは共通して短い。簡潔、明快、的を射て確かだ。時空を超えて不変、不動の真理を説いている。
誠実な人ならば例外なく、常に自分の成長、向上を志し、願っているに違いない。それが実行、実現に至らぬことはあるにしても願いとして、希望としてそう思わない者はあるまい。少しでも向上をと考えることが人生に対する誠実なあり方だとも言えよう。
その原理、原則、鉄則とも言うべき名言の一つが次である。「修業三原則」とも言うべき至言と私は考えている。
良き師、良き友、良き書物
この順序は必ずしもその重要度を示すという訳ではないかもしれない。「師、友、書物」という語の配列は、一音、二音、三音の順である。これは日本人の音律的美意識に合うものらしく、短い音数の語を先行させ、長い音数の語を後に持っていく例が多いようだ。「左右」は「さ・ゆう」と、一、二音の順、これが訓読みになると「みぎ・ひだり」となって二、三音の順になる。「とう・ざい」は同音数だが、訓読みになると「にし・ひがし」と二、三音の順になる。「なん・ぼく」も同様で「きた・みなみ」の方が落ちついて聞こえる。「早寝、早起き、朝御飯」は、三、四、五音の順である。
このように語の順序が、必ずしも優劣、軽重の順を表しているとは限らないようである。
先の修業の三原則もこの伝に従えば、あるいは、語呂の響きを大事にした配列かもしれない。だが、私の経験的実感からすると、先の三者の最重要則は筆頭の「師」に間違いないということになる。目の前の、まさに生き、考え、話している師との出合いほど自分にとって大きな影響を与えてくれる存在はない、というのが私の今や確信とも言える考えである。
そのように考えるに至った経緯や思い出を綴って参考に供したい。これまた紛れもなく「本音・実感の教育不易論」の一つである。
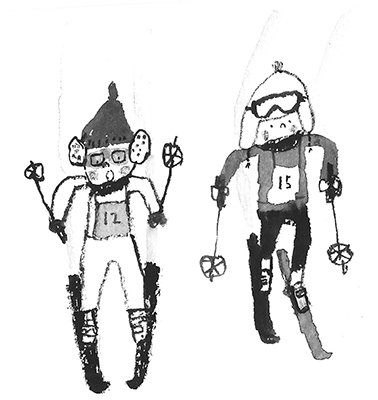
2 小、中、高等学校の教員と大学教員の違い
小、中、高等学校では一般に「教諭」また教頭、副校長、校長、大学では、講師、准教授、教授などと称される。これらは「職名」「職位」であって、これらを全て含めた法律用語では「教員」と言われている。私の職場は小学校だけで、教諭、教頭、校長を歴任して退職した。定年退職後引き続いて北海道教育大学に国語教育の教授として職を奉ずることとなった。
38年間に及ぶ小学校教員生活に終止符を打ち、初任者として大学教員になったのだが、一体この両者は、同じ教員という法的身分を有しながら、どんなところに違いがあるのだろうか、と強い関心を抱いた。いつもそんなことを考えながら暮らしている内に、やがて私なりに三つの相違点があることに気がついた。一つは「師の有無」、二つめは「休日でも出勤する人の多少」、三つめは、妙な言い方だが「納得の違い」である。
一つめについては後述するので、それ以外のことはごく簡単に述べたい。「休日でも出勤」については、大学の教員は大きく「研究」と「教育」という二つの役割を持っているが、一般的には前者の方に重点が置かれている。これが、大学人が「研究者」とも呼ばれる所以であり、大学人としての業績はその「研究」によって評価されることが多い。自分の研究の推進には曜日や休日などは二の次になる。必要とあらば夜中でも、元日でも大学に行くことになる。
小、中、高の教員は「出勤日」には出勤するが、休業日には一般的に学校には行かない。自己目的というよりは、法的規制によって出勤や在宅が決められているから当然だ。
三つめの「納得の違い」というのは、研究者の生命とも言えよう。本当に納得するまでは退かないし、同意しない。そこにいくと小、中、高の教員は比較的物分かりがよく、「分かりました」と言うことが多い。あまりよく分からなくてもこう言う場合もある。これは功罪半ばすることとも言えるが、ここでは深入りはしない。

