読み書き「同時学習」か「分離学習」か ー石井方式を阻む閉鎖性ー【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第33回】

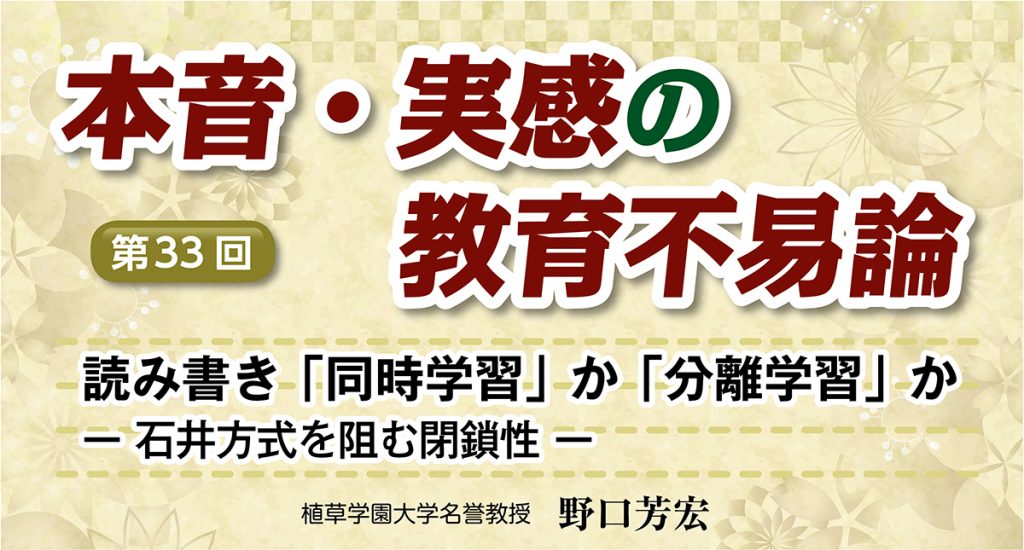
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第33回は、【読み書き「同時学習」か「分離学習」か ー石井方式を阻む閉鎖性ー】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。
目次
1 「書字力」の前に「まず読字力」
今も昔も「漢字書取」の力を高めることは、国語教育の難問の一つである。昔から漢字書取は、朝自習や宿題の定番であり、その意味では「不易の指導法」とも言える。だが、その成果や結果はとなると、漢字学力の定着や活用の点から見ても必ずしも良策、得策とは言いきれないようである。
同じ漢字を何回も書かせるという機械的方法は駄目だとよく言われるが、「反復」という原理の有効性までをも否定する訳にはいくまい。反復は学力を定着させる上では、一つの良策であることは間違いない。
書字力というのは「字形」の認識と記憶と再生の統合されたものであるが、「書く」という行動の前には、「読む」「読める」という「読字力」が必要になる。十分に読めるという読字力の前提なしに「書字」の力をつけることは困難であるし、また意味もない。
国語の学力については、日常生活に役立つという観点から考えるならば、まず「読字力」の形成に力を入れるべきである。子供がテストを受ける場合に、問題文や教材文の中に読めない漢字が五つも六つも出てくるようになると、もう先に読み進める気力が持てなくなる。「読めない」「分からない」ということになれば、その子供の答案はいい加減なものになるだろう。
従って、まずは多くの漢字を読めるようにしてやることが肝要である。「書字力の前にまず読字力」という原理を確認しておきたい。

2 「読み書き同時学習」論の無理
学年別漢字配当表は、教育漢字をいつ、どの学年で教えるかということについて設けた一つの基準である。これが定められていることによって、どこの学校であっても、またどの会社の教科書を使っていても、一定の教育漢字を習得することができるようになる訳だ。これは、よいことに違いない。
ところで、この配当表は、漢字が「読めて、書ける」ようにする為に「読み書き同時学習」という指導上の大原則を前提としている。この大原則が問題なのである。
先述したように、「書字力」の前提として「読字力」が必要だというのは当然だ。この考えに従えば、「読字力」と「書字力」とを同時習得させるのは無理だ、という結論になる。「まずは読字力をつければよい」のであって、それに力を注げば、書字力の形成は時間はかかるがさほどの無理をせずとも自ずと叶うようになる筈である。これを「読み書き分離学習」と呼ぶ。
この方式を発見し、その効果を実証したのが石井勲先生(故人、教育学博士)である。石井先生の考えた指導法は「石井方式」と名づけられ、幼児教育界ではその効果が実証され、実感され、喜ばれている。但し幼児教育でも一部の実施園でのことだ。
石井先生は、「読み書き分離学習」を提唱するに当たり、分かり易く次のような譬喩(ひゆ)を示して説いている。
「読字力と書字力とは、譬えて言えば赤ん坊の這うことと歩くこととの違いに似ている。這う行動をさんざん経験しているうちに、だんだん筋力がついてきて立ち上がれるようになる。つかまり立ちをするようになる。やがて一歩、二歩と歩けるようにもなっていく。更には歩行もできるようになる。これが自然な発達の姿である。読字力が十分につけば、やがてさほどの苦労をせずとも書字力はついてくる。文字の形が十分に認識、銘記されているからである。読めるようになったばかりの場面で文字が書けるようにしようと考えるのは、這い這いを始めた赤ん坊に、すぐに立って歩くことを求めるようなものだ。自ずと書くようになるまでは専ら読ませることに力を注ぐべきである」
大略このような考えに立って、石井先生は、「漢字は平仮名よりもやさしい。幼児でも漢字は一向に難しくなく読める」ということを提唱され、御自身で幼児に漢字を教え、幼児がぐんぐん読んでいく姿を広く公開して見せた。この画期的な発見と実証の功績が教育学博士号の授与ともなったのである。

