「自己肯定感」は偉人への憧れから ー「叱らず」に「ほめる」教育批判ー【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第30回】

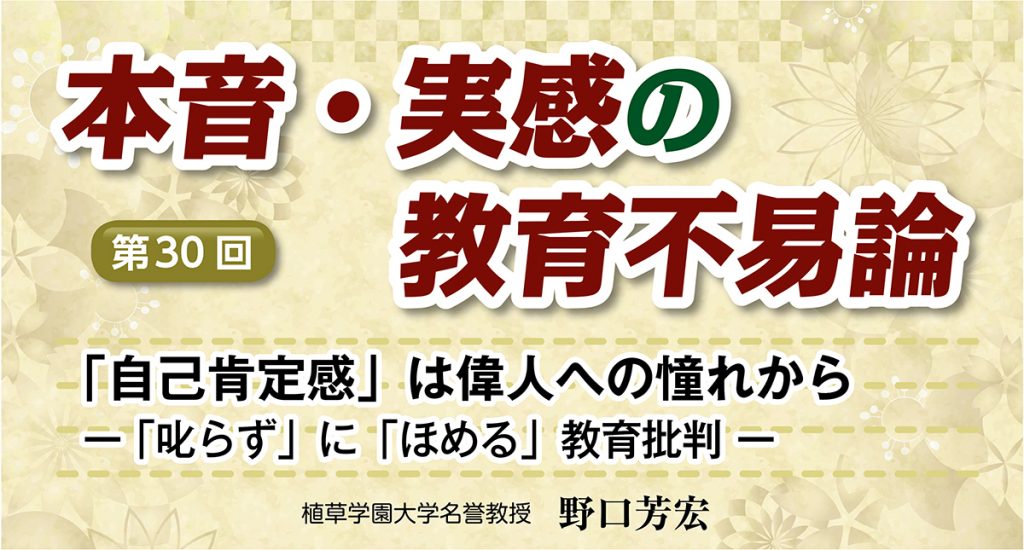
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第30回は、【「自己肯定感」は偉人への憧れから ー「叱らず」に「ほめる」教育批判ー】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。
目次
1 敗戦によって消された軍人と武将
全くの私見であるが、敗戦後の教科書や教育、あるいは教室から消えた話題、または人物に三つ、三種がある、と考えている。
軍人、武将、皇室がそれである。敗戦によって平和国家、民主国家になる大きなうねりの中では、旧来の日本人の誇りや良さまでも否定、破壊、抹殺する必要があったからであろう。
そのことによって、「よくなった」という点も少なからずあったに違いない。だが、同時に失ってはならぬものまで失った点も見逃してはなるまい。一例を引く。
私は海軍士官候補生のとき、私の前を通った偉大な提督東郷の姿を見て全身が震えるほど興奮をおぼえた。そして、いつの日かあのような偉大な提督になりたいと思った。
東郷は私の師である。あのマリアナ海戦(大東亜戦争)の時、私は対馬で待ちうけていた東郷のことを思いながら、小沢(治三郎、後の連合艦隊司令長官)の艦隊を待ちうけていた。そして、私は勝ったのだ。東郷が編み出した戦法で日本の艦隊を破ったのである。
上は、『東郷平八郎』(岡田幹彦著、展転社刊)12ページからの引用であり、語っているのはアメリカ海軍の司令官だったニミッツである。
「以来、ニミッツは東郷の人物に深く感動して東郷を終生の師と仰ぎ、彼のごとき海将にならんと固く心に誓った。ニミッツはこう言っている。」(前掲書P.12)
として先の言葉が紹介されている。
「かつて世界の三大海軍国と言えば、英、米、日であり、その三大国を代表する海将がネルソン、ニミッツ、東郷であった」
とも同書に紹介されている。ネルソンについては、
「1805年のトラファルガー海戦でフランス・スペイン両国連合艦隊を破り、これよりイギリスが世界の海と最大の植民地を支配するに至る基礎を築いた人物である。」
とあり、続いて
「ネルソンはイギリスの誇る世界的英雄であり、ネルソンの名を知らぬ人は世界にない。(中略)だが、ネルソンとともに東郷が、世界の海軍提督中最も偉大なる海将であることは、世界の公論であり、この二人より一人だけ選ぶとするなら、それは東郷にほかならぬことを果たして日本人はどれだけ知っているであろうか。つまり東郷は、古今東西を通じて世界第一の海軍提督として全世界の認める人物なのである。」
と岡田幹彦氏は述べている。
言うまでもなく東郷平八郎元帥は、日露戦争の日本海海戦においてバルチック艦隊を破った英雄である。もし、あの海戦に日本が敗れていたら、日本はどうなっていただろうか。今もって北方領土返還は何らの前進、好転もないままであることを引くまでもなく、日本の国土の大半はロシア領になっていたに違いない、と私は考えざるを得ない。東郷元帥の大恩は語るに余る。
自分の命をかけて国家を守るのが軍人の本務であり、そのような職業は軍人の他にはない。軍人は、国家の大恩人なのだが、今の時代かかることを言うには、随分勇気が必要な不思議な世相である。
一流の軍人は、国家の命運を担う逸材であり、心身、学業ともにずばぬけたレベルの人でなければ務まるものではない。当面の戦争の勝敗のみでなく、識見、判断、勇気、綿密かつ冷静な思慮など全ての総合力がその人を形づくる。時代の新旧、古今を問わず勝れた軍人、武将の功績は、教育の中で特筆すべき人物として子供たちに伝えていかねばならないと私は考えている。
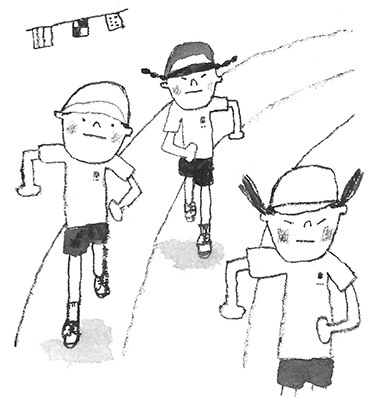
2 「自己肯定感」の低下対策批判
今回述べようとする中心テーマは、「日本人としての誇り」「日本人としての自覚のあり方」といったことである。ここのところ、巷間とりわけ学校でよく耳にする言葉に、「自己肯定感の低下」という問題がある。
内閣府のホームページには「日本は諸先進国に比べて自己肯定感が低い」とあり、その調査データ(平成26年版)が載っている。「自分自身に満足している」という感情が80%台という国は米、英、仏、独であり、70%台が韓国、スウェーデン、日本は46%と低い。成程と思う。
自己肯定感の高い子供の特徴は、
ア 他者を尊重する。相互交流力が高い。
イ 自分の感情の調節ができる。
ウ ポジティブでプラス思考。
エ 万事に意欲的で肯定的に取り組む。
オ 失敗を恐れず挑戦できる。
カ 落ちこまず、比べず、幸福度が高い。
と、よいことずくめである。この反対を考えれば、「自己肯定感の低い」日本の子供の問題は、放ってはおけない。
そこでどうするかという対策として、「ほめることによって自信を持たせる」、つまり「叱らない」「責めない」のがよいと書かれている。──この考え方は広く肯定され、実践されている。「叱らない教育」「ぶつからない指導」の類の書籍が多く出版され、よく売れているようだ。
それでよいのか。このまま広まっていってよいのか。
私は、このような「目先の対応」には懐疑的である。「叱らない」ことによって、「ほめる」ことによって生まれる「自信」などは、本物ではない。「叱られても」「ほめられなくても」「自分自身に満足する」ような子供こそが本物なのだ。叱られること、叱ってくださることは有り難いことなのだ。「叱られる」ことを、暗く、否定的に受けとめること自体が、「自己肯定感の低さ」を証すものだ。「見込みがあるから叱ってくれるのだ」という受けとめ方の教育こそを実践、具現していかねばなるまいと私は思う。

