授業があって指導なし指導があって教育なし【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第11回】

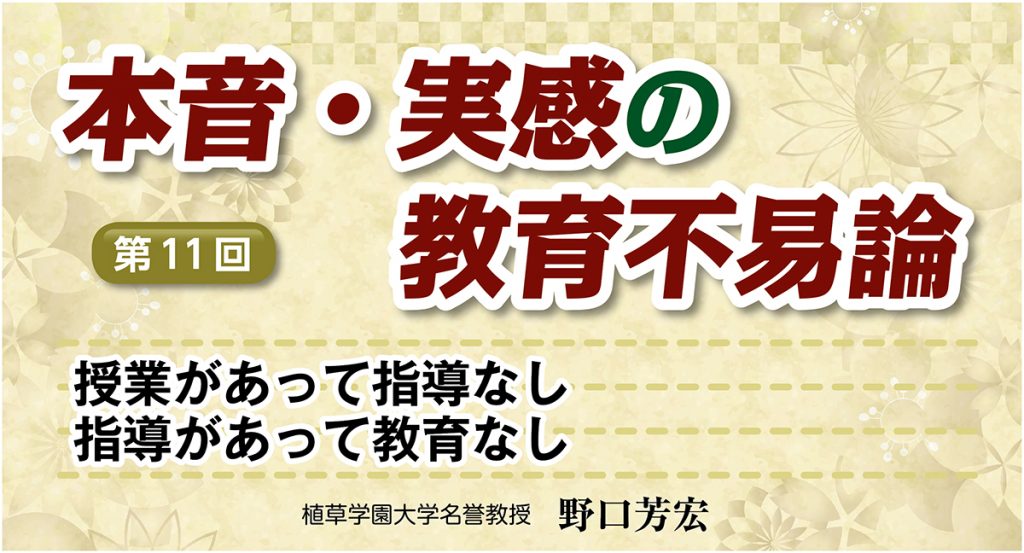
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第11回目は、【授業があって指導なし指導があって教育なし】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVD等多数。
目次
1 従前、現今のままではいけない
「働き方改革」という言葉が流行しているようだ。日本の小、中学校の教員は、世界一労働時間が長く、全般に過労、疲弊の度が高いとも言われている。そのことによって子どもの学力、徳性、体力等が他国に比較して向上していれば何よりなのだがそうはなっていない。いじめ問題も、校内暴力も、学力向上策も、依然として好転の兆しが見えない。つまり、それは、今のままのあり方を続けていっても駄目だ、ということだとも言えよう。そう考えるべきだ。「今のままのあり方」とはどういうことなのか。例えば、多忙、働き過ぎ、遅い帰宅、いつも仕事に追われ通しというような現実を指す。また、授業、指導、教育活動、いずれについても「今のまま」でよいのだ、ということにはなるまい。
現在の全てを否定する、などということを言っているのではない。「これでよい」と思ってやっていることの、「見直し」と「改善」を真剣に考え、具体化すべきだということが言いたいのである。
次のような言葉を耳にしたことがあるだろうか。今回は、この言葉の意味の重さについて考えてみたい。
授業があって指導なし。
指導があって教育なし。
教育があって人間形成なし。
三つに共通する原理は、次のようにまとめられるだろう。
「形の上ではそれらしいことをしているのだが、その目指す実際の価値が具現されていない」つまり「有名無実」「仏作って魂入れず」という原理なのだ。この現実原理にメスを入れて考えてみなければなるまい。

2 授業があって指導なし
「授業をしていますか」と問われれば、現職の教員の全てが「しています」「やっています」と答えるだろう。つまり、行動としての授業、形態としての授業は毎日、毎時どの学校でもなされているということである。だが、それらの授業が本当に「指導」となって機能しているか、という問いを自分に向けた時、胸を張ってどれだけの教師が「然り」と答えられるだろうか。
苦労して物事をほとんど達成しながら肝要の一事を欠くことのたとえ。
この文言は、ある諺の解説文であるが、元の諺が思い当たるだろうか。教師にとって毎時間の授業は決して容易なことではない。それを、毎日毎日やり続けるのはかなりの負担であるが、例外なく全ての教師が日々それをやってのけている。凄いことだ。まさにそれは「苦労して物事をほとんど達成しながら」という表現にぴったりだ。
だが、それらの成果は、となるとどうも捗々しいとは言えない。苦労に値する効果が生まれているか、と問うと、残念ながらそうは言えない。この状況を端的に言ったのが「授業があって指導なし」という言葉である。授業は確かになされているのだが、子どもの学力や社会性や徳性を育み、高める「指導」になっているか、というと必ずしもそうではない。
ある教室に入って授業を見る。教師が子どもに向けて話している。先生に正対し、正視している子も何人かはいる。だが、足を投げ出した姿勢の子、手いじりをしている子、頰杖を突いて窓の外をぼんやり見ている子もいる。だが、授業は授業として進行しているのだ。
教室の板書を写す子もいれば写さない子もいる。何となく教室全体が緩んでいる。しかし、授業は進められている。
ある子どもに音読をさせる。声は小さいし、口を開いていない。張りがない。だが、その子の拙い音読が終わると、みんなが思い出したように一斉に拍手をする。ほとんど意味のない反射的な行動である。拍手された子どもは救われたように少し笑顔になる。
こういう状況は決して珍しくはない。これが「授業があって指導なし」という状況なのだ。なぜ、声が小さく、張りのないぼそぼそ音読を教師は「指導」によって改善しようとしないのか。「今の音読は、Aか、Bか、Cか」と、なぜ評価させないのか。「どこを、どう直せば、もっとよい音読になるのか」と、なぜ問わないのか。
足を投げ出して授業を受ける「心の緩み」をなぜ改善すべく「指導」しないのか。
こんな様子の、こんな調子の「授業」をいくら続けても、教育の成果、指導の成果は生まれまい。「授業」は確かになされているのだが、子どもを何ら「向上的変容」に導くことにはなっていない。「苦労して物事をほとんど達成しながら」というのはこういう状況を指すのだ。
これでは「肝要の一事を欠く」ことになる。何の為の授業なのか、という授業の「根本、本質、原点」が忘れられている。「仏作って魂入れず」という諺は、前述したような「緩んだ授業」にぴったりの「頂門の一針」となるであろう。

