師を戴き、師を仰ぐ ー学びの原点はそこにあるー【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第9回】

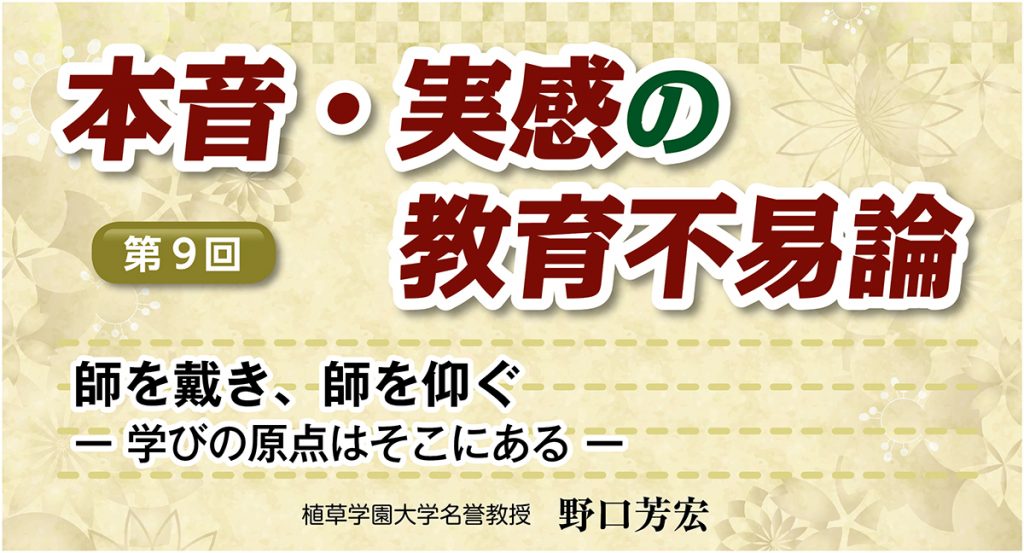
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第9回目は、【師を戴き、師を仰ぐ ー学びの原点はそこにあるー】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVD等多数。
目次
1 師に出会い、師に学ぶ
某日、国立新美術館で開かれた「一陽展」という美術の展覧会に誘われて楽しんだ。500点を超える絵画、彫刻、版画の大作揃いで壮観であった。断然絵画作品が多く、水彩、油彩、パステル、鉛筆画等々が会場を圧している感があった。圧倒される迫力に息を呑む思いだった。
一陽会は昭和30年に設立し、ざっと60年の歴史を有する美術団体であり、その幹部を務める友人に招待されて参上した。友人はいくつかの絵画教室を持ち、プロを目指す新人を指導しつつ、本人も旺盛な制作活動を続けている立派なプロである。
その彼に案内されて全会場を廻ったのだが、いくつかの入賞作品が、彼の教室から生まれていて心を打たれた。彼の教室で学ぶ者は30代から80代までと多彩、多様の人材が学んでいるということだった。私が心を打たれたのは、個々の入賞作品というよりは、「師を持ち、師に学ぶ」という昔ながらの修業の在り方と、その価値についての新たな確信ができたということであった。彼が教えてくれたいくつかの入賞作品は、もし、彼に出会うことなく、指導を受けることがなければ、入賞の栄は多分受けられなかったであろうと私は考えている。
日本の初代総理大臣となり、四度の組閣をし、韓国統監を務め、ハルビンで安重根によって暗殺された伊藤博文は、長州藩士で松下村塾に学び、吉田松陰の大きな薫陶を得て長じている。松陰門下からは高杉晋作、久坂玄瑞、品川弥二郎ら数多の逸材を輩出し、彼らは我が国の近代化を推進した。
その師、吉田松陰は、江戸に出て佐久間象山に洋学を学んで後、海外事情に強い関心を持ち、見識を高め、日本の近代化をリードした逸材として広く知られている。
松陰の師、佐久間象山は、信州松代の藩士で、儒学を佐藤一斎に学び、後に蘭学を修めオランダの自然科学書、医書、兵書などを読破、洋学に精通し、勝海舟、坂本龍馬、吉田松陰らの俊秀を育てている。
この佐久間象山を教えた師匠佐藤一斎は名だたる儒学者だが、一斎もまた中井竹山、皆川淇園、林述斎という大学者を師として学んだのであった。
このように見てくると、師から学ぶことなくして大成した偉人、傑物は一人としていないであろうことが分かる。どんなに偉い人、立派な人も、ある時期はひたすら師に付いてひたむきに学んでいたのである。
「師を持ち、師に学ぶ」という言葉がある。私の大好きな言葉の一つで、私もまたその具現に努めてきた。私は、本当に「師に恵まれた」と心の底から思っている。
私の直接の師を挙げれば、東京帝国大学医学部の俊英だった名内科医の平田篤資先生、書道家の齋藤翠谷先生、国語教育者の高橋金次先生の三方である。もはや三方ともにこの世の人ではない。現在の私の師は、隣の富津市の外科医、俳人、モラロジアンの三枝一雄先生である。三枝先生に師事してざっと20年余りになる。今も毎月一度、我が家に御枉駕いただいて御指導を仰いでいる。
「師事して」と書いたが、「師事」というのは、「師としてつかえ、教えを受ける」ことである。「つかえる」は、「仕える」とも「事える」とも書いて、「身近にいてその人の用を足す。奉仕する。かしずく」ということである。
ここに必須の条件は、「尊敬」と「信頼」の二つであろう。「師事する」というのは、「師を尊敬し、心から信頼して仕える」ことであり、そこには「疑い」や「無視」や「反抗」などは微塵もない。ひたすら、師を尊敬し、師の一言一句をも聞き洩らすまいと、虚心になり、無心になって学ぶことが「師事」である。

2 未熟の自覚が師を求める
私は新米の小学校の教員として出発してから定年までの38年間、小学校という現場でのみ過ごした。定年退職後に、図らずも北海道教育大学の函館校に国語教育の担当教授として勤務することになった。
当然のことながら、私は初めて大学教員として務めることになったので、小学校の教員と大学の教員とではどんな違いがあるのだろうか、ということに関心を持った。
私なりの観察によれば、次の三つのことが違いとして認められることになった。大学教員は、①多くが師を持ち、今も師に学んでいる。②土、休日もかなりの教員が大学に来ている。③簡単に納得せず、とことんつきつめて考える。
小、中学校の教師のほとんどは、①師を持っていない。②土、休日は学校には行かない。③物分かりがよく、簡単に歩み寄る。
この三つの中で、最大の違いは①の「師を持ち、師に学ぶ」という姿勢の有無だと私は思う。とりわけ、書道、声楽、ピアノ、彫刻、絵画などを専門とする教員は、大学の教員になっても旧師からレッスンを受けたり、作品についての指導を受けたりする学びを続けている。
また、大学の教員は、そのほとんどが何らかの「学会」に属して自分の研究を発表し、評価を受けている。「学会」というのは「学術会議」の略語である。そこでの討論や議論は極めてアカデミックなものであり、年功や序列はひとまず外した発言が飛び交う。小、中学校での「研究協議会」とは大きく異なっている。
小、中学校の教師の中でも心ある教師は、現場の当たり障りのない形式的発言に終わる協議会に強い不満を抱いているようだ。その点では大学人研究者による学会は大いに魅力的である。
その基底にあるのは「真理への探究」という謙虚さであり、もっと高まりたいという求道心であろう。それは「師を持ち、師に学ぶ」という心に通ずるものである。
文豪吉川英治は「我以外皆我師」という名言を残している。「師がいない」「師を持たない」場合には、「自分より上の人がいない」ということになり、それはともすると「お山の大将俺ひとり」という思い上がりに傾きかねない。
自分の力不足を知る謙虚さが、自分を伸ばす原点であることを改めて共通確認をし合いたい。

